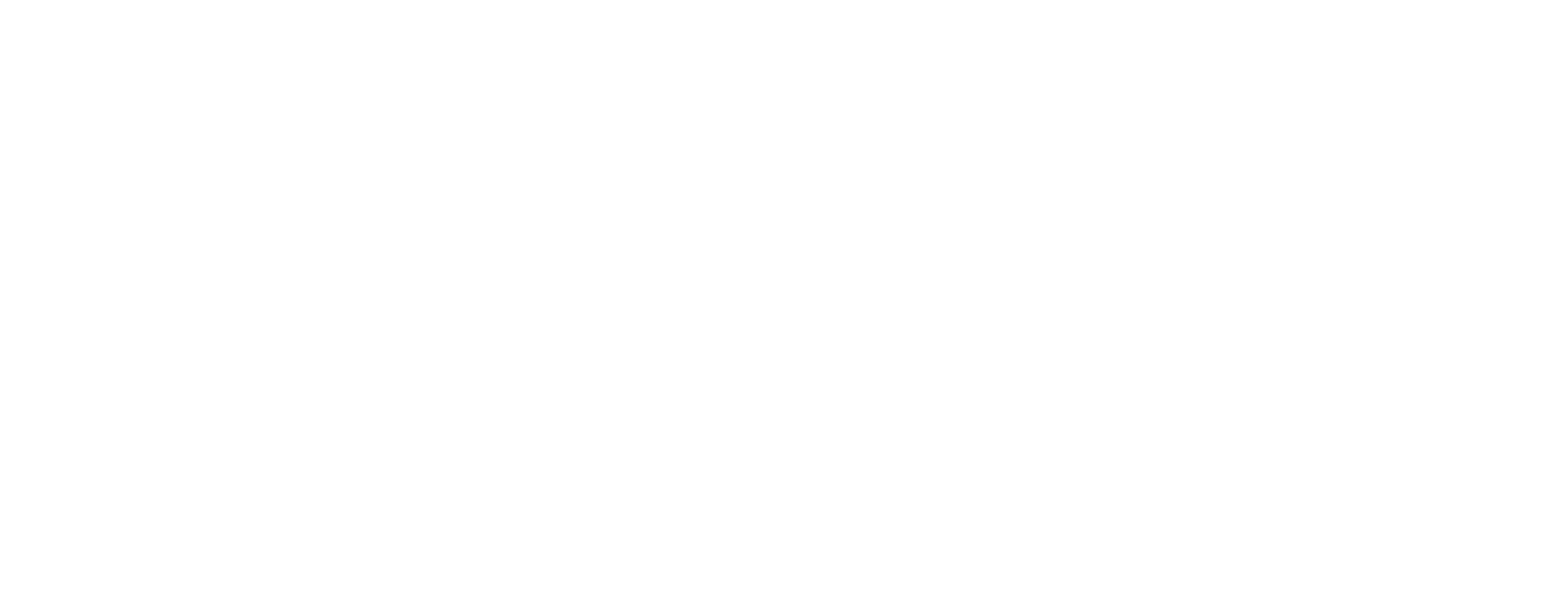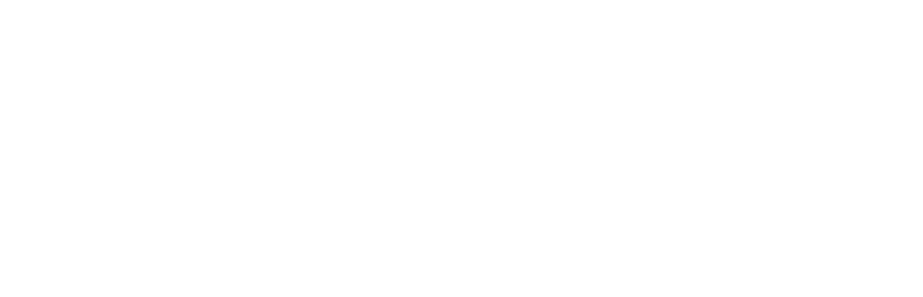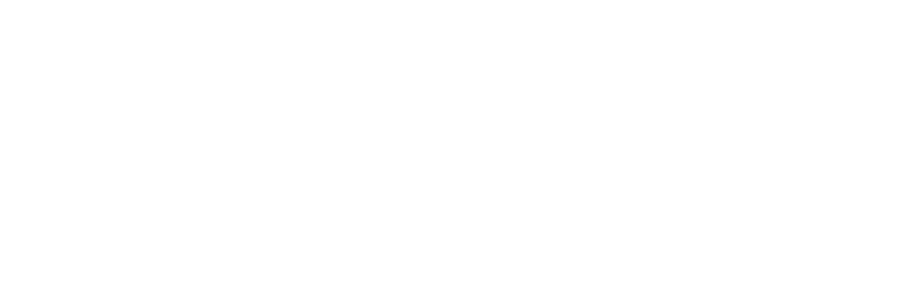ミュージックヴィデオ(以下、MV)はアーティスト、あるいは音楽の
広告であることを目的として制作されてきた。アーティストのイメージを伝え、認知を広め、音楽をもっと売るために。それはMVの本質であり、疑う余地はないだろう。だが、本特集では広告としてのMVではなく、もう一つのMVの本質とその可能性に焦点を当ててみたい。
そのもう一つの本質とは、MVがその黎明期(以前)から試みていた音楽と映像の融合である。例えばダイレクトシネマの先駆者D・A・ペネベイカーが撮影した、最初のMVとも言われるボブ・ディランのドキュメンタリー映画『Don’t Look Back』は、現在のリリックヴィデオの走りでもある。この映画の冒頭では、ディランが歌詞が書かれたカードを音楽に合わせて投げ捨てる。リップシンクを放棄し、所々オリジナルから改変された歌詞と歌のズレは、観客の聴覚と視覚の両面を刺激する。あるいはさらに歴史を遡行すれば、MVの源流にも当たるヴィジュアル・ミュージックでも音と映像の融合=同期が試みられている。
しかし、単に音楽と映像が同期していれば、優れた表現になるとは限らない。作曲家の武満徹はかつて、無音のラッシュ映像から音楽や響きが聴こえてくることがあると述べていた。観者の想像力を刺激する優れた映像に、さらに厚化粧を施す必要はない。映像自体で完結している表現が音楽を必要としないように、優れた音楽もまた映像を必要としない。
それでも、MVはプロモーションでもある以上、音楽に映像を付けなければならない運命の下にある。だからこそ、MVは聴覚と視覚の狭間で揺れ動かなくてはならない。それゆえ、本特集が問うのは視聴覚芸術としてのMVである。その膨大な作品数により全体像を把握できないせいもあってか、日本国内ではMVに関する研究も言説もほぼない。本特集は未踏のジャングルに足を踏み入れるようなものだ。だが、MVが歩んできた聴覚と視覚の実験制作と同じく試行錯誤の果てに何かを見出せる可能性はあるはずだ。MVを通じた視聴覚をめぐる思考の扉を開くため、本特集をお届けする。
INTERVIEW
山田 健人
音楽と映像の番い─MV が表現しうるもの
APPENDIX
ミュージックヴィデオ史 1920–2010s
聴覚と視覚をめぐる試みの歴史
MVエフェクティズム
CRITIQUE
ミュージックヴィデオには
何が表現されているのか
─レンズ・オブジェクト・霊
荒川 徹
アニメーテッドMV、第三の黄金時代
─マイケル・パターソン『a-ha “Take On Me”』からAC部『Powder “New Tribe”』
松 房子
映画音響理論はどこまで
ミュージック・ヴィデオを語れるか
─宇多田ヒカル
『Goodbye Happiness』を例に
長門 洋平
誰のためのパフォーマンスなのか?
─ミュージック・ヴィデオの現在
小林 雅明
なる身体になる
─メシュガーMV 論
吉田 雅史