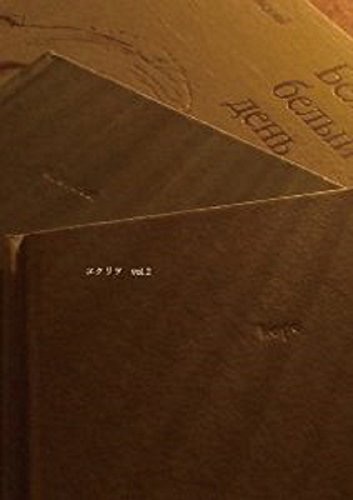総合批評誌『ヱクリヲ』 Vol.2 SOLD OUT/kindle版のみ
Contents
- アンドレイ・タルコフスキー
- タルコフスキーの画面への統御について(深澤匠)
- タルコフスキー作品を観た人は、誰もがその「水」「風」「火」といった自然の表象に目を奪われることでしょう。しかし、それは本当に「自然」なショットなのでしょうか。かつてリュミエール兄弟が最初期の映画において(偶然にも)写し取った「風」という自然の表象は、当時の観客の驚きを得ました。一方で『鏡』を例に挙げるなら、タルコフスキーの「風」はヘリコプターを利用した作為性の高いものです。それは自然(偶然)を機械的に捉えた映像ではなく、作家による統御された画面なのです。前者を「現実のイマージュ」として、後者を「イマージュの現実」として捉えることはできないでしょうか。『惑星ソラリス』では「首都高」が未来都市という「イマージュの現実」として映し出されました。この表象は決して「自然」ではなく、本作以後内省性を深めていくこの作家の内面を映す「鏡」だったのです。
- 傍観者としてのルブリョフ(吉田髙尾)
-
タルコフスキーは『アンドレイ・ルブリョフ』以降、「神」という問題系に接近していきます。なかでもロシア正教会との連関は注目に値します。史実として、ルブリョフが描く図像は正教会唯一の聖像画とされていました。他にも次作「ソラリス」では犬の表象に聖人クリストフォロスの寓意を看取できます。「神」を主題としながらも『アンドレイ・ルブリョフ』ではついぞ聖像画そのものを描くシーンは登場しません。この「不可視性」にこそ、タルコフスキーの宗教観を読み解く鍵があるのではないでしょうか。
-
- 夢現の狭間にあるユートピアーー『惑星ソラリス』について(なかむらなおき)
- 原作者のスタニスワフ・レムは「タルコフスキーが撮ったのは『ソラリス』ではなく『罪と罰』だった」と語りました。確かに、ソラリスは内省のための「鏡」として機能するばかりです。SF的要素を準備しつつも、極めて観念的な映画といえるでしょう。本作でタルコフスキーは何を意図したのでしょうか。『惑星ソラリス』はバッハによるコラール前奏曲で、その幕を開けることになります。通常、この曲は賛美歌を歌う前に用意されるものです。ここで作中の川・馬小屋・犬・「クリス」という名前から連想される1人の伝承上の聖人が、作品を紐解く鍵となりそうです。それは聖人「クリストフォロス」です。亡妻を抱きかかえる行為には、キリストを背負って川を渡ったクリストフォロスの姿が仮託されます。また露正教会ではこの聖人のイコンは犬なのです。冒頭ショットにはタルコフスキーが本作に託した寓意が充満します。
- 『ストーカー』ーー「近代」という桎梏、あるいはタルコフスキーの想像力の臨界(山下覚)
- 『ストーカー』は72年の小説『路傍のピクニック』を基としていますが、脚本にも参加した原作者のストルガツキー兄弟は後に「ゾーンの設定以外は別物」と語っています(彼らはゲルマンの近作『神々のたそがれ』の原作でも知られています)。原作にタルコフスキーはいかなる改変を加えたのでしょうか。群像劇である原作からタルコフスキーは作中人物を3人に限定しています。このうち「作家」に相当する人物は『路傍のピクニック』には存在していません。作家と物理学者、換言すれば「芸術」と「科学」の相克を描いた『ストーカー』が制作されたのは冷戦下という「近代」の限界と直面する最中でした。「芸術」と「科学」の乖離--近代の帰結がもたらすジレンマと、その対立を無化する人智を超えた「ゾーン」が主題となっています。本作はタルコフスキー独自の「水」の表象が決して美しくないことでも知られる作品です。
- 何が映画体験を殺すのかーーアンドレイ・タルコフスキー論(谷口惇)
-
かつて哲学者ドゥルーズは、エイゼンシュテインに代表されるモンタージュを「弁証法的モンタージュ」と称しました。ショットAとショットBを繋げることによって、表象されていないCという新しい意味を産出する技法です。では、その一方で「長回し」によるショットはどんな効果を生むのでしょうか。モンタージュとは対照的に「長回し」によるショットは、描かれえない意味(象徴や観念)を生み出す余地が少なくなります。しかし、この「長回し」の制約に縛られなかったのが後期のタルコフスキーです。具体的な事物そのもの(水や家)を通じて観念的、かつ内省的な主題を描くことに成功したのです。『ノスタルジア』の下記ショットで特に確認できるのが、観念的主題を即物的に描く「長回し」です。同時にそのショットが火や水といった「自然」を捉えつつも、視線の中心化という「作為」があることには注意が必要です。
-
- タルコフスキー・フィルモグラフィー
- タルコフスキーの画面への統御について(深澤匠)
- デヴィッド・シルヴィアン
- ロックシーンに登場したタジオの肖像(中村舞衣子)
-
デヴィッド・シルヴィアンの特徴である「化粧」は、彼が「JAPAN」を結成する以前から行っていたものでした。それは内向的な自身を隠すためであり、またアートスクールを中退する原因にもなります。シルヴィアンはその後にバンドを結成するのです。化粧の意匠からも明らかなようにシルヴィアンはデヴィット・ボウイからの影響を始め、「JAPAN」の楽曲などでファンク、ソウルなど多様な音楽性を取り入れていきます。その背景には70年代後半というパンクの勃興から、急速にポストパンクと移行していくシーンに随行した側面もありました。シルヴィアンが影響を公言するイーノもよく比較の対象とされますが、ソロ活動に限定すれば彼の音楽性の核は「ボーカル」にあり、テクノロジーに価値を見出すイーノとは異なる「身体」性の作家でしょう。
-
- デヴィッド・シルヴィアン 流れと戯れ 後期とその先に寄せて(横山祐)
- デヴィッド・シルヴィアンは82年の「JAPAN」解散後、ソロとしてそれまでの楽曲制作とは態度を異にした活動を続けることになります。現時点での集大成としては、03年『Blemish』が挙げられます。本作はアヴァンギャルド・ギタリストとして知られるデレク・ベイリーも参加しています。そこにJAPAN時代の残滓はなく、シルヴィアンはジャズ・インプロヴィゼーション始め様々な音楽性に接近していきます。イーノやボウイからの影響を公言しつつも、『Blemish』はビートすらない詩とノイズによる独自の音楽となっているのです。かつてアイドルとしてデビューした「JAPAN」ですが、シルヴィアンは現在アンビエントに近い楽曲を制作しながらも、新たな「ポップ」を模索していると語っています。今後もその音楽性の変化を含め、注視すべきアーティストの一人に数えられるでしょう。
- 喪女初聴。デヴィッド・シルヴィアンと「わたし」(丸本文恵)
- シルヴィアン・ディスコグラフィー
- ロックシーンに登場したタジオの肖像(中村舞衣子)
- タルコフスキー x シルヴィアン
- 日々の光ーータルコフスキーの写真とシルヴィアンの写真(淡景)
- タルコフスキーには、79〜84年にかけて撮影されたポラロイド写真集があります。79年とは『ノスタルジア』の制作開始時期で、イタリアでの長期滞在を始めていました。そして、84年とは彼が彼の地でソ連からの亡命を宣言する年でもあります。イタリアへの亡命の2年後にタルコフスキーは逝去することになります。この遺作にも近い写真集の題である『白い、白い日』とは、タルコフスキーが作中で度々引用を行う、父であり詩人のアルセーニーが42年に発表した詩の題でした。これは、当初『鏡』のタイトルとしても想定されていたものです。「白い日」は語義上、「夜明け前」とも解釈され得ます。タルコフスキーのみならず、その影響を受けたデヴィッド・シルヴィアンの写真集をも絡めた論考です。
- シルヴィアン「と」タルコフスキーの狭間をめぐってーーあるいは音楽と映画の結婚(佐久間義貴)
- ブライアン・イーノが提唱した「アンビエント」とは、私たちが普段日常的に行っている「聴くべき音/聴かなくてもいい音」という選別を突き崩すことを意図した概念です。それは、意識の外にある環境音に「恣意的」に耳を傾けることを意味します。ここでタルコフスキー作品の音響を考えてみましょう。『ストーカー』のゾーンを滴る水の音や、『ノスタルジア』の雨の音を印象的に思い出す人は多いはずです。タルコフスキーの「音」は音響派とも通じる性質を持っているのです。ここで同作に影響を受け、同名の楽曲もあるシルヴィアンを検討しましょう。デヴィッド・シルヴィアンの近作はD・ベイリーの参加などインプロヴィゼーションとの接近を深めています。この即興性の高い楽曲群は、そのミニマルさにおいてアンビエントと通底します。シルヴィアンは声を乗せることでタルコフスキーの音響のように自然音を統御するのです。
- 日々の光ーータルコフスキーの写真とシルヴィアンの写真(淡景)
- 特別企画:映画美学校アクターズ・コース修了公演『石のような水』
- 戯曲『石のような水』とタルコフスキーについて(吉田髙尾)
- 演劇稽古レポート:『石のような水』のヤバさ(吉田髙尾)
- 演劇稽古レポート:俳優という乗り物に乗って(なかむらなおき)
- インタビュー:松井周とアクターズ生に聞く『石のような水』(吉田髙尾)
- 舞台本番レポート:ゾーンに影響される私たち。影響されない私たち。(吉田髙尾)
- 舞台本番レポート:俳優という乗り物たちを乗りこなして(なかむらなおき)
- 論考
- 『妖怪ウォッチ』とコミュニケーション(高井くらら)
- 我はパンダなり!…いや、我は人間なり!(なかむらなおき)