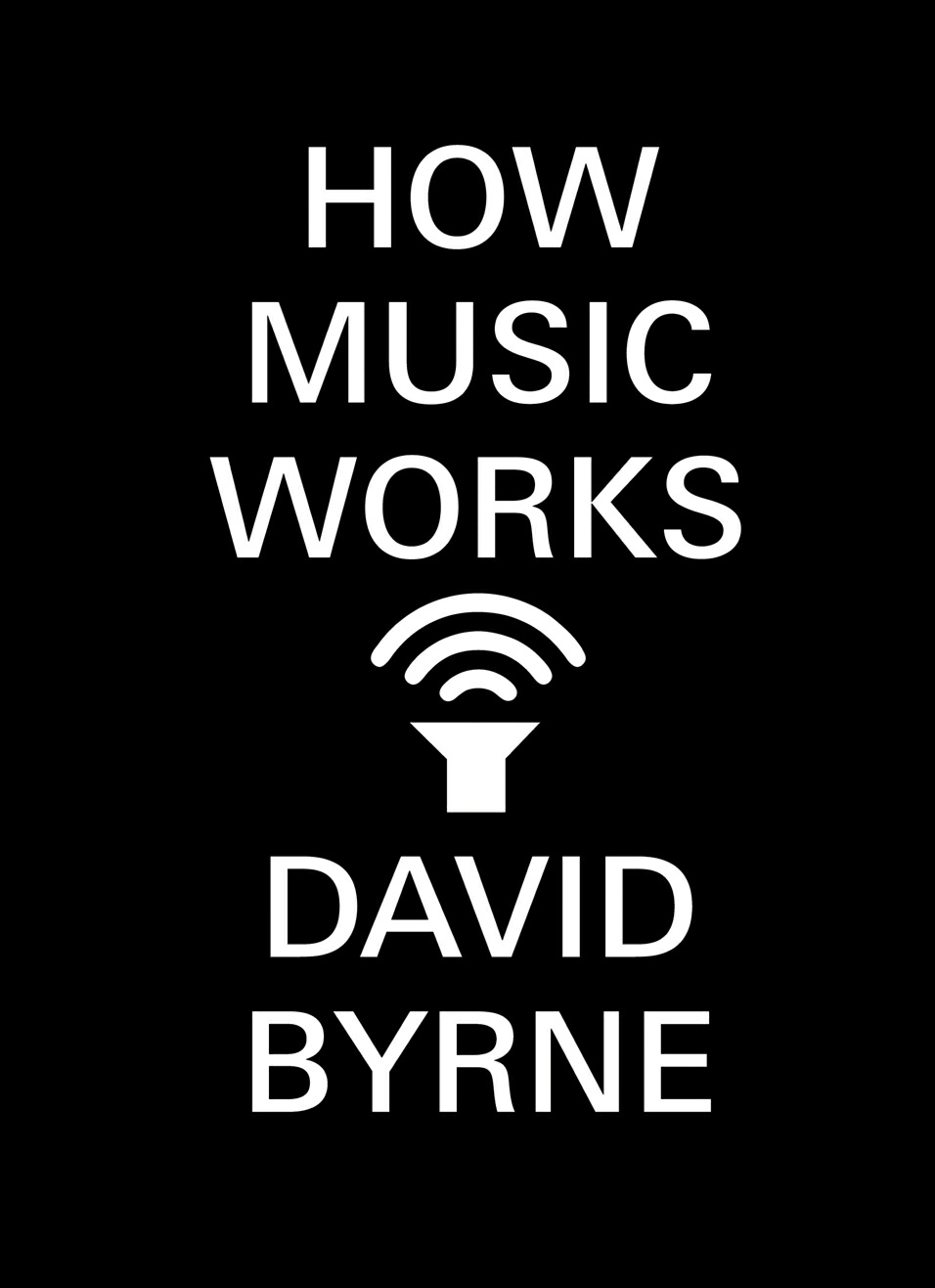 David Byrne “How Music Works”(McSweeney’ s Books, 2012)
David Byrne “How Music Works”(McSweeney’ s Books, 2012)
どの分野の芸術にも「天才神話」というものは付き物である。ある一人の芸術家の脳裡へアイディアやモチーフが、突如として――まるで雷で撃たれたように――降りてきて、マスターピースが完成するという神話は古来より連綿と同工異曲に繰り返し語られてきた。しかし、本当に芸術は一握の「天才」たちによって規定され、更新されてきたものなのだろうか。音楽に関するさまざまな話題のあいだを飛び移り、一見、音楽に関する膨大なメモランダムの集成にも見える本書を通底するのはこの疑問である。
この“How Music Works”のなかでは、トーキング・ヘッズ~ソロを通してのデヴィッド・バーンの音楽活動におけるエピソードや信念を織り交ぜながら、建築、テクノロジー、歴史、ビジネス、スタジオ、果てはハルモニア・ムンディまでさまざまな要素と音楽の関係が例証され、考察される。膨大な要素たちはそれぞれ音楽に変化を加えるものであり、思想やシステム、あるいは場所など多岐にわたっている。要するにここで扱われるのは音楽に影響を及ぼす形で存在し、変革を及ぼしてきた「装置」についてであり、バーンが一見無手勝流とも思える方法で試みているのは、音楽の装置論なのである。
もちろん、メディアが音楽にどう影響を及ぼしてきたか、バッハがどのような環境・場所で音楽を制作していたかなどについての個別の考察はありあまるほど存在する。しかし、第一義的に音楽の実作者である人物によって、自らの作品に限定せず、他者によって制作された多岐にわたる音楽をも対象として、それを取り巻く環境=装置についてこれほどまでに広範にわたって考察された仕事というのは過去に類をみないだろう。本書はバーンの視点を通して、音楽をめぐるさまざまな装置についての情報や考察が統合された、 非 –凡な仕事ということができる。
実は第一章「音楽と建築」の基になった講演がある。2010年にTED Talksとして行われた「いかにして建築が音楽を進化させたか」という約16分間の講演である。この講演は本書の第一章にあたる部分のみが濃縮されたかたちで語られるものであるが、ここで述べられるのは前述のとおり、「音楽がいかにまわりの環境=建築・場所に左右されたか」ということだ。この思考法が最大限に敷衍されたのがこの大部の怪物じみた情報量からなる本書、“How Music Works”ということになる。基調となった講演でバーンが「建築」を取り上げているのは本書の内容を象徴している。バーンは音楽を建築に近いものとして捉えている節も感じとれるのだが、本書の頻出語として、いの一番に思いつくものに「Venue=場」がある。彼の思考のパターンとして、ある場に音楽が構築され、その「場」自体とプラスの要素が音楽を規定していくということが読みとれる。音楽が「構築物として場を持つ」ということが重視されており、それを軸として考察される音楽の概念は――ヤニス・クセナキスと建築の関係を想起するまでもなく――西洋的である。
以上のように、バーンの思考は西洋的であると考えられるが、実は彼自身は非-西洋的なものに惹かれる部分が大きいらしい。本書で挙げられるエピソードに、トーキング・ヘッズ時代の彼が、ライヴを演出するときに日本の能とバリ島のガムラン音楽を伴う劇を参照項にしたというものがある。曰く、西洋の演劇はステージで起こっていることを自然なことに見せかけようとしているが、能のような非-西洋のある種の演劇では自然とは完全に異なるものとして、差異を強調して演じられていることに衝撃を受けた、とのことだ。また、バリ島の劇については生活とガムラン劇が地続きであるものとして境界なく演じられたことに感銘を受けたという言及がある。前者の「能面」に代表される異化効果と呼ぶべきものはトーキング・ヘッズ時代のバーンのトレード・マークとも言えるダボダボのスーツに結実し、後者のバリ島の劇は、演奏者が一人ずつ登場し、彼らが増えていくにつれ、徐々にステージができあがっていくという、過程を見せるステージングに結実した、と彼は述べる。
本書ではほかにも非-西洋の音楽についてのメンションが数多くなされる。非-西洋音楽への積極的な姿勢はトーキング・ヘッズの代表作『リメイン・イン・ライト』(1980)の頃から、サポート・メンバーにアフリカをルーツに持つミュージシャンを加入させたということにも顕著である。彼はそのことについて「みんながバンドの一部となって、一緒に演奏するということが新しいことだった」(第二章)と発言し、人種問題への怒りが背景にあったことを述べる。しかし同時に、「西洋/非西洋」というダイコトミーにこだわることこそが、彼が多分に西洋的な人間であることの証左になっていることは否めない。だからこそ、バーンは、彼にとっての「プラス1」である非-西洋の音楽とそのマナーに非常に惹かれ、それとの接合を試みる。
いま、「接合」ということについて触れたが、この人の定石である「AをBというまったく違ったものに接木する」という発想法にも言及したい。本書第二章に、トーキング・ヘッズ結成前のバーンが、よく知られた曲を違うコンテクストに置き換えて演奏することを常としていたというエピソードが記されている。チャック・ベリーやエディ・コクランをウクレレで演奏したり、スタンダードがインストゥルメンタルで演奏されているあいだ、バーンはただ変なポーズを取っているだけの担当だったり、というようなことである。彼はクラシック音楽に代表されるような、「よく知られた曲をクラシカルなスタイルで上手に演奏する」といったことをかたくなに拒み、変な要素を注入しようとする。要するに、彼は極めて西洋的な人間でありながらも、伝統的な、クラシカルな西洋的人間であることに飽き飽きしてしまっているのだ。そうすると彼が本書で膨大な量の「プラス1」への代入を試みた理由も自明であろう。愚直なまでに繰り返し、繰り返し行われる「プラス1」への代入実験は、バーンがいかに音楽それ自体とがっぷり四つに組み合ってきたかということの証明であり、極めて西洋的な音楽の西洋からの見つめ直しであり、同時にそこからの脱出でもある。全く西洋的な人間が非西洋の文化を見つめ、 反射的に西洋文明への疑義を投げ返す、というこのアティテュードは、どこか人類学者レヴィ=ストロースの姿勢を想起させられるような部分があることも付言したい。
音楽について、途方もない範囲の話題が扱われるこの大著の隅から隅まで、一律に楽しめるという人もなかなかいないかもしれない。この本のなかのトピックは矢継ぎ早に繰り出される手品のようなものであり、素直に驚けるものもあれば、これなら自分にもできそうだ、使えそうだ、というネタもある。一方で種も仕掛けも知っていて楽しめないものもあるかもしれないし、退屈で見ていられないネタやあまりに地味な小ネタも混在しているはずだ。ただ、少しでも音楽に興味を持つ人であればここに書いてあることのどこかに引っかかりを見つけることができるはずである。それはトーキング・ヘッズ時代の思い出話かもしれないし、音楽メディアの歴史についてかもしれない。あるいは、スタジオにおけるレコーディング方法のアイディアかもしれないし、音楽で稼ぐための心得かもしれない。つまり、この本は音楽を聴く人/奏でる人/作る人/学ぶ人/批評する人たちすべてにとって役立つエンサイクロペディアなのである。バーン自身、序章で述べるようにどこから読んでも構わない。建築、民族、東洋、西洋、歴史、メディア、ファッション、アナログ、デジタル、コラボレーション、ビジネス、調和などなど……どこを読んでもバーンが音楽を取り囲む「プラス1」の部分に膨大な量の事物を代入しつづけている。
本書の第二章を読めば話題の充実ぶりが感じられるように、トーキング・ヘッズの活動についての話などだけで一冊の自伝としても充分おもしろいものになったことが伺えるが、この本では、敢えてその話題に終始することを排した。ここに提供されたものはデヴィッド・バーンの音楽活動の単純な「記憶」だけではない。バーンが一人の音楽家として考えていることをできるだけ多く一冊の書物にトレースしようとした「思考」の集成である。この思考の束によって、「音楽は天才の頭から突然出てくるものではなく、これだけ多くの要素の集積の結果の構築物なのだ」ということが本書のなかでは明示された。バーンが試みたように、普段聴く音楽について、それがどのような「装置」において成り立っているのか、実例に即して考えてみることは、その音楽がどのような建築物であるかをくっきりと浮かび上がらせ、場合によってはその音楽に対するわたしたちの聴き方にも作用してくるかもしれない。音楽と向き合っていくうえでの方法論としても非常に実践的な一冊であることは間違いない。
志賀恒彦
※2019年8月24日付でサポートメンバーの出自に関する記述を修正しています












