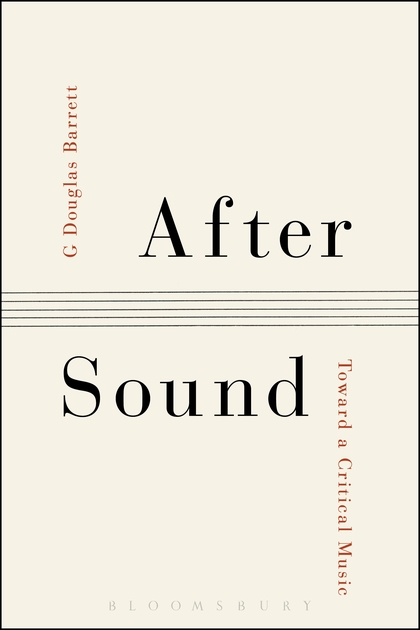G Douglas Barrett, After Sound: Toward a Critical Music(Bloomsbury, 2016年)
「絶対音楽」は、言葉から解放された「響きそのもの」を称揚する。サウンド・アートは、その名の通り、「サウンド」を特権視する。ゆえに、サウンド・アートとは絶対音楽である。Q.E.D(証明終わり)。
この大胆不敵な短絡から出発する本書『アフター・サウンド』は、19世紀から今日まで連綿と続くサウンド遍重の見方からの脱出を試みる。その実践的な方途を、理論家でもあり作曲家でもある著者ダグラス・バレットは「クリティカル・ミュージック」と名づける。古来、音楽は「ハルモニア・リュトモス・ロゴス」の三つ組みとして語られてきた。「クリティカル・ミュージック」とは、このうちの「ロゴス」を実装し直した音楽である。とはいえ、単に歌詞を伴う音楽や標題音楽を指すわけでは、もちろんない。ここでの「ロゴス」の実装とは、すなわち批判性/批評性の獲得を意味する。「クリティカル・ミュージック」は、ときに社会や政治、経済、教育へと介入し、ときに過去の音楽作品や他領域の創作をも巻き込みながら、文字通り決定的なトピックを狙い撃つ。本書は、全6章からなり、こうした音楽の実践を、著者自ら批評しつつ、あらたな概念を練り上げていくのである。
たとえば、キャッシー・ソーントンは教育を下支えする莫大な借金に批判の矛先を向ける。彼女の集団ワークショップでは、借金をグラフなどに可視化した上で、それをリズムやテンポに変換し、身体的な所作や叫びによって宇宙の彼方へと放射する(第5章「哲学の負債」)。あるいは、フェミニスト・パンクロッカー集団のプッシー・ライオットは、女性を排斥し続けるロシア正教会の祭壇を占拠し、歌声をもってそれを糾弾するだろう(第3章「ジジェクがプッシー・ライオットを歌う」)。本書で取り上げられる多種多様な事例はいずれも興をそそるものであるが、以下ではとくに、過去の音楽作品を巻き込んだふたつの実践をめぐる議論を追いながら、その概念の射程を素描したい。
《SILENT/LISTEN》、《4分33秒》の「正しい」(?)演奏
広いギャラリーに白いテーブルがひとつ。着席した人々はマイクを前にしている。ひとりがアナウンスする。「《4分33秒》、ジョン・ケージによって作曲された」……。「時間です、あなたはなにを聴きましたか?」、アナウンサーの質問は続く、「あなたが最後にこの場所でエイズについて語ったのはいつですか?」。「2006年、8月9日水曜日。オンタリオのアートギャラリーでの録音を開始。最初の語り手は、テーブルに来て、レコーダーに向けて発言してもらえますか?」。ひとりの女性がテーブルに歩み寄り、落ち着いた、そして幾分くすんだ調子で、語り出す。
1994年、ふたりのエイズ・アクティヴィストによって設立され、いまや北アメリカやヨーロッパに多くのメンバーを持つ団体、ウルトラ・レッドによる《SILENT/LISTEN》(2005−2006)の一コマである。北アメリカの7ヶ所において行なわれたこのイベントは、《4分33秒》の実演と、エイズに対する語りおよび聴取から構成される。ある場所でなされた語りは録音され、続く場所においてプレイバックされる。「わたしたちはどこにいたのか、どこにいるのか、どこに向かっているのか」を問い、記録すること。ウルトラ・レッドによれば、この作品において時間は、解決を宙吊りにしておき、わたしたちの喪失と深い悲しみが批判的な言葉を獲得するために用いられる。しかし、すでに疑問符が頭の上に浮かんでいるかも知れない。なぜ《4分33秒》なのか?
ジョン・ケージによる《4分33秒》が持つ美学的な意義については今日まで多くが語られてきたが、それは差し当たり問題ではない。ここで論点となるのは、その社会的・政治的・文化的な背景である。
ケージの「沈黙」をホモセクシャルのアーティストとしての態度と関連づける論者は多い。たとえば、モリア・ルースは、1950年代のニューヨーク・アヴァンギャルドの活動を、マッカーシズムによる政治的な抑圧に直面したアーティスト達の「批評的な麻痺」と否定的に特徴づけ、なかでも、ケージの《4分33秒》やチャンス・オペレーションは、「無関心の美学」の最たるものであるとする。対して、ジョナサン・カッツは、ケージの作品をクィア・レジスタンスの歴史のなかでも特異なものとみなす。もっともホモフォビックな時期にあった同時期のアメリカにおいて、「沈黙」はなにより生存戦力であり、ケージはあくまでも「沈黙のパフォーマンス」、「声明を出さないという表明」をしていたのだという。
バレットは、ケージの記念碑的な作品が背後に持つ社会・政治的なコンテクストを折り込みつつ、現在のエイズ・パンデミックを取り巻く「沈黙」に批判的に介入するべく、それを流用する点に《SILENT/LISTEN》の特異性を見出す。さらに、この作品はケージの《4分33秒》だけではなく、アクティヴィスト集団ACT−UPが掲げ、様々なアーティストによって流用の対象とされてきたロゴ「SILENT=DEATH」を踏まえてもいる。こうして、作品の持つコンテクストと解釈とを幾重にもオーバーラップさせる《SILENT/LISTEN》は、あたかも偶然性や不確定性を標榜したケージ作品の「正しい演奏」のようであり、音楽作品における真正性の問題を突きつけることになる。
バレットは次のように述べる。「《SILENT/LISTEN》は、過去の音楽的戦略および視覚的分野の活動家たちの戦略を縫うように進みながら、《4分33秒》を、現在時の批評的対決へと開け放つのだ」(p.37)。サウンドの軛を断ち、ケージの作品の持つ音楽学的・文化的な重要性とエイズ・アクティヴィズムの中心にある美術史的な議論とを領域横断的に読み込みながら、社会や政治に介入し、集団療法的かつアーカイヴでもあるような特異な作品。これが《SILENT/LISTEN》が「クリティカル・ミュージック」たるゆえんである。
《シェーンベルクからの手紙》、シェーンベルクと自動演奏ピアノの二重生成
オーストリア出身の作曲家ペーター・アブリンガーの作品《シェーンベルクからの手紙》(2007)は、同じくオーストリアの作曲家であるアルノルト・シェーンベルクを巻き込んでいく。この作品は、シェーンベルクがレコード会社のプロデューサーに宛てて書いた手紙の文面を、高性能コンピュータを用いて自動演奏ピアノへと変換したものである。当該の手紙においてシェーンベルクは、自作《ナポレオンへの頌歌》(1942)においてバイロンの詩を読み上げるナレーターに、自らの意に反して女性(エレン・アドラー)が起用されたことに対し、怒りを露にしている。
[動画]
https://www.youtube.com/watch?v=BBsXovEWBGo
A Letter From Schoenberg reading piece with player piano, by Peter Ablinger, 2007.
バレットは、アブリンガー作品の注目すべき点として、「ノイズ/言語」、「聴覚/視覚」といった境界性の閾に立つような横断的な在り方を指摘する。はじめ強烈なノイズとして聞かれた自動演奏ピアノの音は、視覚を頼りとしつつ注意深く聞かれることで、言語(もっとも、相当に亡霊めいているが)として認識される瞬間が訪れる。そして、ひとたびそのように認識されたならば、ふたたび純粋な音響として聞くことはむずかしくなる。あるいは、「演奏/再生」という境界。この自動演奏ピアノの音声には、シェーンベルクの肉声の録音をスペクトラル解析したものが利用されている。それゆえ、これは「オートマタ」であると同時に、シェーンベルクという死者と交信するための「フォノグラフ」でもあるのだ。こうして《シェーンベルクからの手紙》においては、「ピアノの発話への生成変化[と]、発話のピアノへの生成変化」が、あるいは、「ピアノのシェーンベルクへの生成変化」が、さらには「アブリンガーのシェーンベルクへの生成変化」(p.115)が生じる。
さらに著者は、作者の意図と演奏解釈、作品の真正性の問題を、録音技術の性質、セクシャリティとアイデンティティ、声といった問題系とリンクさせながら議論を展開していくだろう。《ナポレオン》がファシズムを批判する意図で書かれたこと、そしてなにより、そのスコアには実際のところナレーターの性別は明示されていないことを考えると、とんだお笑い草であるのだが、シェーンベルクは件の手紙において、作曲者としての自らの意志に従うよう権威的に振る舞う(性的な含意もある”bugger”という単語は強烈だ)。バレットは、シェーンベルクの直接の批判が(声ではなく)あくまでも性別に向けられていること、そしてその糾弾が、音源の見えないアクースマティックな録音物を通してなされていることに注目し、次のような問いを投げかける。果たして、トランスジェンダーの歌手、たとえば女性的な声質や声域を有する男性歌手(当然逆のパターンも考えられる)がナレーションを担当する場合、どうなるのだろうか?
このように「《シェーンベルクからの手紙》は、[ボリス・グロイスが「パラドックス・オブジェクト」と呼ぶところの]テーゼとアンチテーゼを同時に具体化した、ひとつのアンビバレンスを差し出す」(p.115)のであり、そうしてサウンド志向から撤退しつつ、音楽あるいは音を巡る様々な歴史的問題へと批判的/批評的に切り込んでいくのである。
批評家が作曲家になり、作曲家が批評家になる
足早に2つの実践を巡る議論を追ってきたが、最後に本書の背後に存すると思われるバレットの問題意識について言及しておきたい。まず理論家として。本書の鍵語である「批評」は、文学理論から影響を受けるかたちでやや遅ればせながら、1990年代以降、とりわけ英米圏の音楽学において盛んに喧伝された。いわゆる「ニュー・ミュージコロジー」と呼ばれるその動向の旗手たちは、それまでのフォーマリズムから脱却し、音楽の意味を文化・社会的なコンテクストのなかでその都度構築されるものと捉え、積極的な解釈へと乗り出した。しかしながら、そこで主な対象とされる楽曲は、やはり19世紀のレパートリーであり、「絶対音楽」であった。「絶対音楽」の意味の欠如こそ、彼らの(ときに主観的にすぎる)構築主義を下支えしていたのだ。この滞留に不満を抱いているであろうバレットが本書において、外側から意味を塗布するのではなく、作品それ自体のなかにこそ批評的な性質を見出そうと試みたのは理にかなっている。ここにそれまでの音楽学における「批評」との大きな差異があり、意義がある。
作曲家として。本稿で紹介したアブリンガーの作例をふまえ、バレットは、2013年にトランスジェンダーの歌手が《ナポレオンへの頌歌》の「トランスクリプション」を歌うという作品を発表した(彼のホームページで聴くことができる)。ここには、クリティカルな音楽作品を批評しつつ、そこからみずからの実践へと折り返し、展開するというプロセスが認められる。バレットの活動においては、作曲行為は批評と分ち難く一体化しているのだ。このように実践へと繋がる種が随所に撒かれている本書は、あたらしい作曲のための手引書として読むことができる。たしかに「クリティカル・ミュージック」は、単に思いつきに頼ったコンセプチュアルな大喜利を打ち出すものではなく、その道はなかなかに険しい。もしこれを批評=作曲しようと思えば、社会や政治、様々な芸術の動向(「ソーシャル・プラクティス」やポスト・メディウム的実践など)、過去の作品の背景・文脈、哲学的な議論などを適切に踏まえる力が、これまで以上に求められるからだ。とはいえ、たとえ道は険しくとも「耳」やエクリチュールの厳しい鍛錬の上に成り立つ従来のハイ・アートとしての「現代音楽」とは別様の道を拓く上で、本書は多くの示唆に満ちている。
原 塁(音楽学、美学)