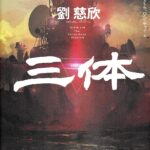※本記事は『エクリヲ vol.14」に掲載されたものです。
Reverse
今の時代における「詩 verse」について考えたい。そのためには、まず詩の不在という現状に対する考察を経由しなければならない。
一見、世の中には「verse 詩」が溢れているように思われる。「Metaverse メタバース」、「Universe 宇宙」、「Diverse/ Diversity 多様な/多様性」といった今の世界を特徴づけるトレンドワードの中には「verse」がしっかりと存在している。しかし、それらの中身を見ると、いずれも「詩」とまったく関係がない。あまりにも無関係であるから、人類史におけるかつての詩の比類なき重要性を考慮に入れると、意図的に「詩 verse」の存在を抑圧しようとしているようにさえ見えてしまう。
今の世界に詩は存在しない。しかし、詩なきこの世界は政治的にも、社会的にも、文化的にもかつての世界へと逆行し(reverse)、行き詰まりつつあるように見える。その逆行と行き詰まりは、詩の不在や詩に対する抑圧とどれほど関係があるのだろうか。そして、詩を取り戻すことでその行き詰まりは打開されるのだろうか。
詩なき世界についてのこの論考は、「Metaverse メタバース」、「Universe 宇宙」、「Diverse/Diversity 多様な/多様性」における「-verse」という脚韻を軸にして、世界が「Reverse 逆行し、反転する」様を描き出そうとする。いずれの「-verse」もほかと必然的な連関はない。その意味で、この論考は論証的というより、むしろ詩的な形式のシミュレーションにより近い。
そうすることによって、世界に詩的なものが再び到来すること、すなわち世界の「Re-Verse 再-詩化」を夢見たいのである。
「Metaverse メタバース」、「Universe 宇宙」、「Diverse/ Diversity 多様な/多様性」はいずれも「これこそ世界の進むべき方向性だ」というふうに、ある種の理想として捉えられている。しかし、「理想」という言葉は本来似つかわしくない。いずれも、そうであることが望ましいのではなく、望ましいかどうかにかかわらずそうなってしまうのが必然だと考えられているからである。「そうしたい」ではなく、「そうせざるをえない」なのだ。
理想の時代、もしくは夢の時代は過去の遺物となって久しい。しかし本来、理想や夢とは、自然が私たちに押し付ける必然性に逆らって、私たち自らにとっての必然性を新たに作り出し、実現させようとする心や社会のあり方である。それが不可能なものだと感じられるようになったということは、自然が私たちに押し付ける必然性をただ単に受け入れるしかないことを意味する。
私たちは自然が押し付ける必然性の時代を生きている。
自然の必然性とは一般的に、エネルギー問題や気候変動といった人類種の生存にとってのある種不可避な限界を意味している。しかし、ここでは「自然」という言葉に、単に自然そのものだけでなく、人類社会のあり方も含めたい。限界問題に直面する時、多くの人は「現実主義」を標榜し、その理念的な解決の不可能性を主張する。例えば次のような考え方がある。「資本主義の社会において格差は現実的に考えて避けられないものである(資本主義システムを越えられない)」。「誰もが国家に帰属しているかぎり外国人の排除は現実の状況に応じてやむをえない、もしくは積極的に行うべきである(国家を越えられない)」。「現実的に考えて戦争は不可避であり、それに備えるべきである(国際政治における軍事の必要性を越えられない)」。いずれも、こういった限界問題に対する容認が不可避であること、すなわち必然性を持つことは「現実的に」考えれば明らかであるというメッセージが含まれている。
他方で、それに対抗するリベラルの側も同様にもう一つの必然性に訴えかけようとする。例えば、「格差は絶対的になくさなければならない」「差別主義者に対してはただちに社会的な死を宣告すべきである」、「戦争は絶対的にしてはならない」と声高に叫ぶが、多くの場合彼らもまた、現在の世界はどのようになっており、どのような世界を実現していくかという具体的な思考や想像を欠いたまま、機械的に自動化した「ポリコレ」の形式にしたがっているにすぎない。このような形式的な「ポリコレ」は、世界を必然性にとらわれた自動機械へと変換してしまう危険性を持つ。
私たちはこの二つの必然性の間に挟まれ、窒息しそうになっている。
ジグムント・バウマンの言うように、ポストモダン以降の世界は液状化し、流動化している。それはそのとおりだが、流体力学が一つの必然的な物理法則(必然的に下に向かって流れていく、など)をなしているのと同じように、それによって世界全体がどんどん必然性にとらわれ、自動化した機械へと凝り固まっていくという側面が強まっている。
そのような世界の情勢の中で現れ、それこそ「必然的に」私たちを閉塞から連れ出すものとして熱狂的に、もしくは当然なものとして受け止められたのが最初に列挙した三つの「-verse」――「Metaverse メタバース」、「Universe 宇宙」、「Diverse/Diversity 多様な/多様性」である。しかし、これから見ていくように、実際には、それらは私たちを閉塞から連れ出し、必然性の壁に穴を空け、そこから新たな空気を入れて私たちの窒息を緩和するどころか、新たな必然性の壁を建設するものにほかならない。それらは必然性の時代への応答として解決を目論むものである反面、時代を逆行(reverse)し、その必然性をさらに補強しようとしているのである。
Metaverse
周知の事実だが、現実の世界は何一つうまくいかなくなっている。拡大する経済格差、戦争を止めるどころかますます煽りさえする政治、人と人の間の分断がますます進む社会、いずれ人類の生存に適さないものへと変化していく自然。
そのような危機的で、絶望的な状況に対して、メタバースはある種の避難所、現実の困窮状況を立て直すための新しい世界として期待される。いわく、メタバースは人間の新しい土地または空間となるだろう。いわく、メタバースはもう一つの現実であり、そこで私たちはなりたい自分になることができる。そして何よりも、新しい現実として、メタバースは資本主義における新たな商材の産出を可能にする場である。したがって、メタバースは必然的に私たちの未来となるほかない。
こういった言説が溢れている。[1]
いうまでもないことだが、これらの言説はメタバースを推進したい者たちが使う宣伝の論理によって貫かれている。そして、私たちの社会はそれをそのまま、つまりベタに受け入れてしまっている。「メタ」を謳う言説を「ベタ」に受け入れるという皮肉。
そもそも「メタバース Metaverse」はニール・スティーヴンスンが一九九二年に発表したS F小説『スノウ・クラッシュ』に描かれたヴァーチャル空間サービスの名称であり、この小説におけるさまざまなアイデアが現在のインターネット環境の誕生と発展に大きな影響を与えたことはよく知られている。つまり、メタバースは新しいものというより、インターネットの黎明期に逆行(reverse)して見出されたものである。
「metaverse」という概念は、「meta-」という「高次の、超えた」といった意味を持つ接頭辞に、「universe」(宇宙、世界)を合わせたものである。したがって「宇宙を超えた宇宙」または「高次の宇宙/現実」といった意味になるだろう。しかし、宇宙を超えた宇宙とはいったいどんな宇宙なのか。それを字義通りに解釈するならば、私たちが観測できる宇宙を超越したもの、例えば、三次元の宇宙に対する十一次元の宇宙、現在ある宇宙の外部にある宇宙といったようなものでなければならないのではないか。
実際のメタバースは明らかにそういうものではない。それは最新のデジタル技術と通信技術をベースにしたヴァーチャル・リアリティ以上のものではない。
表面上、それはV Rゴーグル、アイトラッキング、ハンドコントローラーなどの技術を駆使して、人が完全に没入できるようなインターフェイスを構築することで、S N Sの一般化によって言語的コミュニケーションがかつてなく支配的になった世界において、非言語的なコミュニケーション、つまり空間と身体を通じたコミュニケーションを復活させようとしているように見える。そのため、現在のV Rは実際の身体を模倣する方向へと向かっている。しかし、身体の模倣は身体そのものではなく身体の地図を作ること(マッピング)であり、身体を記号的に縮減していくものである。身体を完全に再現すること、領土と同じ大きさや情報量を持つ地図を作ることではない。したがってそれはむしろ身体を、単なる視覚的情報としての身振りの記号へと切り詰めていくことで、身体の文法化または規範化というある種の必然性を持つ方向へと向かっているとも考えられる。
さらに、メタバースを裏返しにする(reverse)と、右に述べた欺瞞に加えて、一種の高次の=メタな搾取が存在していることがわかる。というのも、メタバースは何よりもMeta(旧Facebook)などのプラットフォーマーが行き詰まったビジネスモデルを刷新し、新たな営利モデルを作り出して、覇権を取り戻す(regain)ための戦略である。それは新たな商材を作り出し、新たな利益を生み出すための新たな仕掛けである。Metaだけでなく、Google、Apple、Microsoft、Amazon、Tencent といった高次のプレイヤーは相争ってこのゲームに参入しようとしている。その背景には単にS N Sの飽和状態だけがあるわけではない。むしろS N S全体に込められていた理念、ユートピアの実現という理念の失敗がある。メタバースとは、その失敗を覆い隠すために、『スノウ・クラッシュ』の見せていた未来、現在ではすでにノスタルジアとなってしまった未来へと再び戻り(return)、ユートピアの夢とその失敗という無意味なサイクルを再起動する(reboot)ためのものである。今度こそより盤石な収益モデルをあらかじめ織り込んだ形で。メタバースに生きる者たちにとっての世界は、高次の=メタな主体としての運営者にとって、自由に操作可能な、利益を得るための客体でしかないのだ。
したがって、メタバースとは一種のレトロフューチャーである。それは未来というより、未来の不可能性を示している。
中国のS F作家劉慈欣は短編小説「共存できない祝日(不能共存的节日)」(二〇一六年)において、人類全体がメタバースの中に入ってしまう世界を皮肉な筆致で描いている。高次の存在である異星人が、人類がより高次の存在として再誕 (rebirth)できるかどうかを観察するために地球にやってくる。しかし、人類は完全なヴァーチャル世界、すなわちメタバースを開発してしまう。
「未来のヴァーチャル世界はたしかに天国でしょう。そこでは誰もが実際に神になれます。想像を絶するほど素晴らしい世界になるでしょうね。私はその時の現実世界を想像してみたいと思います。まず、現実で暮らす人間はどんどん少なくなります。誰もが我先にと自分をアップロードしていきます。ヴァーチャルな天国がこれほど素晴らしいなら、苦しみに満ちた現実にいつづけたいと思う者はいないでしょうからね。地球からどんどん人間がいなくなっていき、最後には現実から人類がいなくなってしまうでしょう。世界は人類が現れる前の状態に戻り、森林と植物がすべてを覆い尽くし、野生動物の大群は自由に動き回り飛び回る… …それに対して、ある大陸のある片隅の、地中深くに地下室があり、そこで一台の巨大なコンピューターが稼働していて、その中に何百億もの人類が暮らしています」[2]
高次の存在である異星人はメタバースに入り込んだ人類が必然的にそうなり、地球という世界全体が人類が現れる前の状態へと逆行する(reverse)ことを予言する。彼らがこれまで多くの星で実際にそれを目撃してきたからだ。発展した文明はみなメタバースの中に引きこもったからこそ、これほど広大な宇宙がこれほどの静けさを湛えているのである。宇宙がこれほど長く存在し、地球のような惑星が多くあるにもかかわらず、異星人が見つかっていないというフェルミのパラドックスは、現実の苦しみに耐えられなくなった文明がみなメタバースの中に入り込んでしまったことによって生じたというわけだ。
このように、人類のより高次の存在への再誕は失敗に終わる。高次の存在である異星人は人類がメタバースを発明した日を「流産祭」として記念する。それは私たちに未来が存在しないことを意味する。劉にとって、人類という種族がより高次の存在に進化する道は「宇宙 Universe」へと出ていく以外にないのだ。
Universe
宇宙は、Universeは、二〇世紀の半ば過ぎまで、無限の可能性を象徴するものだった。S F小説やS F映画の中では、人間は宇宙へと進出し、さまざまな苦難を経験しながらも、新しい世界を発見し、可能性を発掘していった。フロンティアとしての宇宙は、現在私たちのいる場所の否定であったと同時に、新しい場所の出現の絶対的な肯定でもあった。それは宇宙という空間の無限性に偶然性の無限生成を夢見ていた時代だった。しかし、現在の宇宙に対するイメージは明らかに裏返され(reverse)、完全に反対のものになっているように思われる。偶然性と可能性が生まれ出る場所としての宇宙は、現在ではむしろ必然性を導き出す装置として機能するようになった。
前節で、劉がメタバースを知的な文明を必然的に滅亡させるものとして描き、それに対抗するためには宇宙に向かわなければならないとしていることを論じた。しかし、彼は同時に、その必然性と対立する、(可能性ではなく)別の必然性を持ち出す。
世界を席巻し、エンターテイメントにとどまらず現代におけるある種のダークな世界観の一般化の象徴的存在でもある劉慈欣の長編S F小説『三体』三部作(二〇〇八〜二〇一〇年)は、まさに必然性の装置としての宇宙を前面に打ち出した作品である。劉は黄金時代のアメリカS Fを理想としながらも、その作品においては宇宙に理想と可能性を見出すのではなく、むしろ一種の論理的な必然性を見出そうとしている。〈三体〉シリーズは、人類と接触した異星人「三体人」の侵略艦隊が到着するまでの四〇〇年の間に起きた人類社会の変化、さらに太陽系がより上位の異星人によって滅ぼされ、宇宙全体の終焉を目撃した人類の生き残りを描いた作品である。
シリーズの第一部である『三体』は主にその出会いのきっかけと三体人の存在を知った直後の人類社会を描いている。『三体』は独立した三つのパートによって構成されている。それぞれの主な舞台は、文化大革命時代の中国、『三体』というV Rゲーム、そして「現在」の世界である。その三つのパートの中で、人類は自身についての真理、そして宇宙の真理を発見する。
まず文化大革命のパートでは、人類がいかに悪をなしうるかということが中心的に描かれている。当時の中国でなされた悪は、中国に限定されず、世界でなされた悪、人類全体の悪へと接続されていく。人類とは必然的に悪をなし、世界を滅ぼす存在として同定され、否定される。次のパートで描かれる『三体』というV Rゲームは、「三体人」という地球侵略を目論む異星人が、必然的な滅亡によって特徴づけられた三体人の歴史を人類に体験させ、共感させるために作り、配布したものである。彼らは絶えず迫りくる絶滅の脅威にさらされながらもなお必死に生きようとしているのに、人類は恵まれた環境にあるにもかかわらず悪をなし自らを滅ぼそうとする。ならば、いっそのこと地球という世界を彼ら三体人に明け渡してしまえばいいのではないか。このように、V Rゲームにのめり込んだ者は現実の否定へと行き着く。最後に、「現在」の現実世界のパートでは、物理法則そのものがより上位の存在者によって偶然に決められたもの、絶対的でも必然的なものでもないものとして提示される。それによって、多くの人間は「人類は必然的に滅ぼされる」と絶望する。
作中では、その絶望的な世界観が「射撃手(シューター)と農場主(ファーマー)」という形で表現されている。
射撃手仮説とはこうだ。あるずば抜けた腕をもつ射撃手が、的に十センチ間隔でひとつずつ穴を空ける。この的の表面には、二次元生物が住んでいる。二次元生物のある科学者が、みずからの宇宙を観察した結果、ひとつの法則を発見する。すなわち、“宇宙は十センチごとにかならず穴が空いている”。射撃手の一時的な気まぐれを、彼らは宇宙の不変の法則だと考えたわけだ。
他方、農場主仮説は、ホラーっぽい色合いだ。ある農場に七面鳥の群れがいて、農場主は毎朝十一時に七面鳥に給餌する。七面鳥のある科学者が、この現象を一年近く観察しつづけたところ、一度の例外も見つからなかった。そこで七面鳥の科学者は、宇宙の法則を発見したと確信する。すなわち、“この宇宙では、毎朝、午前十一時に、食べものが出現する”。科学者はクリスマスの朝、この法則を七面鳥の世界に発表したが、その日の午前十一時、食べものは現れず、農場主がすべての七面鳥を捕まえて殺してしまった。[3]
つまり、「射撃手」と「農場主」の寓話とは、人類世界全体の秩序が偶然なものであることを示すと同時に、圧倒的な高次の存在に対して我々は手も足も出ないという絶対的な必然性の存在を人類に思い知らせる物語である。
三つのパートは形こそ違えど、人類の絶滅に対していずれもその必然性を再認し、あるいはニヒリスティックに諦め、あるいは興奮した調子で歓迎している。こうした必然性は人類を恐怖に陥れると同時に、ある種の魅力を持ってもいる。人類が必然的に悪をなすことは絶望の源であるが、「三体人」という高次の存在がそんな悪をなす人類を必然的に滅ぼすことは救いでもあるのだ。[4]
宇宙における物理法則は物理学の対象ではなく、むしろ社会学(または戦争学?)の対象であり、より強力で優位なものたちの間の闘争とパワーバランスによって決定されていくという宇宙観は何も劉のオリジナルではない。これはスタニスワフ・レムがすでに「新しい宇宙創造説」(一九七一年、『完全な真空』所収)できわめて説得的な形で展開した理論的なヴィジョンである。そこでは、宇宙の物理法則は自然で必然的なものではなく、高次の=メタな存在たちの間の闘争によって形成されたものであり、その闘争は現在も続いているがゆえに、宇宙の物理法則はなお形成と変化の途上にあって、操作可能なものである。これはある意味、宇宙がメタバース化したイメージともいえる。Meta、Google、Apple、Tencent といった高次の存在の争いの結果によって世界(=メタバース)の物理法則(=アーキテクチャ、またはプログラム)が決定されていく。
ここには一種の逆説がある。物理法則、もしくはより広く自然の必然性そのものがある種の偶然の結果だと暴露されたことで、むしろ私たちの必然性の感覚がより強固なものになっていくという逆説である。物理法則が集合的な社会的関係(正確には「知性を持つ文明」同士の関係)におけるゲーム理論的な戦略論へと転じた途端、私たちは何もできなくなってしまうのだ。ゲームの中で最適な戦略を探ることしか生き延びる道はなく、そのゲームのルールから外れた者を待っているのは支配される運命のみである[5]。
ここには神に近い力を持つ高次の主体たちと、それらの主体によって客体化される低次の主体という対立構図が存在している。主体が成り立つためには、確固たる客体の存在が必要である。そのため、主体同士の闘いとは、相手を客体化しようとする闘いとなる。より高次の力を持つ主体の前では、人間という低次の主体はそれとの闘争に敗れ、客体化される。主体たちが形成する秩序は客体化された人間にとっては必然性を持つ自然となるが、その自然は単にそのまま存在しているのではなく、恣意的に操作される対象となっているのである。
メタバースへの退却は、こういった主体同士の、相手を客体化しようとする闘いから撤退することを意味する。メタバースという「誰もが実際に神になれ」る、「想像を絶するほど素晴らしい世界」では、誰もが他の主体によって客体化されることなくすべてを客体化でき、劉やレムの描いた宇宙におけるような、神の力を持つ高次の主体でいられるのだ。[6]
メタバースにおける「meta-」もまたこの意味で理解できる。それは必然性の次元から自由になるために、宇宙的な高次性に縛られ、とらわれ、支配されること自体から降りること、高次性へと向かうことに対する逆行(reverse)を目論むようにも見えるが、実際には完全に客体化、支配された世界において、高次性を持つ主体をシミュレートしているにすぎないのだ。
メタバースが私たちに救いをもたらすことはない。
Diverse/Diversity
前節では、メタバースの否定として導入された必然性の装置としての「宇宙 Universe」は、「メタバース Metaverse」への退却、高次性に対する逆行(reverse)の正当化につながることを論じた。
しかし、それは宇宙のルールの全的な拒否を強制する(「こうするしかない!」)という意味で、必然性にとらわれていると言わざるをえない。「共存できない祝日」で描かれたように、そのようなメタバースは現実の拒否をその存立条件としている点において必然的に現実から人間を絶滅させるからだ。また、それは、Meta、Google、Apple、TencentといったIT巨頭、つまり高次の存在のゲームに完全に支配されてしまっているという意味で、むしろ宇宙論的な必然性をいっそう推し進めたものともいえる。
そのようなメタバース像とは反対に、そうはいってもむしろメタバースをある種の多様性を実現するための場として利用することもまた可能ではないかと考える向きも多い。例えば、現実世界で主体同士の闘いに参加したい人は参加すればいいし、したくない者はメタバースの中に安住すればよい、と。または、みなそれぞれ異なる欲望の形を持つがゆえに、それぞれの欲望が互いに衝突せずに、自らを実現する場を確保することが大事なのではないか、と。
その背景に「多様な/多様性 Diverse/Diversity」という、時代を代表する思想の存在があるだろう。ごく簡単にいうと、社会的にマイノリティであることは、客体化されることを強いられるが、それを避けるためには多様なものに対する配慮が必要だということである。客体化の強制については例えば「ステレオタイプ」がわかりやすいだろう。「中国人はこういうものである」、「女性はこういうものである」、「ゲイはこういうものである」といったステレオタイプな認識は、現実的には「◯◯はこういうものであるべきだ」という強制力として働く。マジョリティたちがゲームのルールを制定し、マイノリティはそれを必然的なもの、不可抗力として受け入れるように強制されるのだ。そのルールはしばしばマイノリティを傷つけ、否定し、その権利を侵害するような結果を招く。
マイノリティも含めて誰もが生きやすく、その人権を尊重されるような社会を築くためには、多様性への配慮が必要だというわけである。それを前提として、ポリティカル・コレクトネスや多文化共生といった概念が広く認知され、実践されるようになっている。しかし、よく知られているように、例えばポリティカル・コレクトネスが独断的な規範をもって世の中を雁字搦めにしようとしているというポリコレ批判は、世界中で日に日に強まっているという現実も存在している。こういった批判はいわゆるマジョリティから発される時、マイノリティに対する嫌悪の念から排除を意図している場合が非常に多いが、とはいえ、多様性の推進自体にもいかがわしさがないわけではない。
現在の多様性に関する議論は主に経営学の分野で行われ、発信されている。いわゆる「ダイバーシティ・マネジメント」や「ダイバーシティ&インクルージョン」といったものだ。日本では経済産業省が推進している「ダイバーシティ経営」などが代表的だろう。経産省はダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につ7なげている経営」であると定義している。[7]つまり、人権を尊重すること自体が目的なのではなく、多様な人材の起用が結果的に利益につながるがゆえの施策であり、このような目的による多様性の推進は、むしろ多様性の土台を掘り崩すことになる。社会学者の岩渕功一は、以下のように指摘する。
多様性/ダイバーシティは食べ物やファッション、音楽、ダンスなどの社会の中心に位置するマジョリティにとって都合よく消費できる文化差異と結び付けて奨励される。そうした〈エスニック〉文化は社会を豊かにするものとして寛容されるが、その受け入れは既存の権力構造に挑戦したり、中心と周縁の不平等な関係性を変革したりすることから遮断されている。[8]
言い換えれば、多様性/ダイバーシティはマジョリティの利益獲得ゲームのルールブックに則ったものにすぎず、新たな排除の基準を設けているにすぎないということである。それによって、「多様性/ダイバーシティは社会に『問題』を引き起こさず、経済的にも有益だと評価される一方、経済的に有益と評価される個人の資質・能力と結び付けられるエスニシティや人種化された差異をめぐる差別・不平等の問題とその取り組みは後景化されてしまいがちになる」[9]。ここには「ダイバーシティ」や「多文化共生」といった言説の欺瞞があり、人権の後景化をもたらすという意味で社会的な逆行(reverse)を引き起こしている。
多様な者たちが共存する社会というのはたしかに理想的である。しかし、そもそも「diverse」は語源的に「離れて別々の方を向く」という語義から「多様な」の意味が派生しているのに対して、「社会 society」の語源であるラテン語の「sociō」は「一体化する unite」という原義を持っており、そこに深刻な対立が潜んでいる。私たちのいう多様性のある社会とは、「一体化」できるような多様性のみを歓迎し、それ以外を排除する社会にほかならない。「unite」された「diversity」は、もはや多様性の場ではなく、前節で論じた高次の主体(=マジョリティ)たちが必然性に則って争奪ゲームを繰り広げる場としての「Uni-verse」へと反転する(reverse)だろう。[10]
では、多様性を真に実現するための理想的な条件とはどのようなものなのか。
アニメ映画『羅小黒戦記』(二〇一九年)は神話上の妖精(=神)と人間が共存する世界、より正確には共存することの難しさと向き合わざるをえない世界を描いている。妖精たちは人間ほど種としての同質性をもっておらず、数も少ないため、マイノリティ的な多様性の象徴だといえる。この世界の「原住民」であり、神であった妖精たちはどんどん人間から生活の場を奪われていくも、妖精会館という妖精の組織を作り、人間との共存を管理する。
ここで注目したいのは、マイノリティであり、かつ人間から生活の場を奪われる妖精たちが、言ってみれば「多文化共生」のための組織を運営していることである。人間たちは妖精たちの存在自体を知らない。何らかのトラブルによって妖精の存在が露見した場合、妖精会館が人間の記憶を消して、後始末をする。
ここでは現実でのマジョリティとマイノリティの関係性が逆転(reverse)している。現実では抑圧する側がマジョリティであり、彼らが多様性や多文化共生を謳い、その制度を運営し、包摂と排除の基準を設定しているが、『羅小黒戦記』ではマイノリティたちが圧倒的な力、それこそ神の力を持ちながらも、決して人間を抑圧したり排除したりせずに、抑圧され排除される者として、あるいは人間社会に溶け込もうとし、あるいは人間世界から離れて自分たちで暮らしているのである。さらに、現実ではマジョリティは意図的にマイノリティを排除するのに対して、『羅小黒戦記』ではマイノリティ自体がマジョリティにとって不可視の存在であり、それを可能にしているのはマイノリティ自身の力の行使である。
なぜ彼らは神(に比肩しうるほど)の力を持ちながらも、このような構造を維持しているのか。
妖精=マイノリティたちは自らの力の恣意的な使用を自らの自由意志で禁止し、人類との共存の仕方を模索しているのではないかと考えられる。妖精たちは神として高次の存在である。彼らが望みさえすれば高次の存在として主体性をかけて闘い、人間を客体化していくという必然性のゲームを展開できるだろう。しかし、それは共存とは程遠い世界にならざるをえない。彼らが自らの力を行使するのは、あくまで共存にとって有用である場合のみであり、それ以外の目的のための使用は固く禁じられている。すなわち、神の力はマイノリティと人間の権利を守ることにのみ使用できるのだ。彼らの中で圧倒的な力を持つ者たちは「執行人」と呼ばれ、人間と妖精の両方の権利を守るために存在していることも象徴的である。言い換えれば、ここでは神の力は高次の主体による恣意的な支配のためにではなく、それとはまったく反対の理由、すなわちその支配の禁止と制御のためにこそ行使されているといえる。
妖精=神は自らの主体的な欲望、すなわち神の力を行使し他者を客体化したいという欲望から自由になっている。それは主体性をかけた必然性の闘いから自由になっていることも意味している。そこから妖精と人間の共存のための形が生成される。ここでは、妖精たちは神の力を独占し恣意的に行使することを放棄し、主観的ではない、客観的で公共的=コモンなものとして差し出している。この映画の悪役はまさにほかの妖精たちの力を奪い、独占し、それを行使することで人間を排除しようとする者であり、それを阻止する主人公は「自らの意のままに操ることができる世界」(それこそメタバースや高次の存在にとっての宇宙のような世界)を放棄する者であるという対立構造からも明らかだろう。
新しい共存的な世界が生まれるには、神の力は客観的で、公共的=コモンなものでなければならないのだ。とはいえ、現実は残念ながらこのようにはなっていない。今の「Diverse/Diversity 多様な/多様性」を称揚する風潮に欠けているのは、このような客観性や公共性に対する批評的な思考である。そして、現在において詩と詩的なものについて再考する必要性もまさにここにある。
Verse
世界は必然性の中で逆行(reverse)し、「Metaverse メタバース」、「Universe 宇宙」、「Diverse/Diversity 多様な/多様性」はすべてその装置として徴集、搾取される。しかし、その搾取の中においてさえ完全に姿を消してしまっているものがある。この三者の併置によってはじめて顕あらわになるもの、すなわち「詩 verse」である。
詩とは何か。詩は何をなしうるか。
今日ではもはや問われることのないこれらの問いを改めて考えてみたい。
映画『Dead Poets Society(死せる詩人の会)』(邦題『いまを生きる』、一九八九年)では、故ロビン・ウィリアムズが演じる英語教師ジョン・キーティングが、自らの意に反して厳格な規則を持つ全寮制の進学校に入れられ、親や社会からの「〜になるべきだ」という必然性の命令にしたがって生きていくうちに、自らの人生に意味を見出せなくなった男子高校生たちに詩の意義を教える。彼は授業でウォルト・ホイットマンの詩「O Me! O Life!」を引用する。
O ME! O life! of the questions of these recurring,
Of the endless trains of the faithless, of cities fill’d with the foolish
… …
What good amid these, O me, O life?
Answer.
That you are here — that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.
繰り返し現れる疑問、終わりのない不信、愚かさに満ちた社会……そのような世界からどんな善きものを見出すことができるのかという問いに対して、まさにここにいること、自分として存在していることによって、世界という力強い演劇に自分の詩(verse)を寄与できるだろうという答えが差し出される。悪や愚かさに満ちた世界に対して、自らの存在と実存をもって、それを劇として演じ直し、自らの詩を入れ込むことが重要だということである。
詩とは生きることであり、世界という集合的な演劇の一節をなすものである。
ホイットマンを引用した後に、キーティングは生徒たちに問いを投げかける。「きみはどんな詩を?(What will your verse be?)」と。
実際、彼の授業は単に詩を読み、解釈するものではない。常に、どのように生きるかということを問いかけながら行われていた。詩の教科書のイントロダクション部分をすべて破り捨てるように生徒に要求したり、新しい視点に立って物事を見られるようにと生徒たちを机の上に立たせ、周りを見回すように勧めたりする。体を動かす授業も多く、例えば普段の歩き方とは別の自由な歩き方を試みたりする。もし文法のような規範が言葉のみでなく、人生の至るところにあるならば、文法や言葉の自然=必然な連関から自由になる詩もまた人生のあらゆる場面に応用できる。そして、それは結果的に世界や他人の人生にも影響を与えるだろう(you may contribute a verse)。
詩は、詩的なものとして、人生の自由の条件として拡張されていく。
キーティングを演じたロビン・ウィリアムズは二〇一四年に自死した。同年にiPad AirのCMで『Dead Poets Society』のホイットマンの場面における彼のセリフがナレーションとして使用され、最後に同じ問いを投げかけられる。
「きみはどんな詩を?(What will your verse be?)」と。
その演出は感動的で、新しいテクノロジーとしてのiPad Airは生活のあらゆる場面であなたが自分自身の「詩 verse」を作り出すのに役立つだろうというメッセージを伝えている。
しかしながら、こういった美しいメッセージを裏返してみる(reverse)と、まったく別の世界が見えてくる。
ロビン・ウィリアムズが自死し、iPad Airの素晴らしいCMが世に出た同じ二〇一四年に、まさにその素晴らしいテクノロジー製品の製造を請け負う会社Foxconnの組み立て工場で働いていた若い労働者がビルから飛び降り自殺をし、その短い一生を終えた。ちょうどFoxconnと新しい三年の労働契約を結んだばかりだった。 彼は筆者と同じ一九九〇年生まれで、許立志という名前である。そして、許立志は詩人でもあった。
何年も前に
彼は荷物を背負い
このにぎやかな街に足を踏み入れた
意気揚々としていた
何年も後に
彼は自分のお骨をもって
この街の
十字路に立ち
呆然と周りを見渡している
――「都市に出た労働者」[11]
ネジが一つ地面に落ちた
この残業の夜に
まっすぐに落ちていき、軽い音を立てた
誰かの注意を引くことはない
ちょうどこの前の
ある似たような夜に
誰かが地面に落ちたのと同じように――「ネジが一つ地面に落ちた」[12]
労働者たち(その多くが農村出身者)は、意気揚々と都市に足を踏み入れたが、最後には生きることの意義を見失い、自らの死骸を手に持ち、街路に立ち尽くす。社会という自動機械を動作させるネジとしての彼らの死は誰の注意を引くこともない。ネジには機械を動作させる以外に存在意義がないからだ。生が動作しか意味していないように、死は故障以上の意味を持たない。許立志の詩はこういった生、いや、こういった生の不可能性を表現し、可視化する。彼らはiPad Airのような自らの生を「詩 verse」として社会に寄与するのに役立つデバイスを生産するが、その生産の仕方は逆に彼ら自身の詩を不可能にしてしまう。ここにダイバーシティのイデオロギーが人権の後景化をもたらしてしまうのと同種の矛盾を見出せる。
詩というものは現在の日本において現実から遊離した、曖昧でふわふわとした、非論理的で感情的な「ポエム」として揶揄され、嘲笑の意味合いで使われることも少なくない。しかし、現実の苛酷さを身を以て経験してきた中国の出稼ぎ労働者や「農民工」と呼ばれる低賃金労働者たちの中にこそ、むしろ詩人が多くいる。『The Verse of Us』(原題『我的诗篇』、二〇一五年)というドキュメンタリー映画は、そんな彼らの生活と詩作の活動を記録している。就職活動中、企業の採用担当者相手に自作の詩を朗読し、説教されるといった衝撃的なシーンもある。この映画の宣伝ポスターには、「The powerful play goes on, and you may contribute a verse.」と、ホイットマンのあの一節が小さくプリントされている。
社会がある種の必然的な論理にしたがって、彼らに苛酷な環境での長時間労働を強い、それによって彼らが客体化された存在として尊厳を奪われている状況において、彼らの生、ネジとしての生自体が「力強い演劇」に「詩を寄与する」ことは許されない。しかしそれでも、あるいはだからこそ彼らは、iPad Air のCMにおけるような比喩的な意味での「詩」ではなく、文字通りの「詩 verse」を寄与しようとし、詩そのものをもってこの世界への抵抗を試みている。
彼らの抵抗は何よりも社会が押し付ける必然性の構造に対してであった。そして、必然性に対抗するためには偶然性が必要である。宮野真生子によれば、偶然性の問題を探究してきた九鬼周造にとって、「偶然性の具体的次元を可能にする一つの実践方法」が詩であり、そして詩における押韻だった。[13]
(前略)押韻そのものを構成する言語の偶然的な関係はその偶然性ゆえに私たちに現実を越えた驚きを与えるからである。まさに「詩」とは押韻という言語の偶然的音楽によって超越的次元を垣間見させるものであると九鬼は考えた。[14]
詩において言葉は自然で必然的な連関の関係から解き放たれ、別の偶然で潜在的な可能性へと開かれる。言葉の押韻は偶然である。そこには文法的=ルール的な必然性もなければ、文脈的=歴史的な必然性もない。しかし、偶然であることは、単に恣意的である(ほかのものでもよかった)ことを意味しない。偶然であるにもかかわらず、押韻によって言葉と言葉が響き合うと、まるで必然的な対応がそこにもともと備わっていたかのように感じられるようになる。
韻を踏むというのは、ある意味では偶然的な結合であり、個々の言葉の意味や文脈によってあらかじめ決定されているわけではない。しかし、ある言葉と言葉が実際に韻を踏み、それが豊かな意味の広がりをもたらす創造的な効果を発揮したならば、両者は韻を踏むのにはじめからふさわしかったものとして――必然的な結合であったもののとして――立ち上がってくる。[15]
こう記す古田徹也によれば、韻を媒体に互いに関係のなかった言葉と言葉の文脈が融和し、新たな文脈が作り出された時、私たちは遡及的に「この言葉でなければならない」という必然性を感じる。その意味で、詩における押韻は偶然性を足がかりに(ルール、歴史の両方において)新たな必然性を創造する営為だといえる。そして、重要なのは、それは単に個人の主観による恣意的な創造なのではなく、誰もが声に出して言うことができるコモンとしての言葉の中に、偶然でありながら必然だと感じられる連関を作り出しているという点で、客観的なものであることだ。宮野は古田の言語論を踏まえながら、九鬼周造の押韻論を次のように要約している。「〔詩における〕律格という形式は、創造的必然性を宿す言葉を客観的に呼び込む場を開く装置であったと言えるだろう」[16]。
この客観性はある主体の恣意的な力によるものではなく、コモンである言語の力自体から「到来」するものであるという点において、前節でみた『羅小黒戦記』における神の力の扱われ方が、恣意的な使用ではなく、客観的なコモン化であるのと通じるところがある。
中国の労働者詩人たちは詩作を通して、グローバル化し、多様性が謳われた世界を裏返しにする(reverse)ことで、実際には多様性を抑圧し、必然性の論理をもって人々の生を不可能にしているという本質をより客観的な形で顕にしている。
しかし、彼らはそれに実際に抗うことはできない。『The Verse of Us』は、彼らの詩の力を見せつけると同時に、その詩がいかに無力かも描いている。許立志は転職が叶わず、意に反してFoxconnと二度目の労働契約を交わした四日後に自殺し、その遺骨は海に撒かれた。就職活動で詩を読み上げた者は結局仕事を見つけられなかった。発破工の詩人は、給料を払ってもらえず、正当な理由もなく辞めさせられた。
映画『Dead Poets Society』の主人公ニールは、キーティングの影響で親の意向に反対し、自らの意思で人生を演劇に捧げると決める。誰もが認めたように、彼の演技は最高なものだった。[17]彼の父親も観劇したが、感激はしなかった。父親は演劇を続けられないようにするために彼を転校させることに決める。それに絶望したニールは父親の拳銃を取り出し、自らの命を終わらせた。その後、キーティングは生徒たちをそそのかした罰として教員の職を追われた。この映画の中心にあるのはこの絶望感である。
ニールには演劇しかなかった。そして、それは彼を抑圧した者にとっては無力なものだった。中国の労働者詩人たちにも文字通りの詩しかなかった。そして、それは社会や世界に対抗するにはあまりにも無力だった。ニールが自らの人生をかけて演じた悲劇がなかったことにされ、キーティングの言葉だけがiPad AirのCMに引用され、偽りの希望として搾取されたのと同じように、詩人の死もまた搾取される。許立志は死の少し前に、まさにそのことを予見したかのような詩を残している。
こんな日が来ることを知っている
知っている人たちや知らない人たちが
私の部屋に踏み入り
私の残骸を片付け
床中に流れた私の黒くなった血を洗い流すだろう
(中略)
あの書き終えられなかった詩を誰かが代わりに書き終えて
読み終わらなかった本を代わりに読み終えるだろう
(中略)
最後は長年開けられることのなかったカーテンだ
私の代わりに開けて、しばしのあいだ陽光を招き入れて
から
再び閉じて、そして釘でしっかりと封じるだろう
すべての過程は秩序正しく、厳かだ
これらすべてを片付けたあと
人々は列をなして離れていき
そして静かにドアを閉めるだろう
――「こんな日が来ることを知っている」[18]
許立志は生前ほとんど注目されることはなかったが、その死後に大きな注目を浴びた。『The Verse of Us』では、彼の遺骨を海に撒くシーンが一つのクライマックスをなしており、映画の公開に先んじて、彼個人の詩集も出版された。しかし、二〇二二年の現在、まだ彼の名前を覚えている者はどれほどいるだろうか。労働者の詩人という存在にまだ興味を持ちつづけている者はどれほどいるだろうか。彼らの詩作が提起した問題を、中国という特殊な国における特殊な問題ではなく、世界にとって普遍的な問題として引き受ける者が果たしてこの日本にいるかどうか。人々は彼の部屋の「長年開けられることのなかったカーテン」を開いて、「陽光を招き入れ」たにもかかわらず、それを「再び閉じて、そして釘でしっかりと封じ」てしまった。離れる時にドアを閉めることも忘れずに。
現実には許立志の死は何も変えられなかった。世界は相変わらず「Metaverse メタバース」だの、「Universe 宇宙」だの、「Diverse/Diversity 多様な/多様性」だの、欺瞞に満ちた言説をもてはやしている。詩の抑圧の上に成り立つ世界、詩人の死を強いる世界はなお続いている。それは生を抑圧し、生の別の可能性に死をもたらし、不可能にしてしまう世界である。我々の力では、ひびも入らず、傷一つ付かない、必然的な法則にしたがって動く自動機械としての世界。許立志は生前、中国を代表する現代詩人顧城の詩集を愛読していた。彼の死後にその「残骸」と「部屋」を片付けた者の一人は、彼がその中の一節に線を引いていることを発見した。[19]
死は小さな手術
命だけを取り除く
傷口さえ残さずに[20]
Re-Verse
中国の労働者詩人たちには詩しかなかったが、詩をもって再び詩のある世界(Re-Verse)の到来を夢見ていた。人々が高次の者たちが決めた必然性にしたがって生きるのではなく、自らの手で、コモンとしての必然性を創造できるような世界を夢見ていたのだ。
許立志は二〇一四年九月三〇日の午後にビルから飛び降りた。その前に「微博」というTwitterに似たSNSにおける自身のアカウントでつぶやきの予約投稿をセッティングした。
二〇一四年一〇月一日午前零時にそれは予定通りに投稿される。
新しい一日だ。
そこにはこの一言のみ書かれていた。人間は死してなお自動機械が私たちの代わりにポジティブなメッセージを発しつづけられるという皮肉なのかもしれないし、自らの死は新しい未来を夢見ることを可能にしようとするものだと言いたかったのかもしれない。彼が何を言いたかったのか、それが何を意味しているのかは誰にもわからない。彼自身にもわかっていなかったのかもしれない。
彼は単に世界の必然性に抗うことができず、失敗してしまったのである。
しかしながら、伊藤亜紗がヴァレリーの詩論を通して論じているように、詩とは一種の失敗においてこそ現れる。
たとえば「マッチを擦って火がつく」のは詩ではないが、「マッチを擦って火がつかない」のはひとつの詩になる、とヴァレリーは言う。(中略)言語によるそれにせよ、それ以外のものにせよ、詩があらわれるのは、「事物の自然な流れ」が断ち切られるところである。そしてこの断ち切りによってのみ、「私たちが持つ潜在的なものの総体」としての錯綜体への接近は可能になる。[21]
詩、もしく詩的なものは「事物の自然な流れ」を断ち切ることによって自然の必然性に抗うならば、「事物の自然な流れ」という必然性の側に立つ、立たされている我々からみれば、それは必然的に「失敗」とならざるをえない。ここでは「失敗こそ成功である」という逆説が詩の条件となっているのだ。
だからこそ、許立志の自死=失敗後に発された先の言葉が絶えず彼の自死する前の瞬間へと逆行し(reverse)、それにふさわしい意味を再び得ようとしていると感じずにいられない。それは失敗という形で我々に影響を及ぼそうとする一種の逆行的=再-詩的(Re-Verse)な「力」なのだ。その逆行の力は再び詩を取り戻した世界(Re-Verse)と応和し、一つの韻を形成し、新たな必然性を獲得しようとしている。
註
[1]例えば、理論的にこういった言説を補強しようとするものに、岡嶋裕史『メタバースとは何か:ネット上の「もう一つの世界」』(光文社新書、二〇二二年)や三宅陽一郎「メタバースによる人の意識の変容」(『現代思想』二〇二二年九月号〔特集=メタバース〕所収、青土社、二〇二二年)などがある。
[2]刘慈欣《不能共存的节日》、二〇一六年。「2016科幻春晚重播:刘慈欣《不能共存的节日》」知乎 / 未来事务管理局,https://zhuanlan.zhihu.com/p/348095903
[3]劉慈欣『三体』大森望、光吉さくら、ワン・チャイ訳、立原透耶監修、早川書房、二〇一九年、八一-八二頁。
[4]さらに、シリーズの第二部『三体Ⅱ:黒暗森林』や第三部の『三体Ⅲ:死神永生』でも第一部と同様に、いずれも宇宙をある種の必然性の装置として描く。第二部では、宇宙における各プレーヤー(文明)間のゲーム理論的な関係性は必然的に敵対性を生み出すという「宇宙社会学」が、滅ぼすか滅ぼされるかの二択を人類に迫る。そこでは人類の思考と倫理はすべて無効化され、そのゲームに乗り、そのルールにしたがうことを強いられる。第三部はそのような世界観をさらに展開し、現在の宇宙の状態や物理法則は、より高次の存在たちの間の闘いの結果であるということを提示する。宇宙という自然の必然性は、(高次の存在たちの)社会や歴史という偶然性の累積の結果だった。第一部と第二部の主人公が曲がりなりにも人類を目前の危機から救ったのとは対照的に、第三部の主人公は人間性という偶然的なものに固執し、宇宙の必然性を拒否したがために、太陽系の滅亡を間接的に引き起こし、さらには人類や宇宙の行く末を何もできずにただ見守ることしかできなくなってしまう。
[5]この構造は、現代の我々の新自由主義的な世界において、利益追求のゲームによって伝統とコミュニティが解体されるにつれて、我々がますます資本のルールに支配され、客体化されるという構造と相似形をなす。
[6]ここでは別のメタバース映画を思い出してもいいだろう。『マトリックス』の三部作(一九九九-二〇〇三年)における「救世主」は、実際に人々をメタバースから救い出す存在ではなく、むしろ救済を不可能にするための、救世主のシミュレーションでしかない。
[7]経済産業省ホームページ「ダイバーシティ経営の推進」https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/index.html
[8]岩渕功一編著『多様性との対話:ダイバーシティ推進が見えなくするもの』青弓社、二〇二一年、一一頁。
[9]岩渕、前掲書、一二頁。
[10]逆に言えば、完全に「離れて別々の方を向く」メタバースは社会を構成しえない。
[11]许立志《新的一天》秦晓宇编选、作家出版社、二〇一五年、一四六頁。本論考で引用した中国語の詩の訳はすべて筆者によるものである。
[12]许立志、前掲書、二一四頁。
[13]宮野真生子『言葉に出会う現在』ナカニシヤ出版、二〇二二年、三四頁。
[14]宮野、前掲書、三六頁。
[15]古田徹也『言葉の魂の哲学』講談社選書メチエ、二〇一八年、一八九-一九〇頁。
[16]宮野、前掲書、二九三頁。ただ、押韻や律格のみがその力を持つというわけではなく、むしろ詩のその力を突出して象徴しているのが押韻であると考えたい。
[17]演目はシェイクスピアの『夏の夜の夢』である。これもまた社会的な権威(=貴族)による規範の押し付けと、高次の者たち(=妖精)の気まぐれな闘いにおける力の恣意的な行使に翻弄され、客体化される人間たちを描いた物語と考えられる。
[18]许立志、前掲書、二三〇頁。
[19]许立志、前掲書、二二頁。
[20]顾城《暴风雨使我安睡》北京十月文艺出版社、二〇一一年。
[21]伊藤亜紗『ヴァレリー:芸術と身体の哲学』講談社学術文庫、二〇二一年、二六四頁。