Jemes Braxton Peterson “The Hip-Hop Underground and African American Culture: Beneath the Surface”(Palgrave Macmillan、2014年)
一言、「ヒップホップはマニエリスムだ」と言ってしまえばよいのだ。長らくそう思ってきた。ポール・D・ミラー『リズム・サイエンス』(青土社)の訳者解題で元祖サンプリング藝術としてのマニエリスムに言及し、参考文献リストに高山宏の『近代文化史入門』(講談社)を加えた上野俊哉のみがその認識に多少なりとも届いていた様子で、その慧眼には瞠目させられた(その後、そこを深めることはなかったようだが)。難解を極めるG・R・ホッケの二冊のマニエリスム本(『迷宮としての世界』、『文学におけるマニエリスム』)が奇跡的に翻訳されている自国でさえこうした状況なのだから、未だにホッケが紹介されていない英米圏に特にそれを求めていたわけではないのだが、マニエリスムという言葉を一切使わずに「ヒップホップはマニエリスムだ」と意図せずして言ってしまった本を発掘した。
それが今回紹介するジェームズ・ブラクストン・ピーターソン『ヒップホップ・アンダーグラウンド』である。本書を掻い摘んでいえばヒップホップをめぐる「地下」のテ―マ批評で、この主題を選び取ったこと自体、ホッケが「精神史的洞窟学」と命名したマニエリスムへ導くものだといえる。
著者のピーターソンに関しては、『立命館言語文化研究』という紀要が「アンダーグラウンドの底力――ヒップホップとアフリカ系アメリカ人文化」という訳文を掲載していて、ネットで読める〔1〕。そこでは本書の簡にして要を得た解説もなされているが、著者自身がこの本のポテンシャルに気づいていない様子なので、以下「マニエリスム」という切り口を設けて本書の可能性について触れていきつつ、パラレルにそれを補う試論を展開していく。
メタファーとしての地下鉄道――逃走・闘争・自由
19世紀アメリカ、白人主人から南部黒人奴隷たちを北部自由州やカナダに逃がした秘密組織に「地下鉄道(The Underground Railroad)」というものがあった。「鉄道」とはいうもののそれは隠語であり、実際に逃げる手段は徒歩や馬車だった。その際に奴隷制度反対論者とそのシンパたちは、逃がし屋を「車掌」と呼んだり、黒人の隠れ家を「駅」と読んだり、暗号を駆使して監視の目をかいくぐった。こうした「黒の修辞学」(ヘンリー・ルイス・ゲイツ・JR)こそが黒人文化の本質であるとし、ピーターソンは地下鉄道からアンダーグラウンド・ヒップホップまでを貫通する巨大な根を掘り起こそうとする。
本書に導入されたこの「地下鉄道」のメタファーが、ヒップホップの世界ではコンシャス・ラップの代名詞程度に貶められていた「アンダーグラウンド」のもつ意味合いを賦活する。例えばマーシリエナ・モーガン〔2〕の『ザ・リアル・ヒップホップ』ではL.A.ベイアリアに限定的な地下活動としての「プロジェクト・ブロウド」を扱っているのみであるが、ピーターソンにとってのアンダーグラウンド概念は地下鉄道のように全国津々浦々に張り巡らされた「リゾーム」状のものであり、こうした地理的な限定は意味をなさない。あるいは「地下鉄道」というのはその「移動性」に特徴があるのであり、黒人主体の絶えず変容するアイデンティティのメタファーともなるのである。そのあたりのピーターソンの認識は、アレックス・ヘイリー原作の『ルーツ』(黒人奴隷時代の話に始まる大河小説)のTVヴァージョンが米国で驚異の視聴率を叩きだしたことに触れ、(根っこだけに)黒人の地下空間が地理的に一挙拡大されたと見なすマクルーハン風の綺想に現れているだろう。
こうした革新性を一部示しつつも、ピーターソンの「アンダーグラウンド」理解は基本的に師匠格にあたるモーガンのそれに忠実である。上記した紀要で、ピーターソンは以下のモーガンの文章を自身のアンダーグラウンド観の骨子として引用している。
ヒップホップにおける地下の用語は多くのシンボルと関連があるが、それらはすべて、逃走(flight)、闘争(fight)、自由(freedom)と密接に関連している。また同時に、地下は奴隷制の時代を思い起こさせるものである。当時[奴隷とされた]ある民族は、自分たち自身の言葉や会話、創造性、身体、文化、宗教実践、そして人生そのものをコントロールする機会を求めて、驚くべき欲求と勇気を奮い立たせた……。つまり[地下とは]人間性にとって究極の空間であり場所なのである。[訳=坂下史子]
「逃走、闘争、自由」、その古典的なまでの三大スローガンに支えられた黒人文化の「地下」概念を発掘するために、様々な文学テクストからヒップホップの楽曲までが引用され分析される。リロイ・ジョーンズの『ダッチマン』という黒人男性と白人娼婦の「地下鉄」を舞台にした罵り合いから殺人に至る戯曲や、「地下」で発掘される巻物にヒップホップの奥義が記されていたという魅力的な書き出しで始まるサウル・ウィリアムズ『デッド・エムシーズ・スクロール』など非常に気の利いた素材が選び抜かれている。本書で参照されるこうした「メトロ・テクスト」(高山宏)をリストアップするだけで独自の「アフロ・アンダーグラウンド」の体系をセッティングする助けにもなるだろう。
(アン)コンシャス・ラップ――黒人心理の「地下」に向けて
様々な「地下」を舞台にした黒人文学などからヒップホップにおける黒人アイデンティティー及びそのアンダーグラウンド概念を考えていくといった手法を取るように、ピーターソンが追いかけているものは音楽/文学といった窮屈なジャンル区分を越えたところでの、地下をめぐる「黒い精神史」である。それゆえピーターソンは、デ・ラ・ソウルらを代表選手とするThe Native Tonguesというヒップホップ集団の名前自体に、リチャード・ライトのA Native Son(邦題『アメリカの息子』)、およびそれに対するコメントであるジェームズ・ボールドウィン “Notes of a Native Son” (邦題『アメリカの息子のノート』)などの引喩を読み込む。これはネイティヴ・タンに所属するモス・デフの「ヒップホップ」という曲のリリック分析から導かれたものだが、こうした高度かつ豊かな引喩を駆使するヒップホップこそが、オーバーグラウンド・ラップのマッチョ一辺倒の視覚的優位を転覆させるものだとピーターソンは説く。ここで注視すべきは、マッチョを虚仮にする引喩を張り巡らしたメタラップとでも呼ぶべきこうした知的ジャンルの出現は、人を「内省」のモードへと向かわせるということである。
さらにライターの辰巳JUNKによる「HIPHOPのメンタルヘルス観の変容/「男らしさ」から「脆弱性」へ」といったウェブ記事〔3〕も考えると、もはや時代はXXXテンタシオンやリル・ウージー・ヴァートのように自殺願望やメランコリーを包み隠さず吐露する「エモラップ」にまで到達しており、ヒップホップが強烈な自意識に穿たれた「穴」の中に潜ってより深い「内面」を獲得した経過が伺える。とはいえ本書におけるピーターソンのパースペクティヴは、軽々とヒップホップという狭い範疇を超えていた。奴隷にされた黒人たちは南北戦争以後に、自分たちの悲惨な境遇について(小説などで)書くことでとっくに「内面(interiority)」を獲得していたという指摘で、ヒップホップにおける「内面」だとか「内省」の変容だとか言う前に、歴史をさかのぼって近代の「黒人文学」の誕生――すなわち「内省」の誕生――〔4〕からの連続性で考えなければならないという視座がそれとなく提示されている。
こうした「地下」やそのアナロジーとしての「内面」といったキーワードに触れつつ、黒人文学やヒップホップに顕著なAAVE(アフリカ系アメリカ人土着英語)特有の言語的「仮面」――つまり「素面」としての標準英語に対して、訛りや視覚的な誤表記といったマスキングを行うこと――などにもピーターソンは言及していくのだが、それらを逆手に取ったように露骨にメタリックな仮面をつけたMFドゥーム(別名JJドゥーム)といった黒人ラッパー【図1】はどのように論じるべきなのかなど、肝心な点が抜け落ちているのは少々問題だろうか。
図1.黒人が身に着ける「(見えない)仮面」を露骨に装着するMFドゥームの肖像。逆にそのメタリックな仮面は、覗き込むものを反射的/内省的に映し出す鏡であり、その眼差す主体自身を問題化する「分身」を形成する。
KRS-One「hol(d)」にみるラップの言語遠近法
以上のようにヒップホップを文学的想像力から考える方面でピーターソンは冴えた分析を見せるが、難解な生成文法にまで手を出す言語学方面からのアプローチがより多いのが本書の特徴かもしれない。なかでもKRS-Oneの「hol(d)」という曲に関する分析は、本書の言語学方面からの最上の批評的成果を上げている。dの最後に丸括弧が付いているのは、この曲において「ホールド」なる単語が、文脈によってはhole(穴)にもhold(持つ)にもwhole(全体)〔5〕にも聞こえるという――ときに偶然性(contingency)に立脚した――万華鏡的な千変万化をするからであり、この事情をピーターソンは「形態論的仮面(morphemic mask)」と呼んでいる。
しかしここまで来て何故「マニエリスム」の一語が出てこないのか? 高山宏が「〈視〉に淫する」(『目の中の劇場』所収)で指摘した、ヘンリー・ジェイムズの小説「大使たち」とホルバインの絵画「大使たち」の重なり合いを想わずにはいられない。この「大使たち」という絵は正面から見れば身なりの良い大使二人が描かれたものに過ぎないのだが、パースペクティヴを変えて斜めから見ると、メメント・モリを表す骸骨が無気味に浮かび上がるという仕掛けになっており、絵画の世界では「アナモルフォーズ」と呼ぶ【図2、3】。これは文学においても事ほど左様で、観方(point of view)によってテクストの反射率が変わって、幾通りかに読めてしまうということを、ヘンリー・ジェイムズは同タイトルの小説で実践しているわけだ。
図2.ハンス・ホルバイン「大使たち」
図3.斜めから見ると
よってピーターソンの言う「形態論的仮面」とは、マニエリスティックな言語遠近法=アナモルフォーズの謂いだろう。ラッパーの言語とは、ザ・ブルー・ハーブ《Coast 2 Coast 2》の「味わえ 物を見る角度の違い」という名リリックに象徴されるごとく、角度によって見え方が変わる光学魔術言語なのである。こうした曖昧性や複数性に沈み込む言語アナモルフォーズはほとんど「暗号」の領域であるということは、KRS-Oneのリリック分析が収められた章のタイトルが「黒人文学の文化における地下の暗号」であることからも一目瞭然だろう。そして「地下」から「暗号」へのアナロジーから、ピーターソンが次に焦点をあてるのがファイヴ・パーセンターズである。
ファイヴ・パーセンターズという謎――「アフロ・マニエリスム」を開く鍵
Gravediggazの “The Night The Earth Cried” の謎めいたミュージック・ヴィデオをファイヴ・パーセンターズの教義に照らし合わせて解説するなど、本書ではNASやJAY-Zといった超有名ラッパーたちも加入するこの謎の「地下」組織にも筆が及んでいる。一体どのような集団なのか、簡にして要を得た説明がフェリシア・ミヤカワ『ファイヴ・パーセンター・ラップ』(インディアナ大学出版) の裏表紙にまとめられている。
ファイヴ・パーセント・ネイションは物議をかもした組織で、本質的かつ文化的な勢力である。ネイション・オブ・イスラムの分派で、グループはその信仰の基礎を、ブラック・ムスリムの伝統、ブラック・ナショナリズム、ケメティズム(古代エジプト)のシンボリズム、フリーメイソンの神秘主義、グノーシス主義の精神性に置いている。構成員はしばしば刑務所で勧誘され、非アフリカ系アメリカ人は35年間の修行期間を終えたあとでのみ、第二構成員として加入を許される。ファイヴ・パーセンターズは商業的なラップ、すなわち「ゴッド・ホップ」の力を借りて、人々を改宗させ、関連のある問題を批評し、新たな構成員を勧誘する。
要は黒人版薔薇十字団のようなものと考えてもらえばよろしい。このミヤカワの書物を引用するとき、ピーターソンは「地下」のテーマから「暗号的想像力」(S・ローゼンハイム)にまでアナロジーの翼を羽ばたかせ、とうとう「アフロ・マニエリスム」の域に達する可能性を示唆したといえる。なぜか? 「シュプリーム・アルファベット」とか、リリックを代数学のように組み合わせる「シュプリーム・マスマティクス」といったほとんど数秘術的な暗号学からラップのリリックを解読する作業は、フランセス・イェイツがシェイクスピアに東欧薔薇十字思想を読み解いていった一連の作業と同工異曲のヘルメス的展開なのである。
そもそもソウルズ・オブ・ミスチーフやデル・ザ・ファンキー・ホモサピエンらを擁するカリフォルニア州オークランドのアンダーグラウンド・ヒップホップ集団「ヒエログリフィクス(聖刻文字)」なる名の存在自体が、ラップ・ミュージックのマニエリスム性を物語るものであり、米文学に流れ込んだ埃及狂の系譜を追ったジョン・アーヴィン『アメリカン・ヒエログリフィクス』などを参照しつつ、このエニグマティック・ワールドに挑んでいく展開も本書にはありえただろう。あるいは益子務『ゴスペルの暗号――秘密組織「地下鉄道」と逃亡奴隷の謎』(祥伝社)といった書物を読めば、黒人奴隷が歌うゴスペルが白人農主の監視を逃れて制作された暗号――旧約聖書にちなんだ「聖」なる歌詞が、実は黒人奴隷の逃亡という「俗」な現実を同時に歌っていた――であった可能性が示唆されるのであり、一種の「迷宮としての世界」としてアフロ・カルチャーを捉える壮大な枠組みに気づかされるだろう。
ディオニュソスとダイダロス――あるいはギャングスタとドクター
ヒップホップにおける内省、アナモルフォーズ、暗号と続けてきたところで、こうした醒めた知性の傾向を一つG・R・ホッケの顰に倣って「ダイダロス的」(迷宮の発明家として知られる古代ギリシャの神)と括ってみよう。本書の付録である「ヒップホップ年表」の「2000年から現在にかけて」の項目に、以下のような記述がある。「人気のあるヒップホップ・アーティストはその歌詞をディオニュソス的偉業と経験にまで縮小させた」。他の頁にも出現する、この「Dionysian(ディオニュソス的)」なる単語に託されたものは、ヒップホップの過剰なパーティー性や暴力性を指すと思われるが、仮に英米圏でホッケ『文学におけるマニエリスム』が紹介されていたならば、ここでマニエリスムのもう一方の守護神ダイダロスも召喚されたに違いない。
メインストリームのラップはディオニュソス的にヒップホップ・ドリームという幻想三昧に浸ることは確かだが、そのような彼らにしても同時にその不定形な白昼夢の暴走に制肘を加えるような「リアル」による落し前を重要視するわけだし、また押韻による言語の理性化というダイダロス的構築が行われるのだ。簡単に言えば、(特にフリースタイル時に顕著だが)熱く夢を語りながら、同時に醒めた知性が韻やメタファーを構築していくという分裂状態であり、ホッケの語る「マニエリスムのダイダロス的要素がマニエリスムのディオニュソス的要素を冷却する」構図に、ラップ・ミュージック全体が見事に符合する。
先ほど述べたファイヴ・パーセンターズの「シュプリーム・マスマティクス」などもダイダロス的といえるが、我が国でもキングギドラの《大掃除》という曲で、Kダブ・シャインは「位置に三途の川 誰も死後ろくな名前とかもらわず」「影の過激派地球自由におびやかし中」「キャプテン翼もイラつく百点のうまさ」「地上に降りた最期の戦士」「世は満足じゃ 百万石の貫録」といったように、数え歌風にリリックを紡いでいく。表面上の意味の裏側で知的に数列を展開させていく言語迷宮の構築は、Kダブがダイダロスの末裔であることを示唆する。ホッケによれば、マニエリストとは「ディオニュソス的無定形」と「ダイダロス的輪郭づけ」の矛盾に引き裂かれる。いわば「デモーニッシュなものを、人工的構成によって、合理的代数学の怪異であるとはいえ現存在克服的な図形のうちに囲い込もうとする」運動がマニエリストたるラッパーの中で起こっているのである。
ヒップホップ・アルケミア
本書はラップ一辺倒であるようでいて、『メイキング・ビーツ』の著者であるジョゼフ・シュロスが裏表紙に言葉を寄せていることからも分かるように、「地下」のテーマでビートメイカーにも筆が及んでいる。ギャングスタ(Gangstarr)のDJプレミアによる、その入り組んだ引用の織物と化したトラックを指してピーターソンは「秘密の、ヘルメス的世界」などと形容しているのだが、その易々と出典を開示しないアンダーグラウンドかつ秘教的な姿勢などマニエリスムの典型的韜晦の身振りであるといえる。ましてや、この「チョップ」なる技法を開発したDJプレミアという男は、大学でコンピュータ・サイエンスを学んでいた理工系であり、そのようなダイダロス的人物が「ギャングスタ」なるディオニュソス的名前のユニットに所属しているパラドックスがあるのだが、こうした分裂にこそ豊かなマニエリスムは宿るのである。やたらとDJが「ドクター」を名乗りたがったり、「実験室」といった言葉を使いたがったりするヒップホップ界隈の錬金術的伝統は、ダイダロス主義の遠い末裔なのである〔6〕。
またピーターソンの指摘に補足するならば、ヒップホップの創始者の一人であるアフリカ・バンバータが「ブレイクダンス」「グラフィティ」「DJ」「ラップ」に次ぐヒップホップの五番目の要素として挙げた「知識」〔7〕とは、(ある種のリップ・サービスを感じさせつつも)錬金術における第五元素すなわち「賢者の石」のことであり、これは先述したKRS-Oneの名前の由来が「知識はほぼ全ての人間を完全に支配する(Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone)」の頭文字を集めたものだということと考え併せれば、アルチュール・ランボーが「言葉の錬金術」と呼んだものを実践するラッパーたちを筆頭にヒップホップのもつ秘教主義の一端が見えてくるだろう。
立体的聴取としての「アフロ・メセクシス」
最後にアフロ・マニエリスムの問題系をすこし離れ、本書が文学・言語学の知見にあまりに依っていて、鳴っている音楽そのものへの関心が低いことへの解毒剤として――本書の「聴取」を問題にした分析箇所を強調して終えることにしよう。5章「アンダーグラウンドの暗号」~6章「死者のための涙」の流れがその意味では本書の白眉だろう。ラルフ・エリソンによる黒人文学のカノン『見えない人間』における、ルイ・アームストロングの音楽を蓄音機五台がかりで同時に鳴らしてそのヴァイブスをからだ全体で感じたいという文章記述に、ピーターソンはレコード再生にはない、蓄音機再生ならではの幽かな音の揺らぎがグルーヴを産むことを予測し、この地下室に生きる「見えない人間」に複数のターンテーブルを駆使するヒップホップDJの役割を読み取る。また『見えない人間』の最後の言葉が韻を踏んだコンシャス・ラップのように聞こえると指摘するくだりなどは、「黒い精神史」にヒップホップをどのように位置づけるか、その批評的示唆を与えてくれるだろう。
6章はその議論を引き継いで、この『見えない人間』を作品中に引喩/引用したモス・デフ(ラッパー)~ジェフ・ウォールズ(写真家)の系譜へと話を繋げていく。とりわけジェフ・ウォールズのAfter “Invisible Man” という写真作品【図4】に漂う「暗示された音楽」――とはすなわちエリスンの小説で描写された、孤独な地下室で鳴り響く、ルイ・アームストロングを蓄音機五台で同時再生したDJプレイ――を聴取する内省的/地下的な作業に取り組むことが、オーバーグラウンドの黒人マッチョ・ヒップホップの視覚的イメージの氾濫への対抗策となりうると、ピーターソンは語る。どういうことか? 文化史家フレッド・モーテンいう所の「音の本質(phonic substance)」や「音の物質性(phonic materiality)」なるものを一枚の写真から抽出し、黒人文化のコンテクストをおさえた上で、抑圧されてきた黒人たちの泣き声/叫び声にまで思いを馳せ、写真を聴覚的に「体験する」ことである。つまり白人女性に口笛を吹いただけで惨殺された黒人少年エメット・ティルのビフォーアフターの写真【図5】をただ「見る」のではなく、隙間に入り込み、その口笛を「聞く」こと、そして「体験」することが、聴取を立体的なものにする。音楽史をただなぞっているだけ、ましてや平面的な聴取で事足れりとする表層批評の立場では、決して聞こえてこない「音」があるということだ。
図4 Jeff Wall, After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue1999-2000
1,369個の電球を使用した。大量の電球の下でDJがターンテーブルを廻す『ヒップホップ・アンダーグラウンド』の表紙が、この写真の引喩であることからもその重要性が伺える。
図5 白人娘に口笛を吹いただけで惨殺された黒人少年エメット・ティルのビフォーアフターの写真に「暗示された音楽」(J・ピーターソン)を聴取すること。
ワイリー・サイファーが名著『文学とテクノロジー』で説いた、西洋視覚中心主義がもたらした「疎外されたヴィジョン」に対する、「アフロ・メセクシス」とでも名付けるべきブラック・カルチャーからの回答がこれだ。文学・音楽・写真のクロス・レファランスを通じたコンテクスチュアルかつインターテクスチュアルな立体的=精神史的聴取があって初めて、その場に鳴っている音だけを聴取することがもたらす世界からの疎外――「サウンド・ピクチャレスク」とでもいうべき事態――から逃れることができるだろう。
後藤護(暗黒批評)
【地下に関する注釈】
〔1〕ジェームズ・ブラクストン・ピーターソン「アンダーグラウンドの底力――ヒップホップとアフリカ系アメリカ人文化」(pdf)
〔2〕マーシリエナ・モーガンは、本書の元になったピーターソンの博士論文「黒人文化における地下性の諸概念」の審査委員を務めている。
〔3〕辰巳JUNK「「HIPHOPのメンタルヘルス観の変容/「男らしさ」から「脆弱性」へ」
http://outception.hateblo.jp/entry/music02
〔4〕西洋においても近代小説の誕生は、個室文化とそれに伴う内省のモードへの突入とパラレルである。
〔5〕この箇所はヒューストン・A・ベイカー・ジュニアの魅力的な「Black (W)hole」理論を基にしている。ベイカーは宇宙上のブラックホールに関する物理学の知見を援用しながら、そのアナロジーとして黒人文化における「黒い穴/黒い全て」という概念を規定していく。詳しくは『ブルースの文学――奴隷の経済学とヴァナキュラー』(法政大学出版局)の第3章第2節「リチャード・ライトの再評価――ブラックホールに関する考察」(249―308頁)を読んでもらうに如くはないが、人類学の「通過儀礼」の概念などを援用したこの複雑怪奇な理論をベイカー自身がコンパクトにまとめている箇所があるので、(その豊饒さを伝えるには不完全ながら)紹介の体で引用する。
ブラックホールは、アフロ・アメリカン文学で用いられるときには、真っ暗な地下という隠れた意味をもつ。つまりトリックスターがふざけながら脱構築を行なう地下の穴を表わす。さらに、アフロ・アメリカン文学では、この穴は完全なる統一体であり、黒人のコミュ二ティの強いきずなを示す場である。そこでは、欲望によって経験が呼び起こされ、ブルースとして歌われる。黒人の完全なる統一体という穴では、白人の世界の厳しい拘束を免れることができる(ブラックホールになる)。と同時に、経験が凝縮された地下の特異点を機能させて、ブルース・ライフへの欲望を充分に充たすことができる。(272―273頁)
〔6〕そもそもミュージシャンたちが籠る「スタジオ」という空間も、原研二『グロテスクの部屋――人工洞窟と書斎のアナロギア』(作品社)の第Ⅲ章「ストディオロ(書斎/実験室)」を読めば、驚異生成のための洞窟と捉えることができる。
〔7〕「知識」(knowledge)の語源を辿ると「グノーシス」という秘教主義にまで行き着く。
【図版出典】
図1 Grown Up Rapより
https://grownuprap.com/2015/01/06/lets-hope-2015-is-full-of-mf-doom-goodness/
図2、3 英語版Wikipedia、The Ambassadors (Holbein)の項目より
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ambassadors_(Holbein)
図4 MoMAより
https://www.moma.org/collection/works/88085
図5 Diary of a Mad Mindより
http://diaryofamadmind.com/index.php/2017/07/25/emmett-till-never-forget/
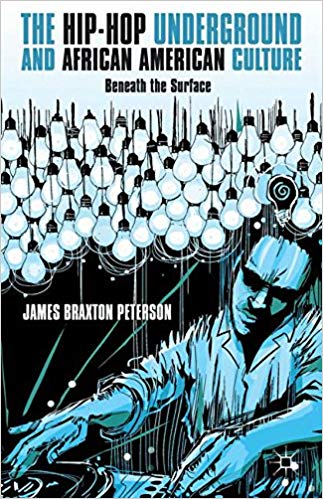


















1 Response
Comments are closed.