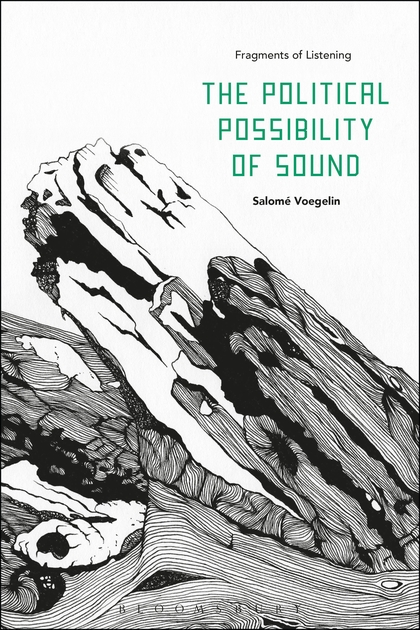Salomé Voegelin, The Political Possibility of Sound: Fragments of Listening, Bloomsbury, 2018
2000年代後半から英語圏でサウンド・アートをめぐる単著が増えだした印象がある。デヴィッド・トゥープやダグラス・カーンらがつくった道は、2000年代半ばにサウンド・スタディーズと結びつきながら広がっていった。本書の著者サロメ・フォーゲリンが所属するロンドンのサウンド・アート研究団体CRiSAP(Creative Research into Sound Arts Practice)の設立が2005年。以降、ブランドン・ラベル、セス・キム=コーエン、スティーブ・グッドマンらが次々と単著を発表していく。フォーゲリンが単著『ノイズと沈黙を聴く──サウンド・アートの哲学に向けて』を出版したのは2010年。彼女は作家、キュレーター、研究者として活動しながら、現在ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーションでサウンド・アートを教えている。
今年2018年に、ラベルは『ソニック・エージェンシー──音と生まれくる抵抗のかたち』を、フォーゲリンは本書を発表し、それぞれの視点から音、政治、芸術のかかわりを論じた。このテーマについては、例えば、ジャック・アタリ『ノイズ──音楽・貨幣・雑音』(1977)などの古典がある。しかし、ラベルとフォーゲリンの著作はサウンド・アートが10年前とくらべて美術により近づいたこと──社会的文脈をより重視するようになったこと──のあらわれかもしれない。とはいえ、フォーゲリンの3冊目の単著である本書は特定の政治的動向や状況について深く考察するわけではない。それらは個々の作品を通じて言及されるだけだ。むしろ本書はいかに現実の衝突と距離を保ちながら、音、政治、芸術のかかわりについて思考できるのかを問おうとする。
エッセイ
フォーゲリンの記述スタイルはこれまでと変わらない。さまざまなテキストから取られた思考の断片がつなぎ合わされる。註などは学術的な体裁をとるが、あくまで「エッセイ」であるという。書名と同じ章題の第1章はフランスの政治哲学者エディエンヌ・バリバールによる『暴力と開明性』(2010)からはじまる。そして、アメリカで実験音楽やサウンド・アートを論じてきたフランセス・ダイソンの『われわれの時代の音色──音、感覚、経済、エコロジー』(2014)が、バリバールらの政治論とフォーゲリンが前著で論じた音響的可能世界論を橋渡しする。これらの議論は本書全体をつらぬくものなので、あとで詳しく説明しよう。本書は全7章、「7つのエッセイ」からなり、第2章以降は建築、地理、身体、物質、聴取といったテーマを通じて、音の政治的可能性をめぐる考察が展開される。
本書は多くの頁を作品論に割いている。たくさんの作品に言及するのではなく、近年の作品をひとつひとつ詳細に記述し、解釈していく。この作品論が本書の魅力である。序論はサン・ラに心酔して「弟子」になろうとするシカゴ出身の作家コーリーン・スミスからはじまる。フォーゲリンが取りあげた作品の多くは動画共有サイトで視聴できる。
本書の冒頭と末尾にはいわゆる「テキスト・スコア」──文章によって読者に行為を指示するスコア──が挿入される。また第5章「見えないものの道徳、聞こえないものの倫理」だけは、大部分が「エッセイ・スコア」である。フォーゲリンが「パフォーマティヴ・エッセイ」とも呼ぶこの形式は、「テキスト・スコア」のように読者に行為をうながすエッセイとされる。例えば、「通りに出て歩きながら次の文章を読むこと…」というように。同章は大学でのパフォーマンスのために書かれたスコアを元にしている。彼女によれば、エッセイ形式やテキスト・スコアを取りいれる理由は、こうした書きかた自体が音のありかたを表現しているからだ。
ここからはまず本書第1章の思考たどり、本書が描こうとする音のありかたを見ていく。次に作品論をいくつか紹介し、最後に本書の論旨を批判的に検討してから、日本の現状をめぐる議論とも結びつけよう。
音の政治的可能性
フォーゲリンは、彼女が音の政治的可能性と呼ぶものがありうる場所を探すことからはじめる。バリバールによれば、政治の基礎とは暴力をなくすことであり、これが秩序の目的である。しかし暴力を秩序によって管理することは、たやすく暴力と非暴力のたえざる循環に陥ってしまう。この循環はむしろ政治が生まれる可能性を抑えこむ。フォーゲリンはこうしたバリバールの議論をふまえて、暴力と非暴力の循環の隙間にこそ政治的可能性があるはずだと論じる。暴力にかぎらず「アンチ(反)」──反民営化、反ネオリベラリズム、反グローバリゼーション──が生みだす循環には政治的可能性を見いだせないと彼女は考える。
フォーゲリンはこの議論を、西洋音楽思想における音の秩序をめぐるダイソンの思考と結びつける。西洋音楽思想は音をモノコードという器具によって離散的システムとして秩序づけ、コール・アンド・レスポンスのくり返しというかたちで管理しようとしてきた。この思想に対して、ダイソンはコール・アンド・レスポンスのあいだに挟まれる息継ぎに注目する。息継ぎの沈黙には音の秩序におさまらない別の声を聞きとることができるのではないか。それは呼吸を必要とする身体の声であり、空気が満ちる環境の声でもある。フォーゲリンはこうしたダイソンの議論を受けて、音楽思想における音の秩序と、暴力を排除しようとする政治の秩序を重ねあわせる。聞こえない息継ぎこそ音の政治的可能性がありうる場所なのだ。さらにフォーゲリンは秩序と無秩序の循環を避けるために、息継ぎの沈黙にはいつも多数の異質な音が共存していると考える。
多数の異質な音の共存という発想はフォーゲリンが前著『音響的可能世界──音の連続体を聞く』(2014)で論じたものだ。彼女はアメリカの分析哲学者デヴィッド・K・ルイスの可能世界論にもとづいて、いくつもの異質なものが並びたつ音のありかたを考察した。人はさまざまな音のなかからひとつの音を聞きとり、これが現実の音だと判断する。しかし実際には、聞きとられない音が必ずいくつもある。フォーゲリンによれば、ルイスが可能世界のありかたとして説明したものはこうした音のありかたに似ている。現実に聞こえる音、現実に生きられる世界はひとつだが、聞きとることができる無数の音、生きることができる無数の可能世界がある。ある音や世界が選ばれる理由は、究極的には偶然に過ぎない。現実にはすべてを聞きとれない多数の音のありかたをフォーゲリンは「音響的可能世界」と呼んだ。
以上のような議論を経て彼女は、音の秩序と無秩序の無限の循環から逃れるには、多数の音が共存する音響的可能世界を想像することが必要であると主張する。こうした認識は政治における暴力と非暴力の循環から逃れるためにも有効であり、音をめぐる認識と政治をめぐる認識を重ね合わせるところに音の政治的可能性がある。彼女がエッセイやテキスト・スコアを取りいれるのは、この音響的可能世界のありかたを文章の書きかたを通じて表現しようとするからだ。フォーゲリンは聞こえない音のありかたを語るために「エコーグラフィー」という言葉をもちいる。そして個々の芸術作品がもつエコーグラフィーを具体的に観察し、記述していく。
サウンド・アートのエコーグラフィー
映像作品、映像インスタレーションとして制作されたローレンス・アブ・ハムダンの《叫びの谷における言語の溝》(2013)は、イスラエルとシリアの国境をめぐる状況を映しだす。この国境にひき裂かれたドゥルーズ派イスラム教徒は、国境両側からマイクで互いに声をかけあい、交流を続けてきた。その様子をとらえた画面はすぐに乱れ、何度もしばらくブラックアウトしてしまう。ナレーションにはイスラエルの法廷で通訳として働くドゥルーズ派の語りなどが聞こえてくる。フォーゲリンは、この作品にあらわれるさまざまな秩序と無秩序の循環、その隙間にある多様な音、そこからひとつの音が選ばれる過程を指摘していく。通訳は語られた言葉から法廷に役立つ意味を選びとる作業である。画面がブラックアウトしたときに聞こえる絡みあう無数の声は、もし国境がなければこの地域がどうなるのかを鑑賞者に想像させる、と彼女は論じる。
フォーゲリンは同じく特定の地理をテーマとする作品として、アンナ・ライモンドの映像作品《メディテラネオ》(2015)も取りあげる。画面にコップが映り、青い水が一滴ずつ注がれる。水音と、エスペラント語で地中海を意味する「メディテラネオ」と言い続けるライモンドの声だけが聞こえる。コップが一杯になってくると、ライモンドの声は溺れているかのようにくぐもり、最後にはあたかも水中に没してしまう。地中海はヨーロッパ、中東、北アフリカの境界であり、移民の通り道でもある。フォーゲリンはこの作品の結末ではなく、水音と声の移りゆくさまざまな表情に注目し、そこに地中海の政治的多様性を見ていこうとする。
第5章「さまざまな主体性を聞く──身体、形、不定形性」は、パメラ・Zのパフォーマンス《ブリージング》(2014)を取りあげる。パメラ・Zはマイクに向かって呼吸や「アイ・ワズ・ブリージング」というフレーズを発する。それらはPCに入力され、彼女の右手にある小さなコントローラの傾きに応じてさまざまに形を変えて再生される。フォーゲリンはこのパフォーマンスを先のダイソンの議論と結びつけ、テクノロジーの力を借りて人種やジェンダーのステレオタイプから逃れていく試みと解釈していく。彼女はレベッカ・ホーンの《ユニコーン》(1970-2)とこのパフォーマンスを比較する。どちらもシンプルなテクノロジーをもちいて身体の機能を変形し、多様性に満ちたユニークな主体をつくる。しかし《ユニコーン》が作者の視覚的アイコンとして固定されたのに対して、《ブリージング》は不定形なままにとどまる、とフォーゲリンは指摘する。
「サウンド」の政治
彼女は音の政治的可能性を、政治的対立から逃れて、代わりに聞きとれない音の多様性を意識することに見いだそうとする。こうした認識はたしかに、彼女が取りあげる作品の細部や文脈に陰影に富んだ解釈をもたらしている。さまざまな音どうしの関係はときに遊戯的、競争的だが、けっして弁証法的な対立をもちこむものではないと彼女は考える。しかし、フォーゲリンが音響的可能世界のありかたとはっきり対比しているものが2つある。どちらも多様なものから偶然選ばれたにすぎないものを固定し、権威づけ、あらゆる議論を「あれか、これか」に落としこむ。そのひとつは視覚であり、もうひとつはネオリベラリズムである。彼女が《叫びの谷》のブラックアウトを重視するのはそのためだ。フォーゲリンによれば、ネオリベラリズムは個人のアイデンティティから人種、性別、階級などを切りだし、固定し、政治的な「アンチ」の構図を描いていく。
本書を読んでいて疑問に感じたのは、この聴覚と視覚の対比である(なお、ブランドン・ラベルも「見えないもの」に『ソニック・エージェンシー』の一章を割いている)。よく読めば、フォーゲリンは聞きとれない音と不定形の視覚像を同列にならべ、それぞれを聴覚と視覚の離散的システムと対比していることがわかる。それにしても、音の多様性と視覚の均質性という対比は何度も語られるのに、ダイソンが論じたような音の内部の対比はほとんど掘りさげられない。不定形な視覚と視覚のシステムの対比もふれられない。視覚が多様な音の豊かさを減ずることがあるなら、均質な音が多様な音を抑圧することも、また不定形な視覚を固定することもあるだろう。フォーゲリンによる聴覚と視覚の対比は身びいきに感じられてしまうことがある。《ブリージング》のテクノロジーを彼女は多様性を生みだすものと解釈する。しかし、例えば、デジタル音響技術には聞こえない音を取りのぞく圧縮という手続きがある。聴覚と視覚の対比とは違い、聴覚の内部の対比はわかりやすく切り分けられるものばかりではない。
フォーゲリンにとっての「音」とは、多様さをかかえた音、聞きとれない音、視覚と対立する音である。逆に言えば、単純、均質、純粋な音は音の世界のごく一部でしかなく、こうした音をいくら寄せあつめても音の世界はつくり直せない。彼女が考える音の政治的可能性は、聞きとれない多様な音の側に立つことにかかっている──だからやはり、音の豊かさを抑圧する音についてはもっと語られるべきだろう。彼女の態度は「サウンド・アート」をめぐる語りかたにもあらわれている。フォーゲリンが映像作家や音楽家の作品を柔軟に取りあげ、「サウンド・アートとは何か」にこだわらないのは、「サウンド」を異質なものに満ちた世界と考えているからだ。彼女はかつてサウンド・アートというカテゴリーに対する恐怖すら論じていた。
循環を逃れる
フォーゲリンの議論はバリバールの政治論から出発するとはいえ、秩序と無秩序の循環や、そこから抜けだすことといった議論はきわめて一般的なものだ。日本においても、例えば、細田成嗣の即興演奏論におけるイディオムをめぐる考察にも似たような発想が見られる。彼によれば、自由な即興演奏を目指して「イディオム的即興」と「非イディオム的即興」の対比を逃れようとする試みは、かつて「汎イディオム的即興」と「音響的即興」というかたちをとった。しかし、どちらも演奏の多様性を維持できなくなり、自由な演奏が失われてしまった。こうした経緯をふまえて細田は、偶然的な「こだわり」を根拠に複数のイディオムのあいだを行きかう演奏、「間イディオム的即興」を提唱する。このとき、彼がイディオムのあいだにある即興と呼ぶものは、フォーゲリンが「音」と呼ぶものと同じありかたをしているのではないか。細田のこの議論は具体的な演奏の記述と切りはなされてしまっているので、イディオムという言葉の意味をどこまで広げたいのかがわかりにくい。彼が考える演奏のありかたがフォーゲリンが音と呼ぶものに近いなら、即興と音のかかわりの再検討が必要になるだろう。また彼が単純化してしまった音響的即興の再検討も。
金子 智太郎(美学・聴覚文化論)