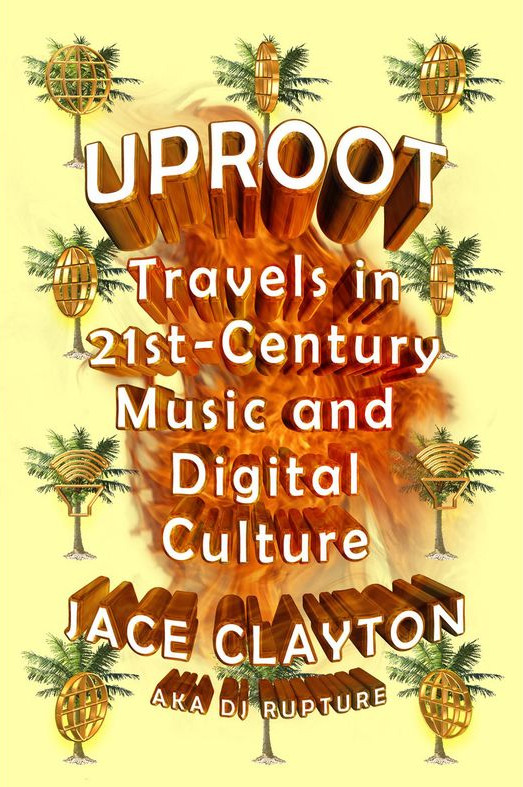Jace Clayton “Uproot: Travels in 21st-Century Music and Digital Culture”(FSG Originals, 2016年)
インターネット以後の「ワールドミュージック」をまなざすDJの視線
ひろく西洋音楽の文脈から外れた周縁あるいは辺境の音楽文化を包括する「ワールドミュージック」なる概念は、欧米中心の音楽市場の要請によって80年代に一般化したものである。もちろん世界各地のローカルな音楽文化が西洋の主流の音楽に影響を与えるという現象は、19世紀末から顕在化した現象ではあった。たとえば1889年のパリ万国博覧会がドビュッシーやラヴェルといった作曲家と東洋音楽との出会いを準備したことは象徴的な逸話だ。そこからおよそ一世紀を経て、アメリカでのレコードの発明と普及に端を発しグローバルな規模に至ったポップミュージックの市場が、万博のように文化混交の場として機能するようになり、20世紀末には欧米のリスナーにとっての文化的他者そのものが「ワールドミュージック」の名のもとに商品化されるようになった。
こうした「ワールドミュージック」の概念やその実態は民族音楽学から音楽社会学、カルチュラル・スタディーズといった多様なディシプリンにおいて吟味されてきた。およそ30年にもわたるその蓄積は、「ワールドミュージック」という言葉の周辺で起こる現象をナイーヴに言祝ぐことも逆に単純に批判することも避け、よりダイナミックで繊細な文化の生成のプロセスとして理解することを促す[1]。とはいえ、ここ数年ひんぱんに耳にするようになった「文化的盗用(cultural appropriation)」行為に対する厳しい批判の声は、異文化間の情報のレベルでの交流とフィジカルなレベルでの断絶・対立がともに加速し引き裂かれ続けているインターネット以降の世界において、依然として「ワールドミュージック」がプロブレマティックな概念=現象であることを告げてもいる。
DJ /Ruptureのステージネームで活動し、欧米のアンダーグラウンドなダンスミュージック・シーンを中心に高い評価を受けているジェイス・クレイトンが著した『アップルート――21世紀の音楽とデジタル文化をめぐる旅(Uproot: Travels in 21st-Century Music and Digital Culture)』は、世界中を渡り歩くDJの視点からローカルな音楽の姿をいきいきと描き出す旅行記であり、欧米の先進国主導で進むテクノロジーの発展と文化の浸透に対して世界中の人びとがどのように応答しているかを批判的な視座から考察する優れた批評書でもある。
テクノロジーは文化の「核心」を照らし出す
同書で取り上げられるのは、欧米の音楽がヘゲモニーを握るポップミュージックの市場においては可視化されづらい文化圏だ。それはたとえばモロッコであり、ジャマイカであり、エジプトであり、メキシコなどである。興味深いのは、どの場所にもYouTubeやFacebookの影がちらつき、mp3のような圧縮音源が飛び交い、コンピューターとDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)による安価な制作設備が揃っている――つまり、人と人とのコミュニケーションやコンテンツの制作・流通にいたるまで、テクノロジーによってある程度標準化されている、ということだ。
もちろん、こうした標準化において主導権を握るのは欧米の先端的なテック企業であるから、しばしばその土地ごとの伝統や慣習とはズレを持つ。それゆえ、そもそもテクノロジーを受け入れることができなかったり、あるいはあまりの浸透力に伝統をかき消されかけたり、またあるいは思わぬ誤用によって新たな可能性が開けたりする。そうした多様な(テクノロジーと文化の)衝突と融和のケーススタディが、この本には詰まっている。
たとえばそうした文脈でもっとも耳目を集めやすいだろう同書のトピックは、第二章の中核をなすAuto-Tune論、とりわけモロッコのベルベル人コミュニティにおけるAuto-Tuneの受容だろう。欧米のポップミュージックを席巻したこのテクノロジーが北アフリカの少数民族のコミュニティに普及しているという事実だけで、興味深い現象だ。
Auto-Tuneは主にヴォーカルの音程を補正するソフトウェアで、この分野では最も有名なブランドのひとつ。1996年の登場以来、ポップミュージックに革命的なインパクトを与えた。のみならず、特殊な用い方をするとヴォコーダーに似た「ロボ声」を作り出せるため、00年代以降には「補正」の範疇を超えたエフェクターのように常用されてもいる。
このAuto-Tuneが、ベルベル人の女性歌手の歌声に必ずといっていいほどかけられている(=「ロボ声」として使われている)ことをクレイトンは見出す。しかも、その普及は2000年代初頭のこと。西洋のポップミュージックで爆発的に流行するのとほぼ同時か、ともすればもう少し遡るかもしれない。加えて、現地のエンジニアは、Auto-Tuneに丁寧にも搭載されたアラブ的な旋法にアジャストする機能を用いるのではなく、ソフトウェアをほぼ初期状態のセッティングのまま、エフェクトのかかり具合を最大にするだけなのだという。
現地をフィールドワークし、ミュージシャンやエンジニアと交流しなければ見出しえないこうした事実から、クレイトンはポップミュージックにおけるAuto-Tuneの濫用や、それが現代の音楽文化に及ぼす影響への社会学的、人類学的な思索を開始する。それはまた、新しいテクノロジーによって改めてあらわになる、共同体のなかに根付く「伝統」なるものの核心を照らし出す。たとえば、実はAuto-Tuneがイスラム文化で重視される巧みなメリスマを強調するのに最適であること、また、女性の歌声に求められるベルベル人のジェンダー観ときらびやかな「ロボ声」に意外な親和性が見られること、等々。
既存のローカルな文化がグローバル化(この場合はテクノロジーのかたちをとる)に飲み込まれながらも、その波を人びとが思いもしないかたちで乗りこなすことによって文化そのもののアイデンティティが問い直され、また想定外の用法によってテクノロジーそのものがよってたつ文脈も相対化される。クレイトンが世界を遍歴するなかで体感し、言語化してみせるこうしたダイナミズムは、「ワールドミュージック」のありようを考察するうえで貴重な視座を提供してくれる。
「ワールドミュージック2.0」
最初に「ワールドミュージック」が話題を呼んだ80年代と2018年現在のあいだでは、音楽産業をめぐる状況は大きく変化している。制作の現場においてはデジタル録音の普及、ProToolsをはじめとしたDAWの一般化が挙げられるし[2]、流通と消費に目を向けてみても、アナログレコードからCDへの移行、音声圧縮フォーマットの普及、iPodの登場とダウンロード配信の一般化、そしてストリーミングプラットフォームの登場と、産業構造を変えるレベルの核心がいくつも起こった[3]。
クレイトンは、こうした変化のうち、インターネットを介した音楽コンテンツの流通サイクルの劇的な加速や、DAWの低価格化に伴う制作環境の民主化を経た00年代以降の「ワールドミュージック」を、「ワールドミュージック2.0」と名付ける。ドットコムバブルを思わせるいささか時代がかった命名だが、00年代に世界各地のローカルなサウンド――ダブステップ、バイレ・ファンキ、クドゥーロ等々――が次々紹介され続けたことを思い起こせば、実際それらが80年代に続く第2の「ワールドミュージック」の潮流であることは疑いえない。また、情報テクノロジーを中心とした変化であるのだから、「2.0」の名はたしかにふさわしいものだ。
「ワールドミュージック2.0」は00年代に特有の現象ではない。現在も、ダンスホール・レゲエの世界的なブームや、その派生としてのアフロビーツ(フェラ・クティに端を発するアフロビートではなく、ダンスホールのサウンドに影響を受けたアフリカ発のダンスミュージック)、そのイギリス経由の変異体であるアフロスウィング、また南アフリカから登場したゴム、そしてアメリカを席巻しつつあるラテントラップに至るまで、ローカルなサウンドがグローバルなポップスのフィールドに進出する例は後を絶たない。
ここでダンスミュージックが特権的なジャンルとなっていることは必然であり、そこに同書のアドバンテージがある。制作プロセスのほとんどすべてがデジタル化されているダンスミュージックは、DAWをはじめとするテクノロジーの発展と民主化の恩恵をもっとも受けやすいし、またサンプリングやリミックスといった技法はインターネットによる情報流通との高い親和性を示す。また、DJやプロデューサーは絶え間なく未知の音楽を探求(=ディグ)してはダンスフロアを通じて拡散し、世界的なトレンドをつくりだす、現代のポップミュージックにとって最も重要なプレイヤーでもある[4]。クレイトンのテクノロジーへの理解とダンスミュージックへの鋭いアンテナ、そしてなによりDJとしての現場での経験が、アクチュアルな問題提起と思索を根拠づけているのだ。
ときにダナ・ハラウェイやレフ・マノヴィッチといった論客の名を示しながら展開する文章の筆致は、クレイトンの旺盛な批評精神と、音楽への真摯な姿勢を感じさせてやまない。また、折々にさしはさまれるさりげない情景の描写がもつ得も言われぬ情緒は、同書をレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』にも連なる紀行文学の系譜に位置づけたくなるほど。同書が扱うトピックや理論的な示唆はこの文章で示したものだけにとどまらない。グローバル化が進行するなかで再編が続くポップミュージックシーンに対して、ひとりのDJがここまで雄弁な記録を残したことは喜ばしい。
imdkm(ブロガー、フリーライター)
註
[1] こうした「ワールドミュージック」をめぐる諸々の議論のサーヴェイとしては、以下の論文を参照した。輪島裕介「音楽のグローバライゼーションと「ローカル」なエージェンシー : 「ワールド・ミュージック」研究の動向と展望」『美学芸術学研究』20巻、193-225頁、2002年。
[2] ポップミュージックとテクノロジーの関係性については、日本語で読める手頃な読み物として、エンジニアの中村公輔が著した『名盤レコーディングから読み解くロックのウラ教科書』(リットーミュージック、2018年)がある。同書は形式的にはエッセイ的なものだが、現場のエンジニアの視点からポップミュージックを支えるテクノロジーのあり方を知ることができる。未邦訳文献にも、有名なところではブライアン・イーノの論考をはじめいくつか重要なものがあるが、現在調査中のため割愛する。
[3] 音響テクノロジーの発展によって激変する音楽産業を捉えた名ルポルタージュとして、スティーヴン・ウィット著、関美和訳『誰が音楽をタダにした?──巨大産業をぶっ潰した男たち』(早川書房、2016年/2018年に文庫化)がある。音声圧縮フォーマットの発明に翻弄される研究者・リスナー・レコード会社を通じて、CD以降ストリーミング以前の混迷する音楽産業の様相が描き出される。
[4] 『アップルート』でも言及されるメインストリームのトップDJのひとり、Diploの活動はとりわけ注目に値する。ローカルなダンスミュージックの発掘とフックアップにかけては近年でもっとも影響力のあるDJであり、冒頭でも触れた「文化的盗用」の問題でしばしば矢面に立たされる人物でもある。「GQ」誌が詳しくレポートしたアフリカツアーの模様(「On Tour With Diplo In Africa (Exclusive)」https://www.gq.com/story/diplo-africa-tour-interview、2017年8月7日公開、2018年10月20日最終閲覧)や、彼のメインユニットであるMajor Lazerが「西側」アーティストとして初のキューバ公演を達成した顛末を捉えた2016年のドキュメンタリー『Give Me Future』(Apple Musicにて限定公開)は、現地のオーディエンスやミュージシャンとの交流の様子も含めて興味深く、一読・一見をおすすめする。