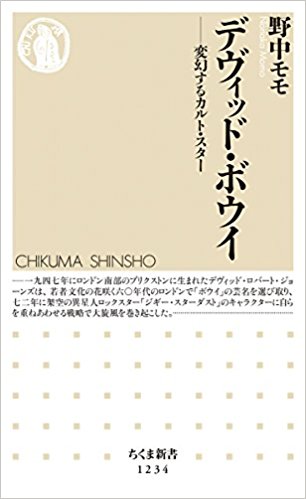2017年1月に出版された、野中モモによる『デヴィッド・ボウイ —変幻するカルト・スター』は簡潔な筆致で、デヴィッド・ボウイにまつわる「出来事」を析出させています。ともすれば「わたしとデヴィッド・ボウイ」というような内容を招来してしまうアーティストであるボウイを、ここまで正確かつ冷静に批評した本書は、彼を題材にしたあらゆる本の中でも白眉ではないでしょうか。そして、その沈着とした文体から正反対の「熱さ」やボウイのチャーミングさをも、ともに感じ取られる点に改めて、人の心情を「増幅」させてやまないデヴィッド・ボウイという人間自体の魅力を再認識させられます。
著者はこの本で「ボウイの多彩な作品と生涯を紹介し、その全体像の輪郭を浮かび上がらせること」と同時に「ボウイの歩みと彼がいた時代を一つの流れとして描き出」(p15)そうとしていますが、その目的は高度な次元で達成されています。つまり著者はアーティスト、デヴィッド・ボウイの生み出した作品自体の解説やそのキャリアを丁寧に追うとともに、彼がアーティストとして活躍した1960年代から2010年代という「時代」の中で生きた彼の肖像をも、同時に詳らかにしているのです。よってこの書評では、その巧みな形式に沿って、はじめにデヴィッド・ボウイを、「変幻」し、自らを「増幅」/「増殖」させ続けたアーティストであるという視点から探ります。次に、20世紀末から21世紀初頭という激動の世代を生きたアーティストとして、「時代」とどのようにボウイが関わってきたか、「増幅」というキーワードを用いて明らかにしていきたいと思います。
デヴィッド・ボウイの魅力とは何なのでしょう。あたかも答えのない問いを問いかけるスフィンクスのような官能性を持って、彼は人を悩ませます。デヴィッド・ボウイであること、つまりデヴィッド・ボウイとして「立つ」こと。一介のモッズ青年であったデヴィッド・ロバート・ジョーンズが1966年に、自分の芸名をデヴィッド・ボウイと決めた瞬間から、彼には「消費される側に立つ」自意識がありました。それは初めてのシングル『キャント・ヘルプ・シンキング・アバウト・ミー』において既に見て取れます。「『ユー(あなた)』に捧げる甘いラブソングにあふれたポップ・ミュージックの世界をひっくり返すかのような『ミー(自分)』で『頭がいっぱい』」(p42)だという自意識を歌うこのシングルがデヴュー作であるというのは、後の彼が自己のキャラクター性を「意識的」に何度も「変幻させる」未来を示唆していると言えるでしょう。
この「変幻」というモティーフは、2013年からロンドンを皮切りに2017年4月現在、日本に巡回中であるいわゆる「デヴィッド・ボウイ大回顧展」=“David Bowie is”という命名においても、読み取ることができます。エレクトロニック音楽グループ、“アート・オブ・ノイズ”における活動で有名なポール・モーリーによるこの命名は、実に素晴らしい「煽り文」ですが、ここで肝になってくるのは、“is”という動詞です。一般にBe動詞として習うこの動詞の起源には、英語自体の祖先でもあるドイツ語が影を落としています。“is”に相当するドイツ語は“ist”で、その原型は英語だと“be”、ドイツ語では“sein”です。そしてこの“sein”という動詞は、ドイツ語で実は名詞“Das Sein”にもなるのです。この名詞は「存在」という意味なのですが、その名残を英語はそのニュアンスに持っています。
例えば、“David Bowie is an artist.”という文は「デヴィッド・ボウイはアーティストです」という意味であると同時に、「デヴィッド・ボウイはアーティストとして『存在して』います」というような語気があるのです。つまり“is”には、自己の存在=あり方=「立ち」方を規定するという含みがあるわけであり、その地点から“David Bowie is”という展覧会名を考えてみると、“is”以下を規定しないで、様々なものに変幻する可能性を内包したタイトルであることがわかるでしょう。そして彼は、そのような自己の様々に変幻する「立ち位置」を自意識として持ち続けたアーティストなのです。
そして我々は、“is”が現在進行形で使われることも知っています。それを踏まえて、この展覧会の内容紹介のドキュメンタリー映画“David Bowie is happning now”の名前を解釈してみましょう。するとそれは「デヴィッド・ボウイという存在が、今この瞬間に生起している」と捉えることができます。そして“is happning now”という句は、ボウイの変幻する様子と同時に、彼が「いま、ここ」という地点で立ち現れてくる何者かであるというように解釈できるでしょう。著者はボウイの『世界を売った男』(1971)が「内省と陰鬱な想像力をロックに仕立て上げる〜『いま、ここ』にある生命力」を持っていると評していますが(p66~7)、まさにそれはボウイのキャリアを通じた、一つのスタンスであったのです。つまりあらゆるものに「変幻」し「増幅」しながら、その変化自体をデヴィッド・ボウイという同一性のもと、いま=ここ=現在という場に収斂させる表現の運動こそが、ボウイの本質だったのです。
さて、“is”についてもう少し解釈を進めてみましょう。“is”は、過去分詞を伴って受動態を作り出す機能も持っています。ここに、アーティストとリスナーの関係を想起することが可能ではないでしょうか。ボウイの作品をリスナーは文字通り聴き=消費するのですが、ボウイは作品制作にあたって、いつも消費されるべき、あるキャラクター(偶像)を用意していました。しかしそれは、大きな賭けでもあります。一度キャラクターが示されその文脈のみで作品が消費されると、そのキャラクターが魅力的であればあるほど、それからの脱却には、多大な努力を要することになるからです。
例えば、『ジギー・スターダスト』(1972)においてボウイは、宇宙からやってきたロックスターであるジギーという男を演じ、そのキャラクター性で一躍スターダムに上り詰めました。しかし彼がジギーの呪縛から逃れるためには、大変な肉体的/精神的苦痛を要することになったのです。つまりこの消費の過程を“is”というキーワードを使って表すならば“David Bowie was consumed as Ziggy Stardust by his lisners.”(デヴィッド・ボウイは彼のリスナーによって、ジギースターダストとして消費された)という受動態の文にすることができます。彼は、1973年7月3日のイギリス凱旋ツアーの最終日に「ジギー・スターダストの死」をわざわざ宣告するに至るのですが、そのことはいかに「自己がどのようなキャラクターとして消費されているのか」という点に彼が自覚的であったかを示す逸話と言えるでしょう。
そしてその消費のされ方に関する自意識がより一層、ボウイ/ジギーの運命の壮絶さを物語ることにもなります。ボウイが、アルバムやそのツアーにおいて、ジギーというキャラクターで消費され尽くされるということは、次のような意味を持ちうるのではないでしょうか。つまりボウイはその自意識によって、ロックスターというものが、いかに虚構の産物であり大衆やレコード会社に祭り上げられ消費されるのみの運命であるかを、身を以て「増幅」させ提示したのです。そのような観点からすると、ボウイ/ジギーはメタ=ロックスターと言えるでしょう。
換言すればボウイはジギーとして消費されることで、まさにロックという祝祭の「供物」となったのです。すると、ロックスターを主題にしたコンセプト・アルバムであるとも読み取れる『ジギー・スターダスト』の最後の曲が、『ロックンロールの自殺者』である点は、とても示唆的に聴こえます。つまりキャラクター的で単一な消費=解釈は、ある意味で「死」と似ているのです。キャラクター=ジギーというペルソナの遊び=演技が成立しなくなり、その一点に固着し反復を余儀なくさせられる時、アーティストはもはや何も新しいものを生み出せない状態となります。それは文字通りアーティストの「死」であって、彼は一つのキャラクターのみを求める聴衆によって「殺される」のです。そしてそれを全て承知の上で、その地点へ自らを向かわせるロックスターは、まさに自殺者ではないでしょうか。
しかし、こういった解釈もボウイという「変幻」し「増幅」する表現者の前では、可能性の一つとしてとどまるに過ぎません。著者は、このボウイとジギーのキャラクター設定の関連において、様々な解釈を具体的に示した上で、「すべてはあいまいで重層的で不定形なまま、どれも合っていてどれも違う、解釈の余地のたっぷりある」ものとしています(p79)。つまりボウイの作品が、あらゆる解釈に開かれているという意味で、また「どこに属しているのか、誰の味方なのか、デヴィッド・ボウイはそういったわかりやすい文脈に回収されることからとことん逃げ続け」(p227)、「どう解釈するかはきみ次第」(p247)といった問いかけとしての価値に、著者は重きを置いているのです。つまり、ボウイは一つのキャラクターとして消費される以上のスピードで、聴衆から逃れ遊戯=演技する場を確保していたというのです。そしてここにこそ、解釈の幅を広げるというボウイの本質である「変幻=増幅」の一つの達成をみることができるでしょう。
受動態としてのボウイは、リスナーによる消費という図式にとどまりません。彼は著者が紹介した通り「時代」というものを意識して、そこから大きな影響を受けているのです。ボウイは1976年、契約に関わる諸問題や自身のヘロイン依存を断ち切るべくベルリンに住まいを移し、そこで創作活動を続けることになりました。ボウイにとって西ベルリンという「文化的に豊かな都市での生活」は、「芸術への理解を改めて深める機会」を与え「創作意欲を刺激」(p132,133)したのです。それにはどういった背景があったのでしょうか。
まず指摘したいのは、西ベルリンという土地は東ドイツ国内の飛び地であり、嫌が応にも冷戦の影響を感じさせる、極めて特殊な場所であったということです。そして壁が築かれる以前から交響楽団などクラシックが盛んであったこのベルリンという都市自体が、表現することへの希求というものを感じさせる稀有な場所だったのです。詳しく見てみましょう。第二次世界大戦で徹底的な破壊を受け、さらに壁で分断された街には、当時から(今でも)工事の音が絶えませんでした。視界に入るものはクレーンや廃墟、いくつもの空き地と銃を持った兵士が立つ、鉄条網の引かれた灰色の長い壁です。そうした特異な街・ベルリンに住んでいた一部の若者は、冷戦の最前線という一触即発の危うさを秘めた時代の現実を芸術へと昇華させ、独自のシーンを形成していたのです。
ボウイはそのようなベルリンの街が生み出す芸術の、核心を見抜いていました。それはボウイの「(ベルリンでは)若くて知的な人たちがなんとかやっていこうとしていて、自分が週給いくら貰うか以上のことに興味を持ってる。ベルリンっ子はストリートでアートが何を意味するかに興味があるんだ。」(p132)という発言からも伺い知れます。そして彼は「分断されたベルリン」で体験した、冷戦という時代の空気を「増幅」させ、現在でも古びないような前衛性に富んだ「ベルリン三部作」を、世界中へ発信したのでした。
同時に著者はボウイの「時代」への目配りが、時として落とし穴ともなり得ることにも言及しています。それは、セールス的にもアーティスト的にも落ち込んだ80年代後期のボウイをして、「とにかくお金を儲けることを是とする近視眼的な開き直りと成金趣味が横行していた」時代の空気を反映し「この時代のだめな部分を思い切り体現してしまったのではないだろうか」(p175)と批評している点に表れます。しかしこのエピソードは、失敗するほど「時代」に対して敏感であり、それを「増幅」する彼の志向ゆえの迷走であることは、言うまでもありません。このようにボウイの作品は、時代と不即不離の関係を持っているのです。
するとリスナーは、ボウイの音楽を通じて、時代そのものを知ることができ、またそれは同時に「時代の中で生きる自己」という問題をも、彼によって突きつけられるのです。本書においてはボウイが時代をどのように「増幅」したか、正確に再現されています。つまりボウイの作品を経由することでロック史、いや現代史のある部分が描き出されているのです。著者はその点でボウイの正確な共鳴者となり、それを「増幅」しています。その視点はまさにボウイの意識していた「時代」への関わり方を再現しており読者へ、ボウイは何を表現したのかを伝えているのです。
同時に、著者はボウイの作品に込められた、極めて私的な部分にも着目しています。例えば著者が『ハンキー・ドリー』(1971)を「『作り込み』と『私的な感情』がちょうどいいバランスでお互いを引き立てあう」と評している点(p72)に、そうした視座が読み取れます。すると本書では、時代という大きな流れの中に生きる一個人として、ボウイがどのように感じたか・生きたかという小さな流れにも等しくウェイトが置かれているわけです。そして二つの流れが交差するところに、デヴィッド・ボウイという表現者が立ち現れるという点が、この本に通底するスタンスとなっています。そして、それこそまさにボウイの「立ち位置」の正鵠を射ているのです。そしてその稀有な地点に立ち続けていたが故に、アーティスト、デヴィッド・ボウイは個人、デヴィッド・ロバート・ジョーンズの死をも『★』(二〇一六)によって「作品にしてしまう」ことができたのではないでしょうか。
★
デヴィッド・ボウイとは、文化的「アンプ=増幅器」です。彼は常に機械のような正確さで、影響を受けたものからその真髄を抽出し、自己のものとして再創造しました。彼の持つ広く張られたアンテナは、常に「時代精神」とも呼べるような、時代の気風そのものを切り出しました。それを彼は、様々な表現活動を通じて全世界へ送り返すことで、時代の文脈の中で生きる聴衆に、「体験」として、知覚させることを可能にしました。そしてリスナーは、彼の作品を聴き解釈することで新たな「デヴィッド・ボウイ」を、「変幻」させ創造し「増幅」させることができるのです。「デヴィッド・ボウイ」とは増幅器であるとともに増幅する運動そのものなのです。そういった意味で、「デヴィッド・ボウイ」という存在は死ぬことが不可能なのです。なぜなら運動「そのもの」は、決して途絶えることがないからです。そしてこの本はその運動への案内書として、最も信頼が置ける一冊となるでしょう。
筑摩書房 デヴィッド・ボウイ ─変幻するカルト・スター / 野中 モモ 著