鎧塚みぞれ(CV: 種﨑敦美)はなぜフグを愛でるのか。それはフグに脚がないからである【図1】。

【図1】『リズと青い鳥』ロングPV(https://youtu.be/lQxwNaoFdQQ)
映画『リズと青い鳥』を監督した山田尚子が脚にこだわりをもつ「作家」であることはファンにとって周知の事実であり、彼女が手がけた過去の作品を見ても印象的な脚のショットは枚挙に暇がない。また、監督自身が「脚は口ほどにものを言う」という趣旨の発言をしたことも知られており、登場人物の心理を細やかに実現する手段として脚の「表情」を利用していることは改めて指摘するまでもないだろう。
じっさい、本作は約1360のショットによって構成されているが、そのうち登場人物の脚だけを捉えたショットは少なくとも120以上にのぼり、比率で言えば、映画全体のほぼ9%を脚のショットが占めていることになる。ショット数ではなく、映し出されている時間で計算すればこの割合はもっと少なくなるだろうが、いずれにしても、本作が脚を強調していることは明らかである(ネット上には山田作品における脚の表象に着目した考察ブログが数多く存在している)。
脚の表現にこだわり続けてきた山田にとって、『リズと青い鳥』は一つのメルクマールをなしている。本作に頻出する脚のショットは、単に各登場人物の性格や心理描写に寄与しているのみならず、作品のテーマおよび物語の展開と直接的に関わってくるからである。女性の脚を執拗に捉え続けた映画作家としてはフランソワ・トリュフォーが知られているが1、こと脚の演出に関して、本作を監督した山田はトリュフォーに比肩すべき境地に到達しているように思われる。その当否を判断するためには、彼女たちの足元を注視するに如くはない。
そもそも、『リズと青い鳥』の世界観にあって、脚はどのような位置づけを与えられているだろうか。多くの人間にとって、脚の存在は生の前提として組み込まれている(だからと言って、そうでない人々の存在を否定するわけではもちろんない)。一般に、映画のなかで人が歩いているシーンがあったとしても、それ自体に価値づけを行おうと考える者は少ないだろう。しかしながら、本作のようにあからさまに脚を強調している作品の場合、観客は必然的に脚の描写により多くの注意を向けることになる。そう、人間に姿を変えた青い鳥が、自らを地上に縛り付ける脚の存在をことさら意識せずにはいられなかったように。
本作は絵本パートと現実パートから構成されている。絵本パートでは、童話『リズと青い鳥』の物語が展開されていく。ある嵐の翌朝、孤独な一人暮らしを送っていたリズのもとに、青い髪の少女があらわれる(リズと少女の声は本田望結の一人二役)。リズの傍らに寄り添い、彼女の孤独を癒すために、青い鳥が人間に姿を変えてやってきたのである。こうして二人のつましくも楽しい共同生活が幕を開ける。
鳥が人間に姿を変えるとは、換言すれば、翼を失い、その代わりにより頑丈な脚を持つということである。このことは何を意味するだろうか。たとえば、絵本パートには、二人が洗濯物を干しているシーンがある。この場面で、風にあおられるシーツを押さえつけようとして青い髪の少女がぴょんぴょんと飛び跳ねていたことを見逃した観客はいないだろう。さらに、その直後には、リズのハンカチが風に飛ばされて空高く舞い上がってしまい、それを取り戻そうとした少女はその場で何度も飛び跳ねてみせる。しかし、翼を失い、もっぱら脚によって自らを支えている今の姿では、彼女は空を飛ぶことはできない。飛び上がろうとする少女の努力は重力によって阻まれ、彼女は地上へと引き戻されてしまう。脚の存在は、青い鳥の自由を縛る枷となっているのである。
やがて少女が青い鳥であることに気づいたリズは、彼女を自由にしてやることを決意する。地上で窮屈な生活を送るのではなく、大空を自由に飛び回ることこそが青い鳥にとって真の幸せだと信じたからである。
本作の現実パートで展開される物語は、絵本パートで青い鳥が自らの自由を縛る足枷から解放される寓話と軌を一にしている。もちろん、童話のなかの少女は翼を取り戻せば空を飛べるようになるが、生身の人間に同じことはできない。その代わりに、映画は、みぞれの成長を「鳥かご」から解放された青い鳥のイメージに仮託しているのである(その際、少女たちの足元が強調されていることは言うまでもない)。
「鳥かご」のモティーフは、現実パートの随所に見出せる。監督の山田尚子と脚本の吉田玲子が公式パンフレット所収の対談で言明しているように、学校という閉鎖的な空間は鳥かごの比喩になっている(現実パートのほとんどすべてのシーンがこの学校=鳥かごの内部で進行していく)。このとき、理科室に置かれたフグの水槽は、学校という鳥かごのなかに置かれたもうひとつの鳥かご的装置として機能する【図2】。学校とフグの水槽は、それ以外の同種のイメージと響応しながら、本作における鳥かごの主題系を形成していくのである。

【図2】『リズと青い鳥』ロングPV(https://youtu.be/lQxwNaoFdQQ)
外界との交渉を遮断された閉鎖環境としての水槽と学校が共有する最大の特徴は、そこが安全な場所であることだろう。学校およびその内部で繰り広げられる人間関係は、みぞれの音楽的才能を文字通り「飼い殺し」にしかねないものでありながらも、みぞれ自身はそのぬるま湯的な居心地のよさから離れられないでいる。一方のフグはといえば、水槽から取り出されたら呼吸することさえかなわず、たちどころに死んでしまう。かといって海に放流したところで、そこは外敵の跋扈する危険な場所であり、死ぬリスクは水槽の比ではない。定期的に水の交換が行われ、餌を与えてもらえる水槽という環境は、生存という観点から見ればフグにとってきわめて安全な、まさに天国のような場所である。
みぞれは、自らのオーボエの才能に制限をかけることで、居心地のよい日常、すなわち大好きな傘木希美(CV: 東山奈央)とともに過ごす天国のような日々を維持しようとしてきた。コンクールの自由曲「リズと青い鳥」ではみぞれのオーボエと希美のフルートの掛け合いが主となるパートがあるが、希美との関係性を考えたとき、みぞれにはそこで希美の実力をはるかに凌駕するような演奏をすることはできなかった。みぞれと希美の音楽的才能が同程度であることは、二人の関係の前提となっているからである(二人は各楽器のエースとしてほとんど互角の実力を持つと他の部員から思われている)。しかしながら、みぞれの演奏について、後輩の高坂麗奈(CV: 安済知佳)には、「窮屈そうに聞こえる」、「わざとブレーキかけてる」と批判されてしまう(このとき、自己主張の強くないみぞれがあれほど強硬な反発を示したのは、自分でも薄々そのことに気がついていたからだろう)。
管理された水槽のなかで一生を過ごせばいいフグと、いくら居心地がよくともいずれは学校を出ていかなければならない人間とでは、生の条件が決定的に異なる。脚も翼も持たず、それゆえに居住転居の自由を有さないフグとは違って、人間は自らの脚で次なる一歩を踏み出すことができる。人間の脚は、足枷であると同時に、青い鳥にとっての翼に相当するような、両義的なものなのだ。青い鳥の飛翔に仮託されているのは、みぞれが希美への過度の依存を断ち切り、自らの音楽的才能を(もちろん比喩的な意味で)自由に羽ばたかせる姿である。
本作で描かれる鳥かごに入れられた青い鳥は、そのままかごのなかで一生を終えるか、それともそこから出て大空を自由に飛び回るかの選択を迫られる。対して、先に述べたように、フグにはそもそもそのような自由が与えられていない。みぞれがフグに癒されるのは、そのヴィジュアルのかわいらしさもさることながら、水槽のなかを優雅に泳ぎ回る姿のうちに、犠牲を伴って安全圏から抜け出す決断を下す必要のない安楽な立場を幻視しているからだろう。
したがって、みぞれが愛着を抱いて世話をしているのがカメやカエルかウーパールーパーなどではなく、脚のないフグであるのは必然である。鳥の場合は翼とともに、ささやかながらも脚も持っているため、地上を歩くこともできるが、フグにはそのように二足のわらじを履く自由は許されていない(そもそも脚がないのだから一足も履けないが)。そうであるがゆえに、鳥は地上と空との間で引き裂かれた存在となる。じっさい、フグの水槽がある理科室には、これ見よがしに鳥の剥製や骨格標本が置かれている。それらが永久に地上に留めおかれた死せる鳥のイメージを体現するとすれば、その対極にあるのは校舎の周りを活き活きと飛び回る鳥たちのイメージであり、自由を制限された水槽のなかのフグは、その中間に位置づけることができる。
翼も脚も持たない水槽のフグは、大空を飛び回る鳥類と、地上に縛り付けられた人類の中間的な存在態様を示している。野生であれば海を本来の住処とするフグは、理科室の水槽に入れられたことでちょうど天地の間に居を構えることになった。また、四方を透明なガラス板に囲まれた水槽のなかで、これまたほとんど透明な水のなかを、ヒレを使って優雅に泳ぐ姿は、(少なくとも人間よりは)鳥が空を飛んでいるイメージに近い。それゆえに、フグは単にみぞれに癒しを与えるだけではなく、天と地を媒介し、地表に縛り付けられているみぞれを天上へと導く存在ともなりうるのである。
このように考えると、フグを見たみぞれが、その直後に両手を広げて走る希美の姿を想像していることの意味が理解できるだろう。一見したところ水中を自由に泳ぎ回っているフグの姿は、みぞれの眼には、あたかも空を飛び回る鳥のように自由奔放に生きている希美の姿と重なって見えるからである(もちろん、フグの自由がまやかしであるのと同様に、希美もまたみぞれが考えているほどに天真爛漫に生きているわけではないが)。
ここでフグと希美の連続性が示唆しているのは、みぞれの音楽的才能を縛る主要因のように思われる希美もまた、みぞれにとって天と地を媒介する存在なのである。みぞれ自身も、制限された檻のなかで安逸な日常を享受することを望みつつ、一方でそのような環境に対する違和を仄めかすような両義的な行動を冒頭から見せている。この点について、脚の存在が強調されていることとあわせて確認しておこう。
映画の冒頭、みぞれは校舎の前の階段に座って誰かを待っている。やがて足音が近づいてくるが、それはみぞれの待ち人のものではない。ほどなくして別の足音が聞こえてくる(このとき、背後で流れている音楽も調子を変える)。足音の主が姿を見せる前に、みぞれはそれが待ち人のものであることを察知し、顔を上げる。はたして、希美が颯爽と登場し、二人は連れ立って校舎の方へと歩いていく(二人の足音はオフで流れる映画音楽と溶け合っていく)。この時点までに、階段に腰掛けたみぞれの脚や、歩いている希美の足元を捉えたショットがすでに存在しているが、同時にそれが聴覚的にも強調されていることはぜひとも気に留めておくべきだろう(何と言ってもこれは音楽をめぐる物語でもあるのだから)。
ここでは、彼女たちの通う高校の校舎が高台に建てられているという設定が効いてくる。二人が歩く際には、先を行く希美のあとをみぞれがついていくという構図をとっているため、常に希美の方が高い位置にいることになり、みぞれはそれを仰ぎ見る格好になる。つまり、この時点で希美はみぞれよりも、より天に近い位置を占めているのである。先を行く希美は、青色の羽根が落ちていることに気づいて拾い上げ、それをみぞれに手渡す【図3】。これは、やがてみぞれが羽ばたいていくことになる空と、現在彼女が置かれている地上とを希美がつないでいることをさりげなく示す好演出である。先を行く希美とそれを仰ぎ見ながらついていくみぞれという構図は、二人が校舎のなかに入ってからも維持され、とりわけ音楽室へと向かう階段を登る際には、二人の高低差がはっきりと強調されている。

【図3】『リズと青い鳥』本予告60秒ver.(https://youtu.be/MBDaON4IPnc)
序盤のこの構図は映画の末尾で反転することになるが、その議論には最後に立ち戻ることにして、この冒頭シーンでは、一人で学校の前までやってきたみぞれが、いったん引き返すようなそぶりを見せながらも、結局は校舎手前の階段で希美が来るのを待っている点に注目しておこう。ここには希美への依存の強さがあらわれているとともに、鳥かごたる学校に対するみぞれの忌避感がすでに仄めかされている。
しかし、その一方で、みぞれにはまだかごから飛び立つための心の準備ができていない。おそらく、バスケットボールのシーンはそのことを示すために置かれている。漢字で「籠球」と表記されるバスケットボールとは、文字通り、人間の頭よりも高い位置に設えられたバスケット=かごをめがけてプレーヤーたちが跳躍を繰り返す競技にほかならない。映画には授業が行われている体育館の天井を写したショットがあるが、鉄骨が張り巡らされたその構造は視覚的に鳥かごを連想させる。つまり、バスケットボールは本作にあって学校や水槽とともに鳥かごの主題系をなしているのである【図4】。
ここでポイントとなるのは、体育の授業中、クラスメートの中川夏紀(CV: 藤村鼓乃美)にメンバー交替を促されたみぞれがゲームへの参加を拒んだ点だろう。もちろん、彼女にはまだ飛ぶための心づもりができていなかったからである。2

【図4】『リズと青い鳥』ShortPV3 犬猿の夏紀と優子編(https://youtu.be/-ZdHAUFlcnA)
しかし、みぞれの心情は次第に変化していく。その変化を端的にあらわしているのが、吹奏楽部の後輩・剣崎梨々花(CV: 杉浦しおり)の誘いに応じて、「ダブルリードの会」(という名の女子会)に参加することを決める場面である。二度に渡って断っていたこの会合への参加表明は、希美以外の他者と関わりを持とうとするみぞれの心境の変化を反映していると同時に、この会合が行われるのが学校の外(ファミレス)である点で、鳥かごからの精神的かつ物理的な離脱志向が表現されている。
このエピソードは、希美とプールに行くことになった際、他に誘いたい子を問われたみぞれが梨々花の名前を挙げた場面とも呼応している。遊びに行く場所がプールであるのは、フグの水槽のイメージと対応させているからだろう。しかし、ここでは学校=鳥かごの外を目指しながらも、海や川ではなく、プールというあくまで人工的な閉鎖環境=別種の鳥かごに取り込まれてしまうあたりに、かごから解き放たれることの困難さがあらわれている。しかも映画内では、じっさいにプールで遊んでいるシーンは一切描かれない(実に大胆かつ鮮やかな省略である)。そのときの様子を事後的に語る際、プールで撮った写真を梨々花がスマホ画面に表示させるのみである【図5】。楽しい夏の思い出は、こうして液晶画面という新たな水槽=檻に入れられることになる。3
映画も終盤にさしかかり、コンクールの本番が近づくと、部員たちは音楽室の床に吸音用の毛布を敷き詰め、上靴を脱いで練習に取り組む【図6】(音楽室の前に並べられた大量の上履きのショットの美しさは、『東京物語』[小津安二郎、1953年]の熱海の旅館で部屋の前に並べられた二組のスリッパを映し出したショットに匹敵する)。毛布の厚みの分だけ、彼女たちは天に近づけたのだろうか(それとも脱いだ上履きの分で相殺されてしまうだろうか)。すぐれた映画は、観客に悟りにも似た経験をもたらす。そこに映し出されているのは、見かけ上はあくまでまったくいつもの日常的な経験でありながら、人々を地上から2インチばかり浮かび上がらせる。もちろん、『リズと青い鳥』はそのような映画のひとつであり、作品を見ている観客だけでなく、劇中人物の意識をも地上から浮き上がらせてしまうのだ。

【図6】『リズと青い鳥』ShortPV4 北宇治カルテット編(https://youtu.be/TH5IAkYE4KU)
ある日の練習で、ついに己の能力を解放し、圧巻の演奏を披露したみぞれは、それによってこれまでの希美との関係を終わらせてしまう。いったん壊れた関係を別様に結び直すために要請された儀式が理科室での「大好きのハグ」である。空と地上の媒介者としてのフグは、映画の終盤にみぞれと希美が理科室のフグの水槽の前で「大好きのハグ」をした際にもその役割を果たしている。このシーンでは、こちらに背を向けて水槽の奥側へと泳ぎ去っていくフグのショットに、飛んでいく鳥のシルエットが廊下を通り過ぎていくショットをつなげている。鳥のシルエットは、廊下に影を落としている窓のフレームを次々に突き抜けて飛んでいく。いくら悠々と泳ぎ回っているように見えても、所詮は限られた四面体のなかでしか生きられないフグと違って、鳥のイメージはその枠組み(フレーム)をこそ突き破っている。みぞれが地上に縛り付けられた鳥であることをやめ、つまりはほどよいぬるま湯のなかで見せかけの自由らしさを担保されたフグのようであることもやめ、空を駆ける鳥へと変貌を遂げる瞬間が、ここにははっきりと描き込まれている(その儀式を見届け、媒介者としての役目を終えたフグは、だから背を向けて泳ぎ去っていくのである)。
みぞれに対抗して音大志望を口にしていた希美は、希望進路を普通大学に切り替え、受験勉強に本腰を入れはじめる。一方のみぞれは、希美と同じ大学に入れなくとも、あくまで音大受験を貫く覚悟を決め、ひとり音楽室でオーボエの練習に励む。放課後にそれぞれの時間を過ごした二人は、校舎の前で待ち合わせ、連れ立って帰路につく。ここで冒頭の構図が反転して提示される。学校が高所にあるため、先を行く希美に対して、今度はその後ろからついていくみぞれの方が高い位置を占めるようになるのである。二人は帰り道の階段の途中で立ち止まり、その構図を維持したまま会話を交わす。その後、階段を降りて平地に至ると、それに伴って彼女たちの立っている位置が水平になり、さらに二人が同時に同じ言葉を口にすることで、シンクロニシティが強調される(「ハッピーアイスクリーム!」)。最後のショットは、振り返った希美の背中と、希美の顔を見て驚くみぞれの表情を映し出している。このとき、フレームが彼女たちの上半身だけを切りとっている点に注目したい。これまで執拗なまでに脚を強調してきたにもかかわらず、最後にはその脚の方をカットしているのである。たとえ束の間の錯覚ではあれ、地上との繋留点である足から解放されたみぞれは、そのとき天にものぼるような心地だったことだろう。
鎧塚みぞれはなぜフグを愛でるのか。それはフグに脚がないからである。より正確に言えば、フグには翼も脚もなく、与えられた閉鎖環境に自足しているように見えるからだ【図7】。水槽という檻のなかで安全に暮らしている点で、フグはみぞれの現状と重なる存在である。一方で、みぞれを地上に縛り付けている脚を持たない点で、フグはみぞれよりも鳥に近い位置にいる。みぞれは、そのようなフグの存在を足がかりにすることで、青い鳥のいる高みへと昇っていくことができたのである。
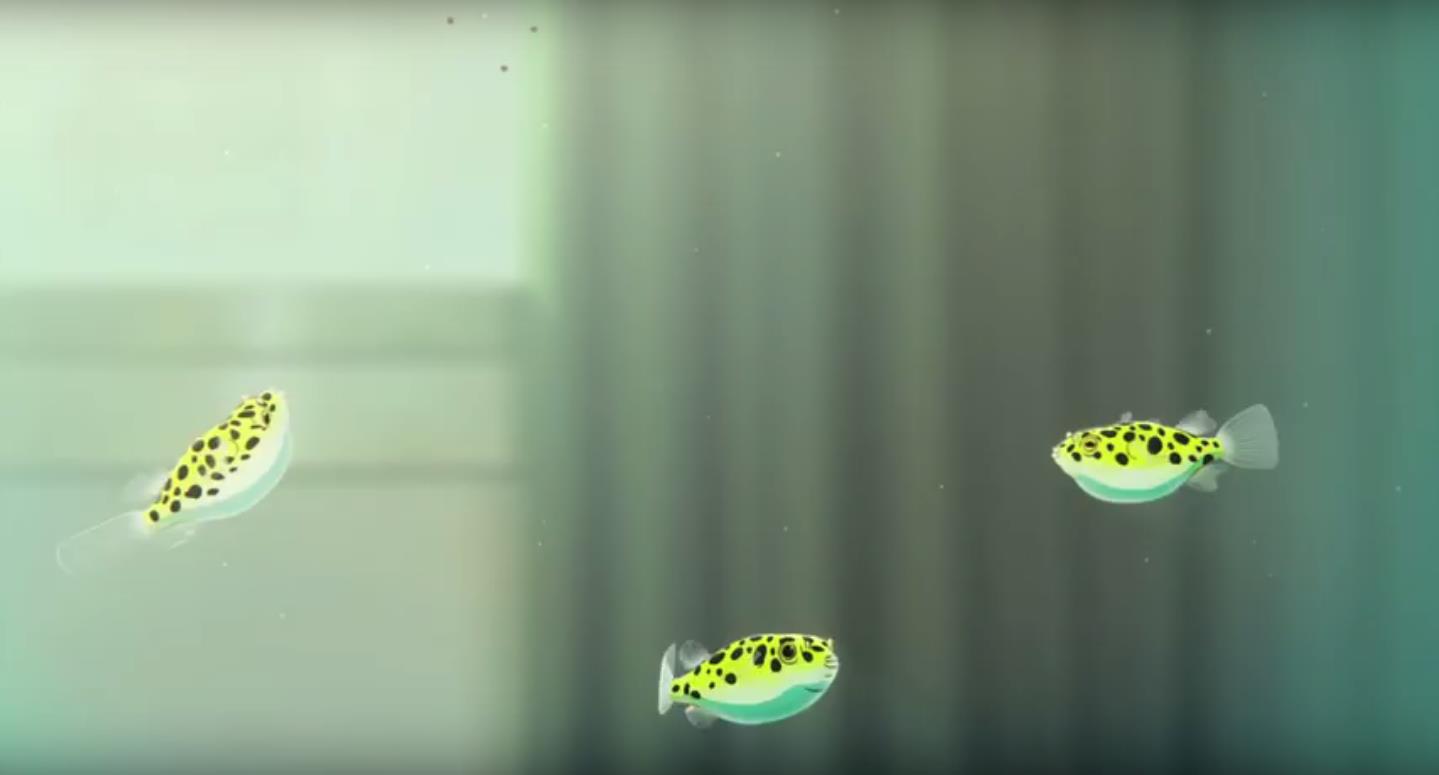
【図7】『リズと青い鳥』ミュージックPV(https://youtu.be/OGWO3u8zgTU)
〈註〉
1 トリュフォー映画に頻出する脚のショットの意義については、原田麻衣「トリュフォー作品における脚ショットと女性像」(CineMagaziNet!, No. 21、2018年、http://www.cmn.hs.h.kyoto-u.ac.jp/CMN21/PDF/harada_article.pdf)の議論を参照されたい。
2 バスケの場面について付言しておけば、夏紀の放ったシュートがゴールから外れる点や、当該シーンが次のゲームの最初のジャンプボールで終わる点はいかにも気が利いている。本作では脇へと追いやられている夏紀も、いつまでも鳥かごのなかの世界に安住しているわけにはいかない。とはいえ、彼女たちの跳躍のゆくえは、この時点では宙に吊られたままだ。このシーンに散りばめられた細部は、そのような状況をさりげなくも的確に表現している。
3 フグと水槽のイメージは、吹奏楽部の後輩がクラスメートの男子学生と水族館デートに行くことになったという会話にも引き継がれている。何となれば、水族館の水槽は、理科室の水槽をより大掛かりに反復したものに過ぎないからで、彼らは水族館の水槽の巨大なガラスを前にして、そこに自らの姿を見出すことになるだろう。また、デートに行く際に着ていくワンピースを先輩から借りたが、サイズが合わなくて着られなかったという一見どうということもないやりとりは意味深長である。膨張した容量は行き場を求めて外殻を破壊する。卵の殻を破らねば、雛鳥は生まれずに死んでいく。死にたくなければ、容量の増大にあわせて自らが属す世界を不断にアップデートしつづけるしかないだろう。身丈に合わなくなった鎧は脱ぎ捨てていけばいい。そのとき、剣の力が必要ならば、それを恃めばいい。












1 Response
Comments are closed.