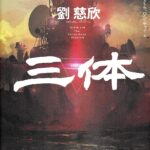アイデアとは魚のようなものだ。
小さな魚をつかまえるなら、浅瀬にいればいい。でも大きな魚をつかまえるには、深く潜らなければならない。
水底へ降りていくほど、魚はより力強く、より純粋になる。巨大であり抽象的だ。そしてとても美しい。
私はある特別な魚を探している。私にとって大切なのは、映画に翻訳できる魚だ。
(デヴィッド・リンチ『大きな魚をつかまえよう』より)

11月7日(金)TOHOシネマズ シャンテ、テアトル新宿ほか全国ロードショー
©2025『旅と日々』製作委員会 配給:ビターズ・エンド
二つの美学とその対決
カメラが捉えようとしているのはおそらく彼女の視線の先にある、なにもない空間だ。シム・ウンギュン演じる脚本家の李が机に座ったまま鉛筆片手に、悩ましげな表情で宙空をじっと見つめ、かと思うと瞼を閉じてそこにあるなにかを優しく摘もうとするがごとく鉛筆を挟んだままの右手の指を小さく動かし、今度は何か閃いたかのようにさっとメモを書き出す。カメラは彼女の顔ではなく、その視線を撮っている。その証拠に、視線の先にある何もない空間を中心に美しい構図が成り立っているではないか。これは、撮影よりも前にきっと意図されたであろう構図の再現であり、また同時に撮影開始後に起きたあらゆる不測の周到な排除なのだろう。それを、いかにも脚本家的なショットだとみなすことはきっと的外れではない。そもそも彼女の役自体が脚本家なのだ。おそらく撮影者は、このショットを通じて、脚本とはあらかじめ想定していた「意図」をその通りに遂行することだと、表現しようとしているのだ。
メモにはハングルが綴られ、「シーン1 夏 海辺 行き止まりに一台の車 後部座席で女が目を覚ます」と日本語の字幕が出る。おそらく彼女が脚本を書いたと思しき、つげ義春『海辺の叙景』を原作とした劇中映画のシーンがそれに続く。脚本の通り、車の後部座席に河合優実演じる若い女が寝ているところから始まるのだが、このシークエンスを支配する撮影の美学は、脚本家のショットとはまるで異なる。
撮影の美学は、水のモチーフを通じて具現化する。フロントガラス越しに後部座席の女を眺めるカメラの前に、車中のものなのか、車外のものなのか薄い霧が漂い、画面の外から運転席に車の持ち主の男が、そして画面を遮るようにフロントガラスのワイパーが視界に侵入する。続く、高田万作演じる青年を描くシークエンス、画面を覆い尽くす波間に顔を出す泳ぐ女の頭を捉えたショットに始まり、砂浜に座って本を読んでいる高田の髪は画面の外からの風でなびき、彼の遠く背後を海水浴客が通りかかり、画面の外から観光客のイタリア語と思しき声が、彼のことをカメラに撮っていいかと話しかける。中盤に見せ場として登場する男女の語らいを見守る長いショットは、会話ではなくその背後で水平線に日が没するのを待つためのものだ。ラスト、男は原作の通り、画面の向こうからやってくる大波に飲み込まれる。こうして劇中映画『海辺の叙景』は、ときに波として、飛沫として、霧として、雨として、ほとんどいつも画面の内外を行き来する水の運動によってあらかじめ想定された構図を乱される。
開巻一〇分足らずで映画は、二つのそれぞれに全く異なる美学を提示する。ひとつは撮影された画面の中心に向かって見る者の視線を集める静的な画であり、もうひとつは切り取られたフレームの外から闖入する何かによって絶えず全体像を乱される動的な画だ。それは作者の意図を実現しようとする脚本家の美学と、被写体がやってくるのを待つ撮影の美学とに対応している。あらかじめ想定した意図を実現しようとする脚本家と、予期せぬ不測の事態を作品に取り込もうとする撮影者。序盤からすでに、この映画は、これに限らずそもそも映画というものが相反する二つの美学の対決の場であることを体現している。
つげ義春の二つの漫画を原作とする、三宅唱『旅と日々』は、『海辺の叙景』を原作とする劇中映画とそれを上映する大学の講義らしき場の序盤、その脚本を書いた李が恩師の死に遭遇して気落ちしつつ遺品のカメラを譲り受ける中盤、気晴らしのために雪山に旅行に出かけた先で出くわすつげの『ほんやら洞のべんさん』を原作とした終盤の実質、三部構成で語られるのだが、中盤で李によって奇妙な台詞が発せられる。劇中映画『海辺の叙景』の上映会での質疑応答で、完成した映画を見て李は「自分には才能がないと思いました」と不穏なコメントを残すのだ。多くの観客はこの一言に戸惑うのではないか。なぜなら、夏の風物を映した劇中映画『海辺の叙景』は、他のパートに劣らぬ一級の仕事に見えるはずだからだ(無論、それは実際に三宅唱の仕事だ)。
にもかかわらず、なぜ李はこの劇中映画を見て、自分の才能の欠如を感じたのだろうか。仮説として、劇中映画が達成したのは単に撮影者の美学だけだったということが考えられる。素晴らしい映画はできている、しかしそれは撮影がうまくいっているだけで脚本の意図は失敗し、頓挫し、画面に反映されていない、それゆえに李は落胆している。では、そもそも李が脚本家として意図したこととはなんだったのか。
あえて「とりあえずいっとく」
李の意図とは、なんだったのか。その疑問に答えるまえに、もうひとつテーマを掘り下げる。彼女は今、自分に才能がないと感じるほどに自分に自信がない。なぜ彼女の創造性はそれほど衰弱してしまったのか。中盤のパートに映画のタイトルを交えながら、これが創造性の回復についての映画であることを李自らほとんど説明するシーンがある。

11月7日(金)TOHOシネマズ シャンテ、テアトル新宿ほか全国ロードショー
©2025『旅と日々』製作委員会 配給:ビターズ・エンド
旅に出かける前に一人部屋で過ごす李のモノローグだ。「初めて日本に来た時は周囲が謎や恐怖に満ちていたが、新鮮だったモノや感情たちは今は言葉に追いつかれてしまった。私は言葉の檻の中にいるみたい」。その台詞は言葉に意味を与えられた「日常」と、そこから離れるための「旅」というふうに、タイトルを解説する。日本に来たばかりで、周りから知らない国の言語を浴びせられる「謎と恐怖」に満ちていたという李だが、そのように日本語に触れる中で日本の映画の脚本を描く仕事にありついたのだろう。「謎と恐怖の日々」はおそらく彼女になにかしらの創作意欲を養ったのではないか。だからこそ今、日本語がよくわかるようになったことで、「言葉の檻の中にいるみたい」に彼女の意欲は萎えてしまったのではないか。この後の展開について、この論理を逆回転させて考えてみよう。つまり、再び言葉を失い、謎と恐怖の日々に浸ることができれば、彼女は創作意欲を取り戻すのではないか。旅に託された展開とはそのような創造性の回復のプロセスであるはずだ。
数理モデル学者の郡司ペギオ幸男は、認知におけるある種の粗さを創造性の源に採用して、天然知能と呼んでいる。理学者である彼の理論はここで詳しく説明することも憚れるほどもっと厳密なものだが、その興味深い一例を挙げると「とりあえずいっとく」というものがある。彼が画家の中村恭子のランに関する博士論文審査を担当したときのエピソードだ。繁殖のために自らのめしべをメスのミツバチの形に似せて、受粉のためにオスのミツバチをおびき寄せるランの受粉戦略というのが登場するのだが、郡司はそのオスバチの行動を「とりあえずいっとく」と表現する。オスバチの行動は、ランのめしべに群がるその様子を状況証拠として、めしべをメスバチと勘違いしたのだと外からはみなせるのだが、本当にそれだけオスバチの認知が粗いものなのかどうかは、当事者のオスバチにしかわからない。郡司の仮説は、実際にオスバチの認知が粗いのではなく、メスバチかメスバチでないかはわからないが、メスバチに対してと同じように欲情できる余地があるのならば「とりあえずいっとく」というものだ。この例から郡司は、ひとつには創造性とは、そのような自らの認知の粗さを積極的に受け入れる勘違いのようなものであるという結論を導き出す。これに倣うならば、『旅と日々』の李は旅を通じて「謎と恐怖の日々」を獲得することで、その粗さを取り戻すことが期待されているのではないか。
郡司の方法論についてもう少し細かく触れておこう。彼によれば、創造行為とはトラウマ構造という構造をつくり出して、その中に受動的に身を置くことではじめてやってくるものであり、決して能動的に獲得するものではないという。創造とはやってくる「外部」を捉えるものだというのだ。トラウマ構造とは、二者択一の選択肢を想定し、その両方が成り立つ状態(肯定的矛盾)と、両方が成り立たない状態(否定的矛盾)を想定し、肯定的矛盾と否定的矛盾が両立する状況だという。先のランとミツバチの例ならば、そのメスバチを模倣しためしべというのは、めしべでありメスバチでもある(肯定的矛盾)、一方めしべでもメスバチでもない(否定的矛盾)。つまり、それがめしべであろうが、ミツバチであろうが、なにかオスバチが欲情する要素を満たすなにかしらであればよいのであって、本質はそのなにかしらであるという点では、メスバチであることも十分条件ではない。このようにトラウマ構造を通じて「オスバチが欲情するメスバチではないなにかしら」という外部がやってくるのだ。
では果たして、旅を通じて李はその外部と出会い直せるのだろうか。
小さな魚を捕まえる
『ほんやら洞のべんさん』を下敷きにした終盤は、宿の予約をせずに観光地の冬山を訪れた李が、いくつもの宿に宿泊を断られた末に、べんさんという冴えない男が一人で営む鄙びた民宿を訪れるところから始まる。夜中にふと、別れた女房と彼女が連れて行った娘のことを思い出したべんさんは、彼女の実家に忍び込み、その実家が生業にして育てている観賞用の高級な鯉を盗むことを思い立つ。予期せず李は、べんさんとともにこの杜撰は窃盗に巻き込まれ、べんさんもまた予期せず、雪山を超えた先にある屋敷に作られた鯉の人工池のほとりで娘に遭遇し、彼が娘に「ここで父ちゃんに会ったことは言うな」と口封じをするところに居合わせる。朝になると、池の近くに李が落としていったカメラを手掛かりに警察がべんさんのところを訪ねてくる。どうやら鯉を盗んだことはバレていないようだが、雪山を越えるときに一匹百万円はするというその恋は凍死してしまい、べんさんは落胆する。
旅先で出会ったべんさんの粗い状況判断と行動力が確かに李の凝り固まった現実認識をいくらか緩めたのだろう。李が、べんさんの後をついて「とりあえずいっとく」ことにしたことによって彼女の創造性の回復がここで試みられていることがわかる。しかし、ただ予期せぬことが起きるだけでは足りない。それでは、劇中映画『海辺の叙景』と起きていることは同じなのだ。結論を先取りしていうなら、脚本の美学が撮影の美学と矛盾しない形で成立するためには、あらかじめ意図していたこと(脚本)が、予期せぬ形でやってくる(撮影)ことが必要なのだ。ではあらためて、脚本家、李の意図とはなんだったのだろうか。
三宅はなぜつげの原作からこの二作を選んだのだろう。この二作には、「悲しい話」という共通モチーフがある。序盤、高田演じる男が河合演じる女に、男が幼い頃にここで一年住んでいたときにあった「怖い事件があった」と切り出し、岬の向こうで漁船に子どもを抱いた女性の遺体が引っ掛かっていたという「土左衛門事件」について話すエピソードがある。岬の下がタコの巣になっており、見つかった遺体が白骨化していたというのを聞いて女は「怖いというよりも悲しい話」と、感想を述べるのだが、李は終盤の『ほんやら洞のべんさん』のパートで「悲しい話」という言葉に再会する。
ほんやら洞に泊まった時、べんさんが李の脚本家という肩書きについて印象を語る「ユーモアのあるドラマが見てえ。でも笑いばかりでもあんまり面白くねえ。いい作品はどんだけ人間の悲しさが描かれるかだ」というセリフにそのモチーフは登場する。『海辺の叙景』、李の魚沼との邂逅と別れ、『ほんやら洞のべんさん』、一見ばらばらに見える三つのエピソードを貫くこの「悲しい話」というモチーフの正体は生き物の死である。それで、これは死をテーマにした映画だ、などというといかにも漠然としていて凡庸だが、そうではない。この映画が取り組んでいるのは社会や倫理ではなく、芸術における死の表現の困難についての映画なのだ。脚本家にとって死は予期したり意図したりできるものではなく、撮影者にとって死という概念は直接目に見えるものではない。死はいかにして表現となるのか。そこでトラウマ構造が活躍するのだ。李は、旅の最後の日の朝、バケツの中で凍っている鯉の死体に、トラウマ構造を通じて出会うのだ。
結論はこうである。死そのものは脚本家があらかじめ意図したり、撮影者が直接視覚的に認識したりできるものではない(否定的矛盾)。しかし、李はたしかに死をテーマにした脚本を書くことを望んでおり、そして日常を離れた旅の果てに、偶然凍死した鯉という撮影された画が彼女の目の前に現れた(肯定的矛盾)。彼女は最後にきっと満足したのだ。映画にとって撮影された「死」とはきっとこのようなものだと。
***
超越瞑想によって創作のアイデアを得てきたデヴィッド・リンチは、そのアイデアを魚を捉えることに例えた。バケツの中で凍って死んでいる観賞用の鯉を見て、そのことを思い出す。映画における編集の妙味は、一つのフレームに切り取られることによって、『ほんやら洞のべんさん』のパートで死んでいる鯉が、『海辺の叙景』パートで撮影された海と同じくらい大きな魚にも見えることだ。李は最後、「大きな魚」を捕まえて帰ったのだろう。
〈参考文献〉
郡司ペギオ幸夫著『創造性はどこからやってくるか』2023年、ちくま新書
デヴィッド・リンチ著『大きな魚をつかまえよう:リンチ流アート・ライフ♾️瞑想レッスン』2012年、四月社、草坂虹恵訳