五十嵐耕平監督作『息を殺して』(2015)を観ていて、どうしても拭うことができなかったのは、牛腸茂雄による伝説的な写真集『SELF AND OTHERS』のイメージだった。どちらもの作品も知っている人なら、このように言うだけで「ああ、あのショットか」と思い当たることだろう。二つの作品は、初めいくぶん離れたところから対象を捉えているが、作品中盤、突然ぐーっと被写体に寄る、そしてまた離れていく。『息を殺して』と『SELF AND OTHERS』は、距離に誠実だという共通点があり、五十嵐耕平は「状況」に対して、牛腸茂雄は「人物」に対して、それぞれ適切な距離で向かい合った結果、「引いて、寄って、引く」という同一の構成展開を持つことになった。
このことについて五十嵐に尋ねると、「被写体のそばにいてあげたいなと思うときはカメラが対象に寄るし、少し離れていてあげたいなというときは距離を取る」と述べ、日常生活における他者との距離感を、そのまま映画内の人物に適用していることが分かった。そしてこれはそのまま『SELF AND OTHERS』における、牛腸の被写体に対する姿勢と一致する。この写真集に写っている大人たちは皆、もともと牛腸と親交があった人々で、牛腸の彼らに対する心理的な距離感がそのままレンズと対象との距離に反映されていると言ってよいものだ(撮影時に初めて出会っただろう道端の子どもたち含め、その距離感が写真にはきちんと写し出されている)。
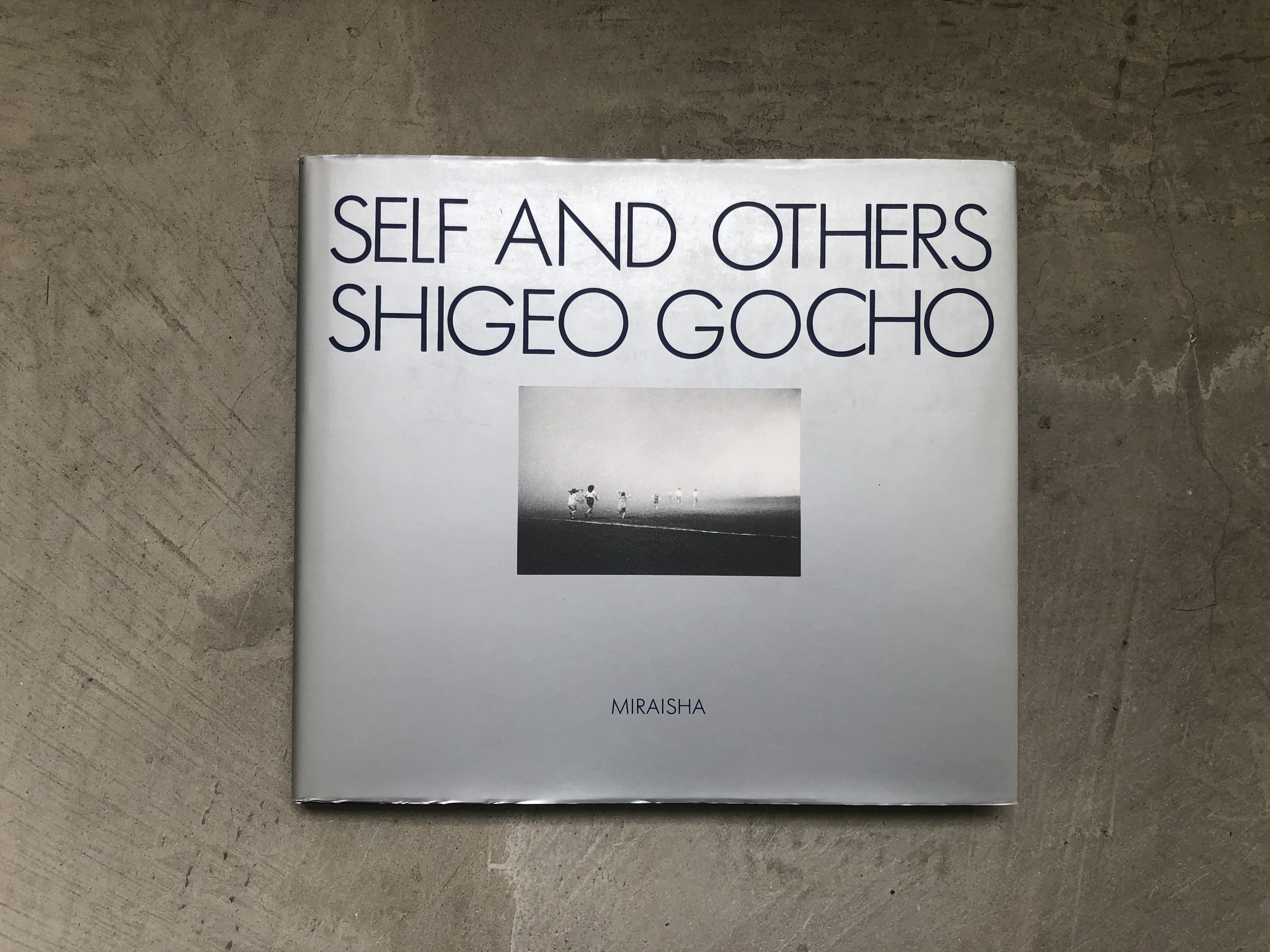
牛腸茂雄『SELF AND OTHERS』(1994年、未来社)
五十嵐耕平がフランス人監督・ダミアン・マニヴェルとともに撮った新作『泳ぎすぎた夜』(2018)もまた、ずいぶん写真的印象を感じさせる映画である。この作品で採用された4:3のフレーミングは、スクリーン特有のワイドサイズよりも私たちが日常で触れるデジタルカメラの画角に近いし(そのことを思い出させるモチーフも作品内に登場する)、電車の乗客役である地元の住人だろう人たちも、動画でありながら固定のバストショットでじっと捉えられることで、かつて日本のリアリズム写真がよく写してきた被写体然とした佇まいを湛えている。
彼の作品に見られるこの写真的印象は、五十嵐作品の多くを担当する撮影カメラマン・髙橋航によるものだろうか。いくつかの作品でスチールを務める龍崎俊もまた、優れた写真家である。彼らのようなカメラマンに囲まれていること、またそうした人々からの信頼を勝ち得ていることも、この不思議な映画監督の性質に迫るキーになるかもしれない。いずれにせよ、五十嵐耕平という映画監督は、まなざすことにとても秀でた人物と思われる。その理由について、『泳ぎすぎた夜』の具体的なショットを挙げて考えてみたい。
*
まず、この作品ではカメラはほとんど動かない。動くとなれば、主人公の少年の移動に寄りそうときである。そのため、たとえカメラが静止している場合でも、少年の動向を見守るような視線がファインダーにやどり続ける。写真家・ホンマタカシがこの作品に対し、「五十嵐&ダミアンの、いわゆる「はじめてのお使い」ですね、微笑」*1 とコメントを寄せたのも道理で、いくらか離れた場所から主人公の少年を見つめるような印象が常に漂っている。
少年を捉えるカメラも、行く先々で彼と同じ空間を過ごすことになる大人たちも(電車の乗務員、乗客、タクシーの運転手、モールの無料給水に並ぶ人、父親でさえ)、彼にただ一つのアクションを起こしはしない。遭遇し、立ち会い、少年を見るだけだ。ただ一人を除いて。そしてその唯一例外の人物こそ、この作品においてもっとも見ることを意識させられるシーンに現れる。
作品の終りに向かい、少年は見知らぬ人の車に入り込み、「3匹のくま」や「白雪姫」の主人公さながら自分が帰属しない空間で寝入ってしまう。このシーンにおける画面レイアウトがとても特徴的だ。後部座席で横になっている少年のアイレベルから、フロントガラスにあるバックミラーが写される。ミラーには運転手の両目が写っているが、その視線が少年を見つけることはない。運転手の男はカーステレオで音楽を流しているため、少年が奏でる寝息や衣擦れの音に気づかない。その様子が眠っている(目を閉じている)少年の目線から捉えられるのである。このショットの緊張感はおそろしい。なぜなら、それまでずっと映画のカメラフレームから見られる対象であった少年、そのまなざしが突如スクリーン、および観客の目と同化しながら運転手の男を目を閉じながらにして見つめるのである。この男は少年に偶然選ばれたにすぎない市井の人であり、観客と同じくらい匿名・一般的である。結果、男は少年を家に送り届ける役目を担い、眠っている主人公を抱えるという、劇中唯一少年に触れる人物となる。閉じた目とミラー越しの視線という、特異な「見る/見られる」の相互関係を持った男だけが、少年との距離を消失し、接近し、彼に触れる。
『泳ぎすぎた夜』におけるこのショットは、冒頭で述べた『息を殺して』と『SELF AND OTHERS』における「あのショット」に相当するものだろう。『息を殺して』においては、主人公の女性が、亡くなった父と接触する瞬間、カメラはいっとう彼らに引き寄せられる。『SELF AND OTHERS』では、ほとんどの被写体がフルショットで捉えられている中、写真集中盤に組まれた牛腸の母のものだけが、大変な至近距離で撮影されている(この2つのショットは偶然にも、父と娘、母と息子における言語化されない親子の関係性を捉えているという共通点もある)。『泳ぎすぎた夜』における少年の閉じた目と、鏡像に写った男の目という、錯視乗算的な「見る/見られる」の相互性による距離の消失は、『息を殺して』と『SELF AND OTHERS』における対象間同士の心象的な距離を、被写体と撮影者の距離に置換する方法論と同質である。見ることと見られること、あるいは、互いの「見る」というまなざしの融和によって、人は他者との距離を狭めていく。

『泳ぎすぎた夜』(2018年、五十嵐耕平監督)©2017 MLD Films / NOBO LLC / SHELLAC SUD
このようなショットを通し、五十嵐耕平の作品からは、被写体や状況に対する撮り手の誠実さが感じられるのである。冒頭で引用した彼の劇中の人物に対する姿勢、他者に対する距離感は、私たちが普段の生活で行なっているとても自然なことなのに、私たちはカメラを構えると、なぜかカメラの向こう側の人物、被写体に対して横暴なふるまいをしてしまう。それはカメラが持つ一方向性、一方的に見るという視線の暴力性の問いよりも、ファインダー越しの世界に対する節度の問題だろう。向こう側の世界は現実と異なるのだから、現実世界で遠慮しているふるまいを行なってもよいのだとしたとき、あちらとこちらという世界の分断が生じる。
映画のカメラはこれまで、そして今でも、基本的にはカメラの存在、つまりはフィクション性を観客に忘れさせようと尽力してきた。映画における作品世界が作られたものであることを隠そうとしたり、あるいは作られたものであることを過剰に示そうとしたりしてきた。そのような態度に、五十嵐は少しも気を払わない。映画の内も外も、キャラクターも俳優も隔たりなく、フラットな姿勢で接する(彼が作品の役名と俳優の実名を分けないことからも、この意識が感じられる)。そしてこの写す対象や状況に対する均質的な姿勢が、写真表現におけるカメラの等価性を感じさせる作品との印象の一致を招くのではないか。カメラの等価性とは、ファインダーのあちらもこちらも等しいものとして、ただ写す、ただ撮るということだが、実際これはとても難しい。カメラを用いれば、エフェクトやフィルター、演出によって向こう側の世界をいくらでも誇張することができるが、同時にとても率直に被写体を「見る」ことができる。そして当然、後者の方がごまかしが効かない。
牛腸茂雄の写真作品が現在なお有効であり続けるのは、写真でも映画でもカメラを介して他者と向き合うということが、そう容易なことではないからだ。そして五十嵐は、映画という写真よりも創意が生じやすい領域で、彼のまなざしをもって他者や出来事、状況と向き合う。この点が彼の映画作品の一つの魅力だろう。カメラの向こう側の世界が、自分のいる世界と同じ世界であること、カメラのファインダーによって分断や転換は起こらないのだということが、ごく自然な態度として行われているように感じる。
さて、『泳ぎすぎた夜』は幼い少年の冒険譚である。冒険譚ではあるのだが、主人公を阻む敵は現れないし、意地悪な叔母や老人も登場しない。雪原を超えて、離れた場所にいる父に会いに行くというドラマティックな筋書きを持つのだが、いくつかの困難を乗り越えた末にその目的が果たされるというわけではない。相棒となるはずの子犬とは一期一会の不確かな共鳴を果たすのみ、旅の協力者は市場に向かっているはずの少年をむしろ自宅に送り届ける。主人公の少年は眠り続け、協力者の存在を認識することもない。自然は脅威であると同時に心地よく、襲われたときには偶然と、人工物である車が彼をフォローしてくれる。『泳ぎすぎた夜』には、いわゆるマザータイプやテンプレートとしての物語がない。そのため観客は可視化されたストーリーテリング以外の、さまざまな事象や関係性を見つけることになるだろう。
家から一歩も出ない二人の女性(主人公の母と姉)は不在の男たちを暗喩するテレビモニターの中にいるだろう男性をじっと眺め(メガネまでかけて)、主人公の少年は自分で撮影したデジタルカメラのモニターを見る。少年は幼くも自前のデジタルカメラを所有するカメラマンであり、自室の天井、あるいは虚空をぼんやりと見つめる。しかし、実際のところ彼が何を眺めているのか、私たちには分からない。観客はそうした彼らの姿を眺めながら、五十嵐耕平やダミアン・マニヴェル、この映画を作った人たちが持つ「見ること」の姿勢を共有するだろう。スマートフォンカメラの、即座に撮れるというアクセシビリティの向上から、「見ること」と「撮ること」という異なる行為があっけなく同等のものとしてすり重ねられ、ときにその露悪性が取りざたされる現在、『泳ぎすぎた夜』における「見ること」と「撮ること」の共生は、とても心惹かれる視点として映画のスクリーンに映し出されている。
*1 「はじめてのお使い」は、初めて一人でお使いを行う子どもの動向を遠方から追跡、撮影するドキュメントタッチのテレビ番組である。











