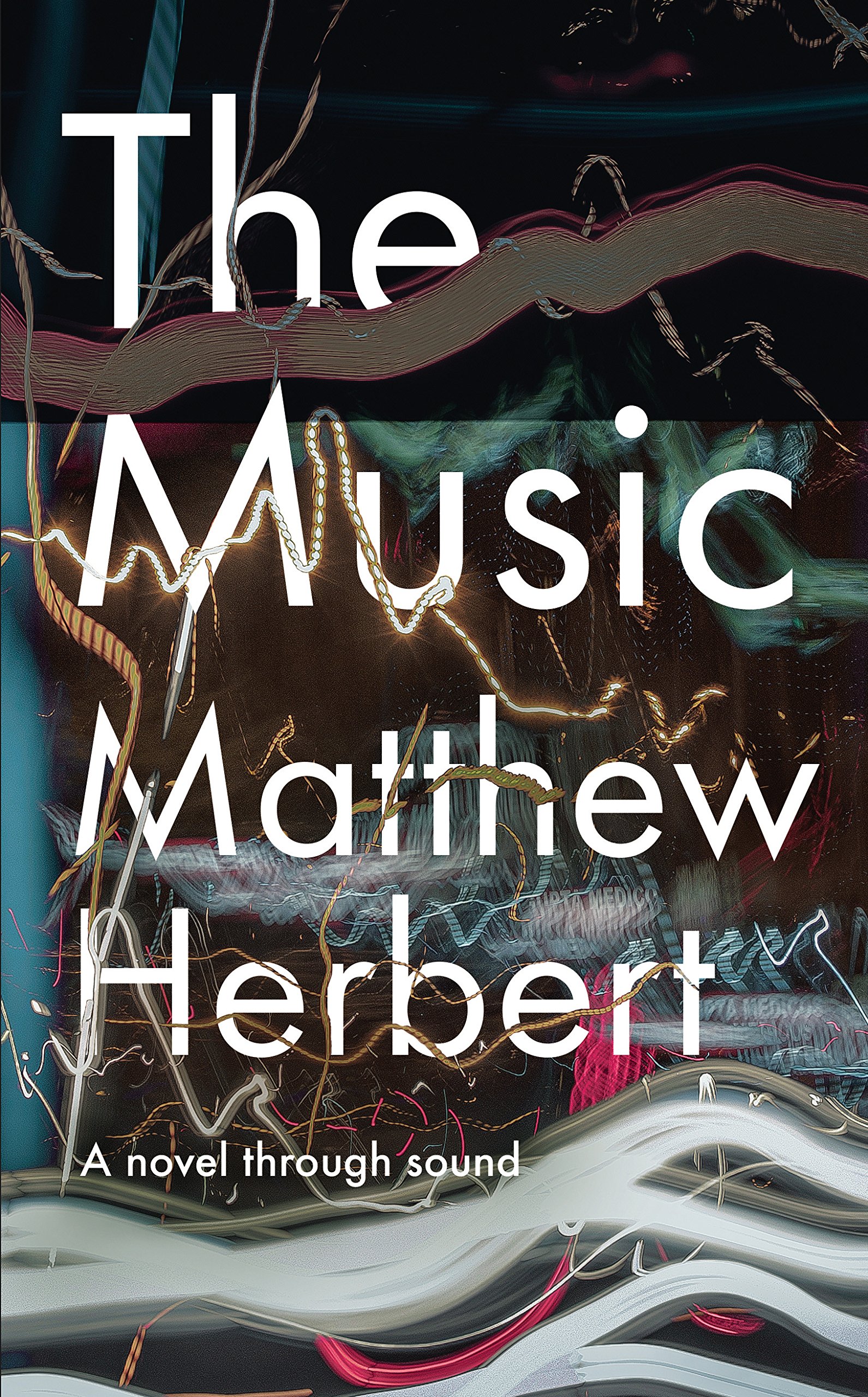Matthew Herbert, The Music: A Novel Through Sound (5 April 2018, Unbound)
Matthew Herbertは90年代からDoctor RockitやHerbertなどの名義で活動をつづけるエレクトロニック・ミュージック界の奇才である。アルバムごとに使うサンプルのソースに特定のテーマを設けたコンセプチュアルな作風や、オーケストラやビッグバンドを従えたいささか奇抜なライヴパフォーマンスは、彼をある種のマッドサイエンティストのように見せる。しかし、その活動は単に奇抜であったり他の実践から異質であるばかりではなく、サンプリングという手法に対する高度な批評たりえている。
そんなHerbertが発表した「アルバム」が、この小説、“The Music: A Novel Through Sound”だ。奇抜な、いわばノヴェルティ的な作品ではないかという予感は半分当たっていて、想像通りというか、物語が読者をよろこばせるような類のものでは決してない。ただひたすらに、奇想に満ちたサウンドが言葉を通して記述され、前書きによれば全部でおおよそ1時間に及ぶとされる「アルバム」をかたちづくっている。とはいえ、小説と呼ぶにも、あるいは音楽と呼ぶにも似つかわしそうもないこの長大な「文字によるアルバム」――副題は「音による小説」と名乗ってはいるのだが――は、単なるアーティスティックな気まぐれの産物などではない。サンプリングという手法、ひいてはそれによってかたちづくられる音楽に対するステイトメントのごとく読むことも充分に可能だ。
「P.C.C.O.M.」と録音芸術の限界
2000年にHerbertが発表したマニフェスト「P.C.C.O.M.(=PERSONAL CONTRACT FOR THE COMPOSITION OF MUSIC)」は、サンプリングを含む現代的な楽曲制作に、いささか不条理なまでの厳しい制約を課すものだった。サンプルであれプリセット音源であれ、自分がつくりだした以外のあらゆるサウンドの使用は堅く禁じられる等々、マゾヒスティックでさえある「縛りプレイ」が以降の彼の活動の中核に据えられることになる。加えて、その制約は2005年の「P.C.C.O.M. Turbo Extreme」ではより過激になる。ここで付け加えられた条項のなかでも彼の活動との関係でもっともわかりやすいものは一番目の項目だろう。
「一、トラックの主題が決定されたあとは、そのトピックに直接関係のあるサウンドのみ使用されうる。たとえば、もしそのトラックがコーヒーに関するものならば、次のようなサウンドが含まれうる。コーヒー農場主とその縁者によってつくられたサウンド。カップやスプーン。ミルク。コロンビア、等々。」
この条項はすぐさま、人体から採取したサウンドでつくられた『Bodily Functions』(2001年)であるとか、あるいはひとりの人間、ひとつのクラブ、一頭の豚をモチーフにした一連の「ONE」シリーズ(『ONE ONE』『ONE CLUB』ともに2010年、『ONE PIG』2011年)を想起させる。こうした「縛り」をもってなお、これらの彼の作品がすこぶるポップに響くことは驚異的である。
しかし、彼の作品の卒ないエレガントさは逆説的に次のようなことを明るみに出す。それはサンプリングに限らずレコードなりCDなりにサウンドを詰め込んでいく、という過程こそが最大の制約なのではないか、ということだ。個人的によく引き合いに出す表現として、「ミックス(ダウン)は社会性」、という細野晴臣の金言がある。いわずもがな、録音物として市場に流通させるためには特定の規格に適合するようにチャンネルを整理し、長さを切り詰め(あるいは引き伸ばし)、それ相応の音質なり音量、あるいはダイナミックレンジへと収める必要がある。製品として完パケすることと、作り手自身がスタジオのなかで完成を意識することには埋められない溝がある――あるいは頭の中で鳴っている音楽と、完成したそれとの間にも同じような溝があるかもしれない。
サウンドが意味を語ることは可能か?
実際、2015年に行われたインタビューでHerbertは本作執筆の動機を次のように語っている。
[……]僕がこの世界のサウンドをどう捉えているのかを要約したようなものというか。ただ最近になって、そんなサウンドを、リアルな実生活の中で、自分の生きているうちに音を用いて表現するのは不可能だと気づいたんだ。そうであれば、想像しているサウンドを言葉を駆使して表現するのが唯一の選択肢だと思ったのさ。
[……]『LIFE IN A DAY 地球上のある一日の物語』という映画の音楽に僕は携わったんだけど、そこでみんなの〈お気に入りの音〉というのを使いたくて一般募集することにした。それで集まったものを、試しに一斉再生してみたんだ。実際に音を出してみようか(屈んでPCを取り出し、iTunesを操作しだす)。これから鳴らすのは、465人分の〈お気に入りの音〉を同時に鳴らしたものだ。それは僕にとって、世界が僕らを滅ぼそうとしている音に聴こえるんだよ
これでたったの465人分だからね。地球上には何億人も住んでいるわけで、彼らをみんな集めて、同じことをやってみたらどうなるんだろう。その音は想像することはできても、楽器やコンピューターでは表現しきれるはずもない。だから言葉で書くしかなかったんだ〔1〕
本書の冒頭に収められた「前奏曲(prelude)」は、太平洋のどこかに口を開けた海溝の奥深くに設置されたマイクと聴音機、そしてスピーカーから発される音の描写から始まる。それは理屈でいえば不可能ではないにせよ実現することはほとんど不可能な未知のサウンドの世界を想起させる。そして、このシステムで鳴らされるのは世界中から採取される眠る人びとの様子であり、実は地球外のなにものかがただひとつ目覚めたまま、これらに耳を傾けていることが示される。ここまで手のこんだSF的なギミックが登場するのは「前奏曲」と終章の「ディミヌエンド(Diminuendo)」くらいだが、世界中のあらゆる場所で並行して生じては消えてゆくサウンドをあたかも地球外の超越的な場所から聴取するかのような描写は本書に一貫している。サンプリングという手法、あるいはそもそも録音技術一般がもたらす聴取の経験は、同時には存在しえないものが媒体の上で共存してしまうことがもたらす不可解さを伴う。その戯画として卓抜した導入と言えよう。
とりわけ、さまざまな来歴を持ち、地理的にもスケール的にも隔たった多種多様なサウンドの列挙は重要な意味を持つ。それは、互いに無関係なものの遭遇というシュルレアリスト的な奇想と同時に、世界におけるサウンドの遍在を強く示唆するからだ。これだけ執拗な記述によるマキシマリズムをもってしても本書はあらゆる可能なサウンドを包摂するには至っていないように思える。となれば、Herbertが常に制作にあたってなんらかのモチーフを設定し、「P.C.C.O.M.」のような制約を自らに課すかも理解できる。あまりにも過剰にサウンドがあふれているなかでなにを選び取るかに意義をもたせることは、制作の別のプロセス――作曲、加工、アレンジ等々――にリソースを割くことにもなる実利的な側面もある。
そして、主題を設定することはすなわちサウンドに文脈を担わせること、少なくともそう明示することにつながる。本書では、あらゆるサウンドが固有名詞やアイデンティティポリティクス、あるいは社会問題を示唆する文脈と結び付けられ、サウンドのマキシマリズムとともに意味のマキシマリズムも志向されている。今日のポップミュージックに何気なくサンプリングされる具体音もまた実際にはこうした意味の過剰に晒されうるし、Herbertはまさにそうしたサンプリングミュージックの文脈形成能力を社会批評や政治的プロテストにも接続してきた。しかし本書の文脈への志向は同時にサウンドのみ提示されては感取できないものでもある。それはあたかもあらゆるサンプルが持つ来歴と、サンプリングされることでその来歴が切断されるアンビバレンスが描かれているようでもある。サウンドが背後に従える文脈の雄弁さと、サウンドそのものの物言わぬ空虚さの両面が逆説的に浮かび上がる。
おわりに
破壊的なまでの騒音を感じさせる第11章「モデラート(moderato)」のクライマックスはその点で興味深い。ここでは、それまでもっぱら不定冠詞のついた「とある○○(a/an xx)」どもの放つサウンドの集積であったものが、いつしか「すべての○○(all/every xx)」によるサウンドの列挙に変わる。内容も徐々に平和や理想的な世界へと漸近し、さらにはダンスフロアや各々の場所で人びとが音楽を分かち合い享受する瞬間へとフォーカスしていく。このクライマックスはちょっとクドいほど感動的に思えた。Herbertの頭の中で鳴っているサウンド、そのサウンドが彼のなかに描き出すヴィジョンの描写として、あまりにもしっくりくる。
演奏され、録音物のなかにつめこまれたサウンドは、この世界に満ちるサウンドの総体へとイマジネーションを跳躍させるにはあまりに寡黙である。思いを馳せることによってのみ到達しうるサウンドへの傾聴がありうる、という例示として、本書は稀有な体験をもたらしてくれる。相応の辛抱強さがなければ通読するのも難しいが……。
Imdkm(ブロガー、フリーライター)
[1] Mikiki「ハーバートが音楽を語る―ジャズとクラシック、『Bodily Functions』と『The Shakes』、想像のサウンドを記した自著」http://mikiki.tokyo.jp/articles/-/8260(2015年9月16日掲載、2019年4月22日最終閲覧)